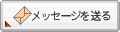2007年01月28日
芋の時代
芋の時代
'んむ ぬ じだい
'Nmu nu jidai
語句・んむ 'Nmu 芋。甘藷(サツマイモ)。ちなみに「たーんむ taa'Nmu」は里芋科の水芋。「ちんぬく」chiNnuku も里芋。
作詞 浦崎 芳子 作曲 普久原 恒勇
一、夜明けしらじらあかとんち 鶏の唄いる声聞けば 我ったアンマーちがきみそーち シンメーナービに芋煮みそーち 子の達 朝の目クファヤー
ゆあきしらじら'あかとぅんち とぅいぬ'うたいるくいちきば わったー'あんまーちがきみそーち しんめーなーびに'んむにみそーち っくわぬちゃー 'あさぬみーくふぁやー
yuaki shirajira 'akatuNchi tui nu 'utairu kui chikiba wattaa 'aNmaa chigakimisoochi shiNmeenaabi ni 'Nmunimisoochi kkunuchaa 'asa nu miikuhwayaa
〇夜が明け、しらじらと少し明るくなって ニワトリの唄う声を聞いたので うちのお母さんは励みなさって シンメー鍋で芋を煮なさって 子ども達の朝の目覚まし(だ)
語句・あかとぅんち 今帰仁方言に「はーとぅんち」があり、意味は「暁。夜明け。明け方。」【今帰仁方言音声データベース】。「はー」は「赤」のこと。「とぅんち」は不明。首里語を扱った【沖縄語辞典(国立国語研究所編)】(以下【沖辞】と略す)にはない。一般にウチナーグチでは「明け方」は「あかちち」「あきがた」「ゆあき」。・ちがきみそーち 励みになられて。<ちがきゆん。 「精出す。(仕事などに)励む。」【沖辞】。励む(気+kakiyuN)+みせーん ・・される の連用形。・しんめーなーび シンメー鍋。直径が50〜100cmほどの大鍋。シンメーの意味は4枚の鉄板で作るので「四枚」→シンメー という。 ・っくゎ 子ども。発音は最初に「っ」がつくので注意。声門破裂音という。「くゎ」の最初の「く」と音がでるまえに口の奥を閉じておいて少し空気を溜めて軽く吐き出しながら「く」と発すると「っく」になる。ちなみに「人」も「っちゅ」と発音する。・みーくふぁやー「目ざまし。おめざ。朝などに目を覚ました時に与えるお菓子の類。」【沖辞】。
・っくゎ 子ども。発音は最初に「っ」がつくので注意。声門破裂音という。「くゎ」の最初の「く」と音がでるまえに口の奥を閉じておいて少し空気を溜めて軽く吐き出しながら「く」と発すると「っく」になる。ちなみに「人」も「っちゅ」と発音する。・みーくふぁやー「目ざまし。おめざ。朝などに目を覚ました時に与えるお菓子の類。」【沖辞】。
二 笑いはっちりとーる熱芋や フーフーまーさぬぬくたまて アンマーが煮ちえる芋の味へ ぬーでぃーくぃーくぃーちーちーかーかー 茶もカティガティーまーさ味
わらい(われー)はっちりとーる 'あち'んむや ふーふーまーさぬ ぬくたまてぃ 'あんまーがにちぇーる'んむぬあじぇー ぬーでぃーくぃーくぃーちーちーかーかー ちゃーんかてぃがてぃまーさあじ
warai(waree) hacchiritooru 'achi'Nmu ya huuhuu maasanu nukutamati 'aNmaa ga nicheeru 'Nmu nu 'ajee nuudii kwiikwiichiichiikaakaa chaaN kadikadi maasa 'aji
〇笑いがはちきれている熱い芋は フーフー美味しいので温もって お母様が煮ている芋の味は喉にひっかっかってお茶を飲み飲みしながら美味しい味(だ)
語句・わらい 笑い。ウチナーグチでは「われー」。CDでは「わらい」と唄われている。・はっちりとーる はちきれている。<はっちりゆん。「はち切れる」【沖辞】。・ふーふー 熱くて息を吹きかける様。ふーふー。・まーさぬ 美味しいので。形容詞の最後を「ぬ」にすると「・・ので」と理由をあらわす。・ぬくたまてぃ 暖まって。<ぬくたまゆん。「暖まる。体などが暖かくなる。」【沖辞】。・ぬーでぃー 喉。・くぃーくぃー 見あたる語がないが、「ぬーくぃー」(何やかや)「ぬーんくぃーん」(何もかも)【沖辞】というように語呂合わせで「ぬーでぃー」を補なっているのではないか。・ちーちーかーかー 「食べ物が胸につかえる様」【沖辞】。・ちゃーんかでぃかでぃ 茶も食べ食べ(する時には飲んで)。
<ちゃー(茶)+ん(も) +かでぃかでぃ (かぬん 食べる 同じ言葉を繰り返して強調する畳語)・まーさあじ 美味しい味。<まーさん。+あじ。味。
三 寒くなりばんうびんぢゃち 暑くなりばんうびんぢゃち クーフチ芋の熱コーコーから クラガー 百号 イナヨー芋から 面影立ちゅさあの時分
ふぃーくなりばん 'うびんじゃち ’あちくなりばん 'うびんじゃち くーふち'んむぬ'あちこーこーから くらがーひゃくごー 'いなよー'んむから 'うむかじたちゅさ 'あぬじぶん
hwiiku naribaN 'ubiNjachi 'achikunaribaN 'ubiNjachi kuuhuchi 'Nmu nu 'achikookoo kara kuragaa hyakugoo 'inayoo 'Nmu kara 'umukaji tachusa 'anujibuN
〇寒くなっても思い出し 暑くなっても思い出し 粉吹き芋が出来たての熱々で クラガー百号 イナヨー芋で 面影がたつよあの時分の
語句・ふぃーく 寒く。<ふぃーさん(形)。・なりばん なった時も。<なり+ばー(時)+ん(も)・うびんじゃち思い出して。<'うび'んじゃしゅん 。思い出す。・くーふち 粉吹き。・あちこーこー「ほやほや。煮えたばかりのさま。また料理の熱いうちに」【沖辞】。料理が出来たてのほかほか熱いさまをこういう。・からで。・くらがーひゃくごー クラガー百号という「甘蔗の一種。上等な品種」【沖辞】。「暗い井戸で見つかった」から「暗井戸(ガー)」。・いなよー不明。これもたぶん芋の種類であろう。。
四 クバ笠かんとて夏の日も 冬の寒さる雨の日も むのーちゅはーら腹一杯かで根気ちきやいうみはまりんでち 親のかまちゃる芋の味
くばがさかんとーてぃなちぬふぃーん ふゆぬふぃーさる'あみぬふぃーん むのー ちゅはーらはら'いっぱいかでぃ くんちちきやい'うみはまんでぃち 'うやぬかまちゃる 'んむぬ'あじ
kubagasa kaNtooti nachi nu hwiiN huyu nu hwiisaru 'ami nu hwiiN munoo chuhaara hara 'ippaikadi kuNchi chikiyai 'umihamaNdichi 'uya nu kamacharu 'Nmu nu 'aji
〇クバ笠をかぶって夏の日も 冬の寒い雨の日も 食べ物をお腹一杯食べて根気をつけて励む(ことができる)と言って親が食べさせてくれる芋の味
語句・くばがさ クバの葉で作った笠。・かんとーてぃ かぶっていて。<かんじゅん 「かぶる」【沖辞】。 ・むのー 食べ物を。<むぬ(食べ物)+や 融合してnoo となる。・ちゅふぁーら 「腹一杯。満腹」「十分」【沖辞】。・くんち 「根気」。元気、というくらいに使われる。・ちきやい つけて。<ちちゅん。付く。・うみはまんでぃち 励む(ことができる)と言って。<うみはまゆん。励む。没頭する。 + んでぃち。と言って。
五 三度三度のはんめーや 芋と塩小し腹みちて 命つぃなぢゃるあの志情や 忘てーならんさ親の恩儀 いちぐいちまで忘んなよ
さんどぅさんどぅぬはんめーや 'んむとぅまーすぐわーしわたみちてぃ 'いぬちちなじゃる'あぬしなさきや わしてーならんさ'うやぬ うんじぇー 'いちぐ'いちまでぃわしんなよー
saNdusaNdu nu haNmee ya 'Nmu tu maasugwaashi wata michiti 'inuchi chinajaru 'anu shinasaki ya washitee naraN sa 'uya nu uNjee 'ichigu'ichimadi washiNna yoo
〇三度、三度の食料は芋と塩でお腹を満たして、命(いつもの元気)を繋いでいるあの志情けは 忘れてはならないよ 親の恩義は一生何時までも忘れるなよ
語句・はんめー糧食。食料。・し で。・うんじぇー 恩義は。<うんじぇー<うんじ。恩義+や。は。融合して、うんじぇー。
(コメント)
沖縄で人気がある新民謡のひとつ。
一昔前の沖縄の普通の家庭の食事を支えていた芋(んむ)。
曲は、テンポがよくエイサー曲にも使われている。
お母さんが朝早くから芋を煮て子ども達に食べさせる。
笑いがこぼれる食卓、できたてをフーフーしながら喉に詰まらせる子どもたちに
お茶を飲み飲み食べないなさいと。
そして子ども達も大きくなり、振り返る。寒くて暑くても思い出す、あのいろいろな芋の味。
クバ笠をかぶった夏も寒い冬もお腹を一杯にして根気をつければ頑張れる、と親がいつも
いって聞かせてたべさせてくれた、あの味。
まずしかったけれど、芋と塩だけで元気、命を繋いでくれた親の情け、恩義は絶対に忘れてはいけない。それを受け継いでいくかなくては。
というような意訳。
私のこどものころ(1959年生まれ)でも、芋はよくたべさせられた。
おやつに、ご飯にまぜて。
さすがに子どものころは「もう、いらん〜」といっていたが、
年をとると芋の味は懐かしい。
朝食を食べない、食べさせない家庭が増え、すぐに「切れる」子どもが増えた。親も格差社会で、苦しみながら、ついついコンビニの食事に頼る親の責任も重いが、社会の構造にも問題がある。
しっかり朝ご飯を食べる、手作りのものを食べる、親が昔からの食事を見直し子どもに伝える。
こんなあたりまえのことがおろそかになっている時代になった。
昔の人のバトンをどこかに落としてしまったのだ。
次の世代、私たちは何のバトンを渡そうか。
【芋の琉球、本土への伝搬】
野国総管
琉球に芋(現在の甘蔗、唐芋、サツマイモ)が伝わったのは1605年。現在の嘉手納にあたる野国村(ぬぐん)生まれの野国総管(総管とは進貢船の役職名。本名は「与那覇松」だと言われている。)が明(中国)の福州から持ち帰った甘蔗の苗を植えたことに始まる。
台風などによる天災により旱魃や飢饉をなんとかしたいという思いであったという。
儀間真常
野国総管が持ち帰り栽培した芋を儀間村生まれの儀間真常が琉球各地に広めた。これが種子島(1698年)、薩摩(1705年)に伝わる。
薩摩では「唐芋(カライモ)」と呼ばれた。
江戸には青木昆陽によって伝わった(1734年)。栽培方法が確立し全国へ広まった。江戸で「薩摩芋」と呼ばれた。
宮古島には別のルートで甘蔗が伝わった(1597年)。
このように芋(甘蔗、サツマイモ)は中国から琉球を経て薩摩や本土に広がっていったのである。

(嘉手納町にある野国総管を祀る神社)

(同上)

(説明板)
2016年10月28日に筆者撮影。
【「あかとぅんち」を巡って】
一番の歌詞に出てくる「あかとぅんち」。なんとなく意味はわかるようで、わからない。
なんとなく「あかつき」にも似てるから、そうなんだろうと歌っている方も多い。
沖縄語辞典(国立国語研究所編)、琉球語辞典(半田一郎)にも「あかとぅんち」の項はない。
SNSのfacebookに「うちなーぐち講座」というグループがあり、そこで伺ってみた。
沖縄で現在「あかとぅんち」を使っているかどうか、と。すると、「聞いたことがない」という返事を頂いた。また、この作詞をされた浦崎芳子さんは伊江島だから「伊江島ムニー」(伊江島の言葉)かもしれないというご示唆も受けた。
それで今帰仁方言音声データベースで検索すると、「あかとぅんち」ではなく
ハートゥンチ (名詞)暁。夜明け。明け方。
という言葉が出てきた。
さらに「ハー」を検索すると
ハー (名詞)赤。haa<aka あかーともいう。
と出てきた。
実際に伊江島ご出身の方に、上述の「うちなーぐち講座」の方が伺ってくださったところによると
アハトゥンチという。暁、夜明け、朝陽に使う。
つまり、暁の意味で、伊江島ではアハトゥンチ、今帰仁ではハートゥンチということがわかった。
つまりこの歌の作者浦崎芳子さんは、自分のシマ(故郷)の言葉で「あかとぅんち」という語句を選択されたのだ。
ところで「とぅんち」とはなにか。
普通は「殿内」と書く「大きなお屋敷」と思う。
しかし、それでは「あかどぅんち」というように連濁のために「どぅ」となるだろう。例えば「ぬんどぅんち」(ヌールーぬ屋敷) などのように。
暁(あかつき)を語源辞典でみると
あか、とき。だという。奈良時代はそうであり、その後、あかつき、になったとある。
すると琉球では、
あかとき、が、あかとぅき、に変化し、あかとぅんち、になったと考えるのも不自然ではない。
沖縄古語辞典の「あかつき」の項に
「アカツィチ 明け方。夜明け。『あかつき』の古形は「あかとき」(明時)で、沖縄北部方言にはアカトゥンチがある」
とある。
奈良時代は「あかとき」、平安時代以降は「あかつき」に変化していく前の「あかとき」が北部には残っていて「あかとぅんち」になったということだ。
私たちはこの「芋の時代」を歌うたびに、奈良時代の「あかとき」の痕跡を残す「あかとぅんち」という言葉を歌っていることになる。
'んむ ぬ じだい
'Nmu nu jidai
語句・んむ 'Nmu 芋。甘藷(サツマイモ)。ちなみに「たーんむ taa'Nmu」は里芋科の水芋。「ちんぬく」chiNnuku も里芋。
作詞 浦崎 芳子 作曲 普久原 恒勇
一、夜明けしらじらあかとんち 鶏の唄いる声聞けば 我ったアンマーちがきみそーち シンメーナービに芋煮みそーち 子の達 朝の目クファヤー
ゆあきしらじら'あかとぅんち とぅいぬ'うたいるくいちきば わったー'あんまーちがきみそーち しんめーなーびに'んむにみそーち っくわぬちゃー 'あさぬみーくふぁやー
yuaki shirajira 'akatuNchi tui nu 'utairu kui chikiba wattaa 'aNmaa chigakimisoochi shiNmeenaabi ni 'Nmunimisoochi kkunuchaa 'asa nu miikuhwayaa
〇夜が明け、しらじらと少し明るくなって ニワトリの唄う声を聞いたので うちのお母さんは励みなさって シンメー鍋で芋を煮なさって 子ども達の朝の目覚まし(だ)
語句・あかとぅんち 今帰仁方言に「はーとぅんち」があり、意味は「暁。夜明け。明け方。」【今帰仁方言音声データベース】。「はー」は「赤」のこと。「とぅんち」は不明。首里語を扱った【沖縄語辞典(国立国語研究所編)】(以下【沖辞】と略す)にはない。一般にウチナーグチでは「明け方」は「あかちち」「あきがた」「ゆあき」。・ちがきみそーち 励みになられて。<ちがきゆん。 「精出す。(仕事などに)励む。」【沖辞】。励む(気+kakiyuN)+みせーん ・・される の連用形。・しんめーなーび シンメー鍋。直径が50〜100cmほどの大鍋。シンメーの意味は4枚の鉄板で作るので「四枚」→シンメー という。
 ・っくゎ 子ども。発音は最初に「っ」がつくので注意。声門破裂音という。「くゎ」の最初の「く」と音がでるまえに口の奥を閉じておいて少し空気を溜めて軽く吐き出しながら「く」と発すると「っく」になる。ちなみに「人」も「っちゅ」と発音する。・みーくふぁやー「目ざまし。おめざ。朝などに目を覚ました時に与えるお菓子の類。」【沖辞】。
・っくゎ 子ども。発音は最初に「っ」がつくので注意。声門破裂音という。「くゎ」の最初の「く」と音がでるまえに口の奥を閉じておいて少し空気を溜めて軽く吐き出しながら「く」と発すると「っく」になる。ちなみに「人」も「っちゅ」と発音する。・みーくふぁやー「目ざまし。おめざ。朝などに目を覚ました時に与えるお菓子の類。」【沖辞】。二 笑いはっちりとーる熱芋や フーフーまーさぬぬくたまて アンマーが煮ちえる芋の味へ ぬーでぃーくぃーくぃーちーちーかーかー 茶もカティガティーまーさ味
わらい(われー)はっちりとーる 'あち'んむや ふーふーまーさぬ ぬくたまてぃ 'あんまーがにちぇーる'んむぬあじぇー ぬーでぃーくぃーくぃーちーちーかーかー ちゃーんかてぃがてぃまーさあじ
warai(waree) hacchiritooru 'achi'Nmu ya huuhuu maasanu nukutamati 'aNmaa ga nicheeru 'Nmu nu 'ajee nuudii kwiikwiichiichiikaakaa chaaN kadikadi maasa 'aji
〇笑いがはちきれている熱い芋は フーフー美味しいので温もって お母様が煮ている芋の味は喉にひっかっかってお茶を飲み飲みしながら美味しい味(だ)
語句・わらい 笑い。ウチナーグチでは「われー」。CDでは「わらい」と唄われている。・はっちりとーる はちきれている。<はっちりゆん。「はち切れる」【沖辞】。・ふーふー 熱くて息を吹きかける様。ふーふー。・まーさぬ 美味しいので。形容詞の最後を「ぬ」にすると「・・ので」と理由をあらわす。・ぬくたまてぃ 暖まって。<ぬくたまゆん。「暖まる。体などが暖かくなる。」【沖辞】。・ぬーでぃー 喉。・くぃーくぃー 見あたる語がないが、「ぬーくぃー」(何やかや)「ぬーんくぃーん」(何もかも)【沖辞】というように語呂合わせで「ぬーでぃー」を補なっているのではないか。・ちーちーかーかー 「食べ物が胸につかえる様」【沖辞】。・ちゃーんかでぃかでぃ 茶も食べ食べ(する時には飲んで)。
<ちゃー(茶)+ん(も) +かでぃかでぃ (かぬん 食べる 同じ言葉を繰り返して強調する畳語)・まーさあじ 美味しい味。<まーさん。+あじ。味。
三 寒くなりばんうびんぢゃち 暑くなりばんうびんぢゃち クーフチ芋の熱コーコーから クラガー 百号 イナヨー芋から 面影立ちゅさあの時分
ふぃーくなりばん 'うびんじゃち ’あちくなりばん 'うびんじゃち くーふち'んむぬ'あちこーこーから くらがーひゃくごー 'いなよー'んむから 'うむかじたちゅさ 'あぬじぶん
hwiiku naribaN 'ubiNjachi 'achikunaribaN 'ubiNjachi kuuhuchi 'Nmu nu 'achikookoo kara kuragaa hyakugoo 'inayoo 'Nmu kara 'umukaji tachusa 'anujibuN
〇寒くなっても思い出し 暑くなっても思い出し 粉吹き芋が出来たての熱々で クラガー百号 イナヨー芋で 面影がたつよあの時分の
語句・ふぃーく 寒く。<ふぃーさん(形)。・なりばん なった時も。<なり+ばー(時)+ん(も)・うびんじゃち思い出して。<'うび'んじゃしゅん 。思い出す。・くーふち 粉吹き。・あちこーこー「ほやほや。煮えたばかりのさま。また料理の熱いうちに」【沖辞】。料理が出来たてのほかほか熱いさまをこういう。・からで。・くらがーひゃくごー クラガー百号という「甘蔗の一種。上等な品種」【沖辞】。「暗い井戸で見つかった」から「暗井戸(ガー)」。・いなよー不明。これもたぶん芋の種類であろう。。
四 クバ笠かんとて夏の日も 冬の寒さる雨の日も むのーちゅはーら腹一杯かで根気ちきやいうみはまりんでち 親のかまちゃる芋の味
くばがさかんとーてぃなちぬふぃーん ふゆぬふぃーさる'あみぬふぃーん むのー ちゅはーらはら'いっぱいかでぃ くんちちきやい'うみはまんでぃち 'うやぬかまちゃる 'んむぬ'あじ
kubagasa kaNtooti nachi nu hwiiN huyu nu hwiisaru 'ami nu hwiiN munoo chuhaara hara 'ippaikadi kuNchi chikiyai 'umihamaNdichi 'uya nu kamacharu 'Nmu nu 'aji
〇クバ笠をかぶって夏の日も 冬の寒い雨の日も 食べ物をお腹一杯食べて根気をつけて励む(ことができる)と言って親が食べさせてくれる芋の味
語句・くばがさ クバの葉で作った笠。・かんとーてぃ かぶっていて。<かんじゅん 「かぶる」【沖辞】。 ・むのー 食べ物を。<むぬ(食べ物)+や 融合してnoo となる。・ちゅふぁーら 「腹一杯。満腹」「十分」【沖辞】。・くんち 「根気」。元気、というくらいに使われる。・ちきやい つけて。<ちちゅん。付く。・うみはまんでぃち 励む(ことができる)と言って。<うみはまゆん。励む。没頭する。 + んでぃち。と言って。
五 三度三度のはんめーや 芋と塩小し腹みちて 命つぃなぢゃるあの志情や 忘てーならんさ親の恩儀 いちぐいちまで忘んなよ
さんどぅさんどぅぬはんめーや 'んむとぅまーすぐわーしわたみちてぃ 'いぬちちなじゃる'あぬしなさきや わしてーならんさ'うやぬ うんじぇー 'いちぐ'いちまでぃわしんなよー
saNdusaNdu nu haNmee ya 'Nmu tu maasugwaashi wata michiti 'inuchi chinajaru 'anu shinasaki ya washitee naraN sa 'uya nu uNjee 'ichigu'ichimadi washiNna yoo
〇三度、三度の食料は芋と塩でお腹を満たして、命(いつもの元気)を繋いでいるあの志情けは 忘れてはならないよ 親の恩義は一生何時までも忘れるなよ
語句・はんめー糧食。食料。・し で。・うんじぇー 恩義は。<うんじぇー<うんじ。恩義+や。は。融合して、うんじぇー。
(コメント)
沖縄で人気がある新民謡のひとつ。
一昔前の沖縄の普通の家庭の食事を支えていた芋(んむ)。
曲は、テンポがよくエイサー曲にも使われている。
お母さんが朝早くから芋を煮て子ども達に食べさせる。
笑いがこぼれる食卓、できたてをフーフーしながら喉に詰まらせる子どもたちに
お茶を飲み飲み食べないなさいと。
そして子ども達も大きくなり、振り返る。寒くて暑くても思い出す、あのいろいろな芋の味。
クバ笠をかぶった夏も寒い冬もお腹を一杯にして根気をつければ頑張れる、と親がいつも
いって聞かせてたべさせてくれた、あの味。
まずしかったけれど、芋と塩だけで元気、命を繋いでくれた親の情け、恩義は絶対に忘れてはいけない。それを受け継いでいくかなくては。
というような意訳。
私のこどものころ(1959年生まれ)でも、芋はよくたべさせられた。
おやつに、ご飯にまぜて。
さすがに子どものころは「もう、いらん〜」といっていたが、
年をとると芋の味は懐かしい。
朝食を食べない、食べさせない家庭が増え、すぐに「切れる」子どもが増えた。親も格差社会で、苦しみながら、ついついコンビニの食事に頼る親の責任も重いが、社会の構造にも問題がある。
しっかり朝ご飯を食べる、手作りのものを食べる、親が昔からの食事を見直し子どもに伝える。
こんなあたりまえのことがおろそかになっている時代になった。
昔の人のバトンをどこかに落としてしまったのだ。
次の世代、私たちは何のバトンを渡そうか。
【芋の琉球、本土への伝搬】
野国総管
琉球に芋(現在の甘蔗、唐芋、サツマイモ)が伝わったのは1605年。現在の嘉手納にあたる野国村(ぬぐん)生まれの野国総管(総管とは進貢船の役職名。本名は「与那覇松」だと言われている。)が明(中国)の福州から持ち帰った甘蔗の苗を植えたことに始まる。
台風などによる天災により旱魃や飢饉をなんとかしたいという思いであったという。
儀間真常
野国総管が持ち帰り栽培した芋を儀間村生まれの儀間真常が琉球各地に広めた。これが種子島(1698年)、薩摩(1705年)に伝わる。
薩摩では「唐芋(カライモ)」と呼ばれた。
江戸には青木昆陽によって伝わった(1734年)。栽培方法が確立し全国へ広まった。江戸で「薩摩芋」と呼ばれた。
宮古島には別のルートで甘蔗が伝わった(1597年)。
このように芋(甘蔗、サツマイモ)は中国から琉球を経て薩摩や本土に広がっていったのである。

(嘉手納町にある野国総管を祀る神社)

(同上)

(説明板)
2016年10月28日に筆者撮影。
【「あかとぅんち」を巡って】
一番の歌詞に出てくる「あかとぅんち」。なんとなく意味はわかるようで、わからない。
なんとなく「あかつき」にも似てるから、そうなんだろうと歌っている方も多い。
沖縄語辞典(国立国語研究所編)、琉球語辞典(半田一郎)にも「あかとぅんち」の項はない。
SNSのfacebookに「うちなーぐち講座」というグループがあり、そこで伺ってみた。
沖縄で現在「あかとぅんち」を使っているかどうか、と。すると、「聞いたことがない」という返事を頂いた。また、この作詞をされた浦崎芳子さんは伊江島だから「伊江島ムニー」(伊江島の言葉)かもしれないというご示唆も受けた。
それで今帰仁方言音声データベースで検索すると、「あかとぅんち」ではなく
ハートゥンチ (名詞)暁。夜明け。明け方。
という言葉が出てきた。
さらに「ハー」を検索すると
ハー (名詞)赤。haa<aka あかーともいう。
と出てきた。
実際に伊江島ご出身の方に、上述の「うちなーぐち講座」の方が伺ってくださったところによると
アハトゥンチという。暁、夜明け、朝陽に使う。
つまり、暁の意味で、伊江島ではアハトゥンチ、今帰仁ではハートゥンチということがわかった。
つまりこの歌の作者浦崎芳子さんは、自分のシマ(故郷)の言葉で「あかとぅんち」という語句を選択されたのだ。
ところで「とぅんち」とはなにか。
普通は「殿内」と書く「大きなお屋敷」と思う。
しかし、それでは「あかどぅんち」というように連濁のために「どぅ」となるだろう。例えば「ぬんどぅんち」(ヌールーぬ屋敷) などのように。
暁(あかつき)を語源辞典でみると
あか、とき。だという。奈良時代はそうであり、その後、あかつき、になったとある。
すると琉球では、
あかとき、が、あかとぅき、に変化し、あかとぅんち、になったと考えるのも不自然ではない。
沖縄古語辞典の「あかつき」の項に
「アカツィチ 明け方。夜明け。『あかつき』の古形は「あかとき」(明時)で、沖縄北部方言にはアカトゥンチがある」
とある。
奈良時代は「あかとき」、平安時代以降は「あかつき」に変化していく前の「あかとき」が北部には残っていて「あかとぅんち」になったということだ。
私たちはこの「芋の時代」を歌うたびに、奈良時代の「あかとき」の痕跡を残す「あかとぅんち」という言葉を歌っていることになる。
この記事へのコメント
はじめまして。
ti-daブログトップからきました。
とても 分かりやすくて、ためになりますっ!!
三線を始めたばかりなのですが、
歌詞の意味がわからないものが多く、
技術を練習しているだけで、心までは意識が向きませんでした。
これじゃぁダメだなぁと思っていたので、
このページを見れてよかったですっ!!
んむぬじだい は、弾くのも歌うのも楽しくて、
よく弾いていますが、こういう歌詞だったんだすね。
おぼろげには分かるのですが、
こういう意味だったとは!
言葉遊びの感覚で歌ってしまってました・・・
単語も詳しく説明があって、すごく分かりやすいです。
これからもアップされるのを楽しみにしていますっ!
ti-daブログトップからきました。
とても 分かりやすくて、ためになりますっ!!
三線を始めたばかりなのですが、
歌詞の意味がわからないものが多く、
技術を練習しているだけで、心までは意識が向きませんでした。
これじゃぁダメだなぁと思っていたので、
このページを見れてよかったですっ!!
んむぬじだい は、弾くのも歌うのも楽しくて、
よく弾いていますが、こういう歌詞だったんだすね。
おぼろげには分かるのですが、
こういう意味だったとは!
言葉遊びの感覚で歌ってしまってました・・・
単語も詳しく説明があって、すごく分かりやすいです。
これからもアップされるのを楽しみにしていますっ!
Posted by おけい at 2007年01月30日 13:00
おけいさん
はじめまして。
そういってもらえると励みになります。
こういう方法をされて研究されてきた胤森さんに学んで
やっているだけなのです。
今後もコツコツやっていきますので、よろしく。
はじめまして。
そういってもらえると励みになります。
こういう方法をされて研究されてきた胤森さんに学んで
やっているだけなのです。
今後もコツコツやっていきますので、よろしく。
Posted by たるー at 2007年01月30日 22:45
たるーさんご無沙汰してます(・ω・)ノ
9/10民謡協会関西支部の記念公演で芋の時代歌います(・ω・)ノ紹介文の参考にさせてください。
確かに今帰仁ではk→hがになるところありますね。草(ふさ)みたいに。
9/10民謡協会関西支部の記念公演で芋の時代歌います(・ω・)ノ紹介文の参考にさせてください。
確かに今帰仁ではk→hがになるところありますね。草(ふさ)みたいに。
Posted by ふーちゃん at 2017年08月16日 13:36
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。