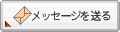2025年01月11日
美童花染小
美童花染小
みやらびはなずみぐゎー
miyarabi hanazumi gwaa
語句・みやらび結婚する前の娘のこと。・はなずみ 野草の花などで染めたもの。浅地(浅い紺色)から繰り返し染めることによる紺地まで。
作詞 上原直彦 作曲 知名定男
歌 玉城一美
一、ーち手さーじ 二ち誰にくぃゆが 三ち 美童ぬ 真肝色深く染みて またあむぬ 思てぃ 呉りようや かなさしよ
てぃーちてぃーさーじ たーちたーにくぃゆが みーちみやらびぬまぢむいるふかくすみてぃ またあむぬ うむてぃくぃりよーやー かなさしよー
tiichi tiisaaji taachi taa ni kwiyuga miichi miyarabi nu majimu 'iruhukaku sumiti mata 'amunu 'umuti kwiri yoo yaa kanasashi yoo
◯一つ 手拭 二つ誰にあげるのか 三つ娘の真心を色深く染めて また染めるから愛してくださいよね 愛しい人よ
語句・てぃーさーじ手拭(てぬぐい)。女性が手織りした手拭は、汗を拭ったりする実用的なものから、男性に渡して愛を伝える、結婚の意思を表すものまである。・またあむぬ「またあるのだから」「またあるのに」と訳せる。前の語句「深く染めて」に係るとすれば「また染める」という意味を含むと考えられる。・うむてぃ思って。愛して。島唄の場合「愛して」と解釈するほうが普通。
二、四ち 嫁ならわ 五ち イービナギ 六ち睦ましく 楽ぬ玉水ん二人し また飲まや 思てぃ 呉りようや かなさしよ
ゆーち ゆみならわ いちち いーびなぎ むーち むちましく らくぬたまみじんたいし またぬまやー うむてぃくぃりよーやー かなさしよー
yuuchi yuminarawa 'ichichi 'iibinagi muuchi muchimajiku raku nu tamamijiN taishi mata numa yaa 'umutikwiri yoo yaa kanasashi yoo
◯四つ 嫁になれば 五つ指輪して 六つ睦まじく 楽しく清らかな水をも二人で繰り返し飲もうね 愛してくださいよね 愛しい人よ
語句・いーびなぎ指輪。指は「いーび」。「なぎ」は、もともと「いーびがにー」と言っていたものの「がにー」(ganii)の「g」と「n」が入れ替わり「なぎー」になったとする説がある。他にも「みーんま」(巳午)が「みまん」となる例もある。・らくぬたまみじ楽しく清らかな水。
三、七ち情花 八ち約束ど 九ち紺染に 十や十かながき かきてまた給り 思てぃ 呉りようや かなさしよ 思てぃ 呉りようや かなさしよ
ななちなさきばな やーち やくすくどー くくぬち くんずみに とぅーや とぅーかながき かきてぃまたたぼり うむてぃくぃりよーやーかなさしよー うむてぃくぃりよーやーかなさしよー
nanachi nasakibana yaachi yakusuku doo kukunuchi kuNzumi ni tuu ya tuu kanagaki kakiti mata tabori 'umuti kwiri yoo yaa kanasashi yoo 'umuti kwiri yoo yaa kanasashi yoo
◯七つ 愛の花(を咲かせること)八つ約束だよ 九つ紺染(本気の愛)に(なるように) 十は10回も縢掛けを繰り返し掛けてくださいね 愛してくださいよね 愛しい人よ
語句・なさきばな情けの花、と直訳できるが島唄、琉歌の世界で「情け」は「愛」が普通。・くんずみ紺染め。比喩として「浅地」「浅染み」は愛情の浅い「好き」くらいの気持ちや「浮気」の比喩まである。「紺染」「紺地」は「本気」「結ばれる愛」という比喩になる。・かながき 「かな」は縢とか綛と書くことができる機織の道具や糸の巻いたものを意味する。色を染める時に使い、また機織りに使う。琉歌によく登場する「かな」は愛情の表現にも使われ「かながき」は繰り返し染めること→愛情を深くすることの比喩である。
解説

曲目は「指 数へ歌」とある。
「いーび かぞえうた」と読むのだろう。
演奏がリンケンバンドとあるのが珍しい。
1979年頃発売されたレコードだ。
上原直彦さんは琉歌にも造詣が深いことがよくわかる。若い娘さんのフレッシュな恋心を琉歌にも散りばめられたウチナーグチで見事に数え歌に収めている。
LINEのオープンチャットというところでこの曲について質問があった。「またあむぬ」と「十かながき」のところがわからないと。
「また〜」という言い回し、よく沖縄の方は文章の中で使われる。
「さようなら」という時も「またやー」「またやーさい」。安里屋ゆんたでも「またはーりぬ」という繰り返しでてくる囃子言葉がある。琉歌でも「繰り返ちまたん」(繰り返してまたも)というような言い回しがよく使われる。
機織りや染色などの仕事は繰り返し同じような作業の積み重ねであり、それが人生においても毎日繰り返される喜怒哀楽の様子と重ね合わせて比喩に使われることが多い。
この辺りからこのウタを見直すと上原直彦さんが、何を言わんとしていたのか、より深く見えてくるものがある。
「かきてぃまたたぼり」、また文中に「また」が出てくる。その繰り返し感が若い娘がただ恋焦がれているのではなく「愛を深いものにしてくださいね」という強い幸せ願望が滲みでている。
沖縄の女性らしさ、というものがよく表現されているように思う。
みやらびはなずみぐゎー
miyarabi hanazumi gwaa
語句・みやらび結婚する前の娘のこと。・はなずみ 野草の花などで染めたもの。浅地(浅い紺色)から繰り返し染めることによる紺地まで。
作詞 上原直彦 作曲 知名定男
歌 玉城一美
一、ーち手さーじ 二ち誰にくぃゆが 三ち 美童ぬ 真肝色深く染みて またあむぬ 思てぃ 呉りようや かなさしよ
てぃーちてぃーさーじ たーちたーにくぃゆが みーちみやらびぬまぢむいるふかくすみてぃ またあむぬ うむてぃくぃりよーやー かなさしよー
tiichi tiisaaji taachi taa ni kwiyuga miichi miyarabi nu majimu 'iruhukaku sumiti mata 'amunu 'umuti kwiri yoo yaa kanasashi yoo
◯一つ 手拭 二つ誰にあげるのか 三つ娘の真心を色深く染めて また染めるから愛してくださいよね 愛しい人よ
語句・てぃーさーじ手拭(てぬぐい)。女性が手織りした手拭は、汗を拭ったりする実用的なものから、男性に渡して愛を伝える、結婚の意思を表すものまである。・またあむぬ「またあるのだから」「またあるのに」と訳せる。前の語句「深く染めて」に係るとすれば「また染める」という意味を含むと考えられる。・うむてぃ思って。愛して。島唄の場合「愛して」と解釈するほうが普通。
二、四ち 嫁ならわ 五ち イービナギ 六ち睦ましく 楽ぬ玉水ん二人し また飲まや 思てぃ 呉りようや かなさしよ
ゆーち ゆみならわ いちち いーびなぎ むーち むちましく らくぬたまみじんたいし またぬまやー うむてぃくぃりよーやー かなさしよー
yuuchi yuminarawa 'ichichi 'iibinagi muuchi muchimajiku raku nu tamamijiN taishi mata numa yaa 'umutikwiri yoo yaa kanasashi yoo
◯四つ 嫁になれば 五つ指輪して 六つ睦まじく 楽しく清らかな水をも二人で繰り返し飲もうね 愛してくださいよね 愛しい人よ
語句・いーびなぎ指輪。指は「いーび」。「なぎ」は、もともと「いーびがにー」と言っていたものの「がにー」(ganii)の「g」と「n」が入れ替わり「なぎー」になったとする説がある。他にも「みーんま」(巳午)が「みまん」となる例もある。・らくぬたまみじ楽しく清らかな水。
三、七ち情花 八ち約束ど 九ち紺染に 十や十かながき かきてまた給り 思てぃ 呉りようや かなさしよ 思てぃ 呉りようや かなさしよ
ななちなさきばな やーち やくすくどー くくぬち くんずみに とぅーや とぅーかながき かきてぃまたたぼり うむてぃくぃりよーやーかなさしよー うむてぃくぃりよーやーかなさしよー
nanachi nasakibana yaachi yakusuku doo kukunuchi kuNzumi ni tuu ya tuu kanagaki kakiti mata tabori 'umuti kwiri yoo yaa kanasashi yoo 'umuti kwiri yoo yaa kanasashi yoo
◯七つ 愛の花(を咲かせること)八つ約束だよ 九つ紺染(本気の愛)に(なるように) 十は10回も縢掛けを繰り返し掛けてくださいね 愛してくださいよね 愛しい人よ
語句・なさきばな情けの花、と直訳できるが島唄、琉歌の世界で「情け」は「愛」が普通。・くんずみ紺染め。比喩として「浅地」「浅染み」は愛情の浅い「好き」くらいの気持ちや「浮気」の比喩まである。「紺染」「紺地」は「本気」「結ばれる愛」という比喩になる。・かながき 「かな」は縢とか綛と書くことができる機織の道具や糸の巻いたものを意味する。色を染める時に使い、また機織りに使う。琉歌によく登場する「かな」は愛情の表現にも使われ「かながき」は繰り返し染めること→愛情を深くすることの比喩である。
解説

曲目は「指 数へ歌」とある。
「いーび かぞえうた」と読むのだろう。
演奏がリンケンバンドとあるのが珍しい。
1979年頃発売されたレコードだ。
上原直彦さんは琉歌にも造詣が深いことがよくわかる。若い娘さんのフレッシュな恋心を琉歌にも散りばめられたウチナーグチで見事に数え歌に収めている。
LINEのオープンチャットというところでこの曲について質問があった。「またあむぬ」と「十かながき」のところがわからないと。
「また〜」という言い回し、よく沖縄の方は文章の中で使われる。
「さようなら」という時も「またやー」「またやーさい」。安里屋ゆんたでも「またはーりぬ」という繰り返しでてくる囃子言葉がある。琉歌でも「繰り返ちまたん」(繰り返してまたも)というような言い回しがよく使われる。
機織りや染色などの仕事は繰り返し同じような作業の積み重ねであり、それが人生においても毎日繰り返される喜怒哀楽の様子と重ね合わせて比喩に使われることが多い。
この辺りからこのウタを見直すと上原直彦さんが、何を言わんとしていたのか、より深く見えてくるものがある。
「かきてぃまたたぼり」、また文中に「また」が出てくる。その繰り返し感が若い娘がただ恋焦がれているのではなく「愛を深いものにしてくださいね」という強い幸せ願望が滲みでている。
沖縄の女性らしさ、というものがよく表現されているように思う。
この記事へのコメント
続けて欲しい。とても勉強になるし、わかりやすいです!
Posted by やすぽん at 2025年03月07日 04:07