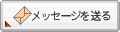2009年04月28日
久場山越路節 (八重山民謡)
久場山越路節
くばやまくいつぃぶしぃ
kubayamakuitsï bushï
語句・くばやまくいつぃ この名前のいわれについては「久場山越地節」に書いた。 「くいつぃ」の発音について。八重山方言では「越える」は「くいるん」(kuiruN)と発音するので「くい」でよい。ウチナーグチ(本島方言)では「くぃーゆん」(kwiiyuN)なので「くぃ」(kwi)となる点は指摘しておきたい。「くい」は二音であるが「くぃ」は一音であるように発音は異なる。また「つぃ」は八重山方言に特有の「中舌母音」をあらわす。「ぶしぃ」も同様。
一、黒島にうるけや さふ島にうるけや (はりぬつぃんだらやう かぬしゃまやう)
くるしぃまに 'うるけや さふしぃまに 'うるけや はりぬつぃんだらよーかぬしゃまよー
kurushïma ni 'uruke ya sahushïma ni 'uru ke ya harinu tsïNdarayoo kanuchama yoo
○黒島に居た間は さふ島(黒島の別称)に居た間は ([はり](囃子言葉) 愛しいよう[かわいそうだよう]愛しい人よ)
[以下囃子言葉略]
語句・うる 居る。<'うん 居る。「うるけや」については、活用等不明だが、石垣方言で接続助詞に「んけん」があり、「・・まで」「間の時」「・・したところ」(「石垣方言辞典」より。以下【石辞】と略す)という意味がある。うる+んけん が融合して「うるけ」になったのかもしれない。【石辞】に「サフジゥマ 二 ウリゥ ケンヤ」「(黒島に居った時は)」という記載があり、普通「けーや」と歌われるが「けんや」という表記もされる場合がある。・さふしぃま 黒島の別称。「さふしま、ぷしま、ぷすま、ふしま」という別称がある。「星の形をした」ということからきているという説もある。 ・ふん 「「国(くに)」の訛語。①国②村」【石辞】 ・はりぬつぃんだらよーかぬしゃまよー 「はり」については囃子言葉である以上の訳は避けるが、こちらに意見を書いている。「つぃんだら」は 「つぃんだーさーん」(①可愛らしい②かわいそうである)【石辞】に感嘆をあらわす「らー」がついたもの。「かぬしゃま」は「かぬしゃー」(「男性からいう女性の恋人。『愛(かな)しき人』の意。「かぬしゃーま」ともいう」【石辞】。
二、島一つやりうり ふん一つやりうり
しぃまぴてぃじぃやり'うり ふんぴてぃじぃやり'うり
shïma pitiijï yari 'uri huN pitiijï yari 'uri
○故郷は一つであった 村はひとつであった
語句・やり 「やり」については「やん」(・・である)の活用。「居る」をあらわす「うり」とともに「・・であった」と訳せる。解説書には「島で永久にいると思っていたのに」という訳が多い。
三、ぶなびしん我二人 ゆいふなぐん我二人
ぶなびしん ばふたりぃ ゆいふなぐん ばふたりぃ
bunabi shiN ba hutarï yui hunaguN ba hutarï
○苧(カラムシ)の農作業をするときも私たち二人 ゆい(共同作業)をする時も二人
語句・ぶなび 苧(カラムシ)の収穫。 <ぶー「苧(お)。カラムシ。八重山上布の原料となる。真苧(まお)。ラミー。」【石辞】。イラクサ目イラクサ科の多年生植物。 + なび 作業。 「ゆなび」(夜業)という言葉がある。 カラムシを収穫し、繊維を取り、紡ぎ、織る。この一連の作業のうち、繊維を取る以後の作業は女性の作業とされていたから、最初の「収穫」だけを意味しているのではないだろうか。・しん するのも。 <しぃん する。 +ん も。 ・ば 私たち。<ばー 。 ・ゆい 「共同作業に互いに労力を提供しあうこと。継続的な結びつきである。「ゆいまーりぃ」は 『ゆい』を順番に行うこと」【石辞】。「ふなぐ」いついては辞書でみあたらない。今後の課題。
四、山行きん我二人 いす下れん 我二人
やま'いきん ばふたりぃ 'いす'うれん ばふたりぃ
yama 'ikiN ba hutarï 'isu 'ureN ba hutarï
○山に行くのも私たち二人 磯下りても私たち二人
くばやまくいつぃぶしぃ
kubayamakuitsï bushï
語句・くばやまくいつぃ この名前のいわれについては「久場山越地節」に書いた。 「くいつぃ」の発音について。八重山方言では「越える」は「くいるん」(kuiruN)と発音するので「くい」でよい。ウチナーグチ(本島方言)では「くぃーゆん」(kwiiyuN)なので「くぃ」(kwi)となる点は指摘しておきたい。「くい」は二音であるが「くぃ」は一音であるように発音は異なる。また「つぃ」は八重山方言に特有の「中舌母音」をあらわす。「ぶしぃ」も同様。
一、黒島にうるけや さふ島にうるけや (はりぬつぃんだらやう かぬしゃまやう)
くるしぃまに 'うるけや さふしぃまに 'うるけや はりぬつぃんだらよーかぬしゃまよー
kurushïma ni 'uruke ya sahushïma ni 'uru ke ya harinu tsïNdarayoo kanuchama yoo
○黒島に居た間は さふ島(黒島の別称)に居た間は ([はり](囃子言葉) 愛しいよう[かわいそうだよう]愛しい人よ)
[以下囃子言葉略]
語句・うる 居る。<'うん 居る。「うるけや」については、活用等不明だが、石垣方言で接続助詞に「んけん」があり、「・・まで」「間の時」「・・したところ」(「石垣方言辞典」より。以下【石辞】と略す)という意味がある。うる+んけん が融合して「うるけ」になったのかもしれない。【石辞】に「サフジゥマ 二 ウリゥ ケンヤ」「(黒島に居った時は)」という記載があり、普通「けーや」と歌われるが「けんや」という表記もされる場合がある。・さふしぃま 黒島の別称。「さふしま、ぷしま、ぷすま、ふしま」という別称がある。「星の形をした」ということからきているという説もある。 ・ふん 「「国(くに)」の訛語。①国②村」【石辞】 ・はりぬつぃんだらよーかぬしゃまよー 「はり」については囃子言葉である以上の訳は避けるが、こちらに意見を書いている。「つぃんだら」は 「つぃんだーさーん」(①可愛らしい②かわいそうである)【石辞】に感嘆をあらわす「らー」がついたもの。「かぬしゃま」は「かぬしゃー」(「男性からいう女性の恋人。『愛(かな)しき人』の意。「かぬしゃーま」ともいう」【石辞】。
二、島一つやりうり ふん一つやりうり
しぃまぴてぃじぃやり'うり ふんぴてぃじぃやり'うり
shïma pitiijï yari 'uri huN pitiijï yari 'uri
○故郷は一つであった 村はひとつであった
語句・やり 「やり」については「やん」(・・である)の活用。「居る」をあらわす「うり」とともに「・・であった」と訳せる。解説書には「島で永久にいると思っていたのに」という訳が多い。
三、ぶなびしん我二人 ゆいふなぐん我二人
ぶなびしん ばふたりぃ ゆいふなぐん ばふたりぃ
bunabi shiN ba hutarï yui hunaguN ba hutarï
○苧(カラムシ)の農作業をするときも私たち二人 ゆい(共同作業)をする時も二人
語句・ぶなび 苧(カラムシ)の収穫。 <ぶー「苧(お)。カラムシ。八重山上布の原料となる。真苧(まお)。ラミー。」【石辞】。イラクサ目イラクサ科の多年生植物。 + なび 作業。 「ゆなび」(夜業)という言葉がある。 カラムシを収穫し、繊維を取り、紡ぎ、織る。この一連の作業のうち、繊維を取る以後の作業は女性の作業とされていたから、最初の「収穫」だけを意味しているのではないだろうか。・しん するのも。 <しぃん する。 +ん も。 ・ば 私たち。<ばー 。 ・ゆい 「共同作業に互いに労力を提供しあうこと。継続的な結びつきである。「ゆいまーりぃ」は 『ゆい』を順番に行うこと」【石辞】。「ふなぐ」いついては辞書でみあたらない。今後の課題。
四、山行きん我二人 いす下れん 我二人
やま'いきん ばふたりぃ 'いす'うれん ばふたりぃ
yama 'ikiN ba hutarï 'isu 'ureN ba hutarï
○山に行くのも私たち二人 磯下りても私たち二人
本島の「桃売い姉小」から「久場山越地節」をめぐり、そして元歌の「久場山越路節」にやっとたどりついた。
八重山民謡で、この歌詞は「つぃんだら節」の「ちらし」(続けて2曲歌うあとの唄、または歌うこと)である。
作は「1836年『大浜英普』が野底与人訳を拝命されたときに、その内容を謡われたと言い伝えられている」(「八重山民謡誌」喜舎場永珣著)。
しかし、ここで紹介した歌詞は、大浜英普(1775-1843)が作詞したものとは異なり、「つぃんだら節」の歌詞を引続き使ったものである。
琉歌の形式ではなく、本句が9 9 囃子が8 5という作り。
沖縄音階(ドミファソシド)を多めに含むメロディーなのだが、暗いイメージがある。舞踊「貫花」の「武富節」(だきどぅんぶし)、つまりその元歌の「真栄節」(まざかいぶしぃ)とメロディーがよく似ている。
さて、上で直訳をしてみたが、すこし雰囲気をつけて意訳もしてみよう。
一、黒島に居た間は、さふ島にいた間は
二、故郷は一つだと思っていたのに、村はひとつだと思っていたのに
三、上布の繊維を取るカラムシの農作業でも私たち二人だったのに 共同作業をするときも一緒だったのに
四、山にいく時も一緒だったのに 海に行くときも一緒だったのに
首里王朝の命令でなされた「島分け」、強制移住政策で黒島から、彼と別れさせられて石垣島の野底に来させられた主人公の「うらみ節」だといっても過言ではない。
しかし、上に書いたように大浜英普が作詞したものは、まったく別の歌詞があって、(紹介は次回に回すが)それはほのぼのとした久場山峠にできた「越路道」の賛歌である。
つまり、古い歌詞は「捨てられて」「つぃんだら節」に合うように歌詞が書きかえられたもの。
それだけ、「つぃんだら節~久場山越路節」にこめた島人の想いは強かったのだろう。
八重山民謡で、この歌詞は「つぃんだら節」の「ちらし」(続けて2曲歌うあとの唄、または歌うこと)である。
作は「1836年『大浜英普』が野底与人訳を拝命されたときに、その内容を謡われたと言い伝えられている」(「八重山民謡誌」喜舎場永珣著)。
しかし、ここで紹介した歌詞は、大浜英普(1775-1843)が作詞したものとは異なり、「つぃんだら節」の歌詞を引続き使ったものである。
琉歌の形式ではなく、本句が9 9 囃子が8 5という作り。
沖縄音階(ドミファソシド)を多めに含むメロディーなのだが、暗いイメージがある。舞踊「貫花」の「武富節」(だきどぅんぶし)、つまりその元歌の「真栄節」(まざかいぶしぃ)とメロディーがよく似ている。
さて、上で直訳をしてみたが、すこし雰囲気をつけて意訳もしてみよう。
一、黒島に居た間は、さふ島にいた間は
二、故郷は一つだと思っていたのに、村はひとつだと思っていたのに
三、上布の繊維を取るカラムシの農作業でも私たち二人だったのに 共同作業をするときも一緒だったのに
四、山にいく時も一緒だったのに 海に行くときも一緒だったのに
首里王朝の命令でなされた「島分け」、強制移住政策で黒島から、彼と別れさせられて石垣島の野底に来させられた主人公の「うらみ節」だといっても過言ではない。
しかし、上に書いたように大浜英普が作詞したものは、まったく別の歌詞があって、(紹介は次回に回すが)それはほのぼのとした久場山峠にできた「越路道」の賛歌である。
つまり、古い歌詞は「捨てられて」「つぃんだら節」に合うように歌詞が書きかえられたもの。
それだけ、「つぃんだら節~久場山越路節」にこめた島人の想いは強かったのだろう。
Posted by たる一 at 13:27│Comments(9)
│か行
この記事へのコメント
石垣で、「つぃんだら節」と「久場山越路節」を教わり、野底マーペーに登って唄いました、マーペーの雰囲気に圧倒され、そして、まだまだ私には、この曲の引き裂かれた悲しみや、人を愛おしむという気持ちが唄いきれないなぁって思って帰ってきました。唄はやっぱり奥が深いですね、「つぃんだら節」と合わせて好きな曲です。
Posted by ナオ at 2009年04月28日 15:22
ナオさん
いつもコメントありがとう!
まだ野底に登ったことはありませんが、
近くを走り、先の灯台で歌わせてもらいました。
同感です。
いつもコメントありがとう!
まだ野底に登ったことはありませんが、
近くを走り、先の灯台で歌わせてもらいました。
同感です。
Posted by たるー(せきひろし) at 2009年04月30日 08:15
at 2009年04月30日 08:15
 at 2009年04月30日 08:15
at 2009年04月30日 08:15池上永一さんが書かれた「風車祭」にでてくる「つぃんだら節」の歌詞がようやくつながりました!!色々と調べても、あの歌詞にたどり着かなくて、『チラシ』として「久場山越つぃ節」の歌詞が使われているのですね。でも、本の中では「つぃんだら節」の途中に中途半端にはさまってました
なぜ、このように書かれたのかが、新たな疑問です??
なぜ、このように書かれたのかが、新たな疑問です??
Posted by サミー山田先生 at 2010年01月07日 22:34
at 2010年01月07日 22:34
 at 2010年01月07日 22:34
at 2010年01月07日 22:34サミー山田先生。
私はまだその本を手にしていないのでなんともいえないのですが
昔の「つんだら節」の歌詞は現在の「久場山・・」の歌詞であったと
ものの本にあります。
その関係かも?
興味がありますのでそのうち調べてみます。
私はまだその本を手にしていないのでなんともいえないのですが
昔の「つんだら節」の歌詞は現在の「久場山・・」の歌詞であったと
ものの本にあります。
その関係かも?
興味がありますのでそのうち調べてみます。
Posted by たる- at 2010年01月14日 16:29
at 2010年01月14日 16:29
 at 2010年01月14日 16:29
at 2010年01月14日 16:29久場山越地節本歌
〇久場山越地ぬねぬらば
山道ぬねぬらば
〇越地道んありばとみしゃる
山道んありばとみしゃる
〇なゆしきぬ越地道
いかしきぬ山道
〇ふんだしぬ越地道
ちぃい通ふしぬ山道
〇越地道ぬ長ぬまま
山道ぬ幅ぬまま
〇糸はゆてちかいす
布はゆておはらす
〇たるたるどちかいす
じりじりどおはらす
〇野底主どちかいす
目差主どちかいす
1966年発行安室孫師版安室流工工四より転載
〇久場山越地ぬねぬらば
山道ぬねぬらば
〇越地道んありばとみしゃる
山道んありばとみしゃる
〇なゆしきぬ越地道
いかしきぬ山道
〇ふんだしぬ越地道
ちぃい通ふしぬ山道
〇越地道ぬ長ぬまま
山道ぬ幅ぬまま
〇糸はゆてちかいす
布はゆておはらす
〇たるたるどちかいす
じりじりどおはらす
〇野底主どちかいす
目差主どちかいす
1966年発行安室孫師版安室流工工四より転載
Posted by くがなー at 2011年03月07日 03:04
くがなーさん
久場山越地節本歌ありがとうございます。
手元にある歌詞とあわせてまた検討してみますね。
ありがとうございました!
久場山越地節本歌ありがとうございます。
手元にある歌詞とあわせてまた検討してみますね。
ありがとうございました!
Posted by たる一 at 2011年03月23日 10:59
at 2011年03月23日 10:59
 at 2011年03月23日 10:59
at 2011年03月23日 10:59ちなみにこの久場山越地の歌詞は黒島で唄われていた歌詞です、黒島には中舌母音が無く、更に5番として。
ふんばがりで うふぁられ
島ばがりで うふぁられ
と続き、昔はまだまだ沢山歌詞があったそうです。
ふんばがりで うふぁられ
島ばがりで うふぁられ
と続き、昔はまだまだ沢山歌詞があったそうです。
Posted by くがなー at 2011年07月10日 15:13
大変重要な単語訳をお伝えするのを忘れていました。「さふ島」とは「サク(石偏に乍)と書く文字、意味は“いしくれ立った”に島」でサク島、これが黒島式脱音によりか行がは行になり「さふ島」となったものです。
黒島の方々は黒島の事を「フルユン」とも言います(語源は滞在していた朝鮮人による朝鮮語の「フリュルン」だそうです)
黒島の方々は黒島の事を「フルユン」とも言います(語源は滞在していた朝鮮人による朝鮮語の「フリュルン」だそうです)
Posted by くがなー at 2011年12月06日 16:00
くがなーさん
度々とコメントありがとうございます。
「さふ島」に関するご示唆、よくわかります。
参考にさせていただいて、また調べてみたいと思います。
朝鮮語との関係もあるのでしょうね。
度々とコメントありがとうございます。
「さふ島」に関するご示唆、よくわかります。
参考にさせていただいて、また調べてみたいと思います。
朝鮮語との関係もあるのでしょうね。
Posted by たる一 at 2011年12月21日 23:59
at 2011年12月21日 23:59
 at 2011年12月21日 23:59
at 2011年12月21日 23:59※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。