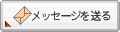2012年12月08日
武富節
武富節(貫花)
だきどぅんぶし(ぬちばな)
dakiduN bushi(nuchibana)
一、でちゃよ押し連れてあたい花むいが 花や露かむてむいやならん(へいやーよーぬひやるがひ)(以下囃し省略)
でぃちゃよ'うしちりてぃ'あたいばなむいが はなやちゆかみてぃ むいやならん
dicha yo 'ushichiriti 'ataibana muiga hana ya chiyu kamiti muiyanaraN
〇さあ 連れだって畑の花をもぎ取りに 花は露を乗せてもぎ取ることはできない
二、白瀬走川に流れゆる桜すくて思里に貫ちゃいはきら
しらしはいかわにながりゆるさくらすくてぃ'うみさとぅにぬちゃいはきら
shirashi haikawa ni nagariyuru sakura sukuthi 'umisatu ni nuchai hakira
〇白瀬走川に流れている桜をすくって愛しい貴方に(桜を)糸で通したりして首にかけよう
三、赤糸貫花や里に打ちはきて白糸貫花やゆいり童
'あかちゅぬちばなやさとぅに'うちはきてぃ しらちゅぬちばなやゆいりわらび
'akachu nuchibana ya satu ni 'uchihakiti siruchu nuchibana ya yuiri warabi
〇赤い糸の貫花は貴方に首にかけ 白糸の貫花はもらえ 子ども
解説
(語句)
一
・'あたい 畑 菜園
・むいが もぐために
<むゆん + i+ga ~しに(cf.「べーべーぬくさかいが」)
・かみてぃ <かみゆん のせる
二
・かわ kawa
白瀬走川 しらせはいかわ 久米島具志川村にある川の名前。
・はきゆん 首にかける
三
・ゆいり もらえ
<ゆいり<yiiri<iiyuN
(コメント)
白瀬走川は久米島具志川間切にある川。流れが速いのでこの名前がある。
古典の呼び名で「白瀬走川節」
舞踊では「貫花」
古典女踊りでは雑踊りと区別して「本貫花」(むとぅぬちばな)
武富節と呼ばれるのは本歌が「真栄節」(まざかいぶし)であるから。
歌詞を紹介しよう。
生りや竹富育や仲間ぬまざかい エイヨウヌヒヤルガヨウ
(まりやたきどん すだつやなかまぬまざかい)
なゆぬうゆんいきゃぬつぃにゃんど仲間くひだ
(なゆぬゆんいきゃぬつぃにゃんどなかまくひ《い?》だ)
大浦田ぬみなぐつぃぬゆやんどう
(うはらだぬみなぐつぃぬやんどー)
餅米ぬ白米ぬやんどう
(むちぐみぬしるぐみぬゆやんどー)
この最初の「竹富」(ダキドン)から「武富節」(だきどぅんぶし)と呼ばれるのだろう。
あくまで想像の域であるが、
(本歌)真栄節(八重山民謡)→白瀬走川節(久米島民謡)→武富節(古典)→本貫花・貫花(舞踊曲)
という流れで歌が広がっていったのではないだろうか。
貫花というのは、色々な花を糸で貫いてハワイのレイのようなものを持って踊る。
久米島には桜が今はみられないので、白ツツジや赤ツツジを桜にたとえたという説。昔は桜があったという説がある。
前回の「サーサー節」の3番で「糸をもらえこどもよ、それで露の玉をつないだりして遊ぼう」という歌詞と、この3番が関連しているように思える。
ところで、「ゆいり」には2説ある。
胤森さんによると
「琉歌大成」では「捨てろ」
「沖縄古語辞典」では「もらえよ」となっているが、
「赤糸は喜びの象徴で祝儀に使われ、白は不幸に使われる。」ことから
「捨てろ」が妥当だという。
しかし、私には疑問がのこる。
・なぜ、不幸の色の白糸で貫花をわざわざ作ってから子どもに捨てろというのか?
それから「花笠節」という唄の副題に「白糸節」と一名があり、四番に「白糸
かきやい貫花造とて里前御衣 里と我が仲語らんむんぬん 我がうてちちゅみ」
白糸が不吉ならこの唄は不吉な唄となるが、そうではないのは何故か?
だきどぅんぶし(ぬちばな)
dakiduN bushi(nuchibana)
一、でちゃよ押し連れてあたい花むいが 花や露かむてむいやならん(へいやーよーぬひやるがひ)(以下囃し省略)
でぃちゃよ'うしちりてぃ'あたいばなむいが はなやちゆかみてぃ むいやならん
dicha yo 'ushichiriti 'ataibana muiga hana ya chiyu kamiti muiyanaraN
〇さあ 連れだって畑の花をもぎ取りに 花は露を乗せてもぎ取ることはできない
二、白瀬走川に流れゆる桜すくて思里に貫ちゃいはきら
しらしはいかわにながりゆるさくらすくてぃ'うみさとぅにぬちゃいはきら
shirashi haikawa ni nagariyuru sakura sukuthi 'umisatu ni nuchai hakira
〇白瀬走川に流れている桜をすくって愛しい貴方に(桜を)糸で通したりして首にかけよう
三、赤糸貫花や里に打ちはきて白糸貫花やゆいり童
'あかちゅぬちばなやさとぅに'うちはきてぃ しらちゅぬちばなやゆいりわらび
'akachu nuchibana ya satu ni 'uchihakiti siruchu nuchibana ya yuiri warabi
〇赤い糸の貫花は貴方に首にかけ 白糸の貫花はもらえ 子ども
解説
(語句)
一
・'あたい 畑 菜園
・むいが もぐために
<むゆん + i+ga ~しに(cf.「べーべーぬくさかいが」)
・かみてぃ <かみゆん のせる
二
・かわ kawa
白瀬走川 しらせはいかわ 久米島具志川村にある川の名前。
・はきゆん 首にかける
三
・ゆいり もらえ
<ゆいり<yiiri<iiyuN
(コメント)
白瀬走川は久米島具志川間切にある川。流れが速いのでこの名前がある。
古典の呼び名で「白瀬走川節」
舞踊では「貫花」
古典女踊りでは雑踊りと区別して「本貫花」(むとぅぬちばな)
武富節と呼ばれるのは本歌が「真栄節」(まざかいぶし)であるから。
歌詞を紹介しよう。
生りや竹富育や仲間ぬまざかい エイヨウヌヒヤルガヨウ
(まりやたきどん すだつやなかまぬまざかい)
なゆぬうゆんいきゃぬつぃにゃんど仲間くひだ
(なゆぬゆんいきゃぬつぃにゃんどなかまくひ《い?》だ)
大浦田ぬみなぐつぃぬゆやんどう
(うはらだぬみなぐつぃぬやんどー)
餅米ぬ白米ぬやんどう
(むちぐみぬしるぐみぬゆやんどー)
この最初の「竹富」(ダキドン)から「武富節」(だきどぅんぶし)と呼ばれるのだろう。
あくまで想像の域であるが、
(本歌)真栄節(八重山民謡)→白瀬走川節(久米島民謡)→武富節(古典)→本貫花・貫花(舞踊曲)
という流れで歌が広がっていったのではないだろうか。
貫花というのは、色々な花を糸で貫いてハワイのレイのようなものを持って踊る。
久米島には桜が今はみられないので、白ツツジや赤ツツジを桜にたとえたという説。昔は桜があったという説がある。
前回の「サーサー節」の3番で「糸をもらえこどもよ、それで露の玉をつないだりして遊ぼう」という歌詞と、この3番が関連しているように思える。
ところで、「ゆいり」には2説ある。
胤森さんによると
「琉歌大成」では「捨てろ」
「沖縄古語辞典」では「もらえよ」となっているが、
「赤糸は喜びの象徴で祝儀に使われ、白は不幸に使われる。」ことから
「捨てろ」が妥当だという。
しかし、私には疑問がのこる。
・なぜ、不幸の色の白糸で貫花をわざわざ作ってから子どもに捨てろというのか?
それから「花笠節」という唄の副題に「白糸節」と一名があり、四番に「白糸
かきやい貫花造とて里前御衣 里と我が仲語らんむんぬん 我がうてちちゅみ」
白糸が不吉ならこの唄は不吉な唄となるが、そうではないのは何故か?
Posted by たる一 at 09:25│Comments(4)
│た行
この記事へのコメント
たるーさん
お久しぶりです
「武富節」、八重山民謡では「真栄(まざかい)節」といいます
人頭税として米を収めるため
米作りに竹富島から西表島へ移住した男・真栄のことを歌ったものです。
たるーさんがお持ちの工工四にも載っています
「真栄節」の前の曲「まんのーま節」のチラシとしても多く用います。
お久しぶりです
「武富節」、八重山民謡では「真栄(まざかい)節」といいます
人頭税として米を収めるため
米作りに竹富島から西表島へ移住した男・真栄のことを歌ったものです。
たるーさんがお持ちの工工四にも載っています
「真栄節」の前の曲「まんのーま節」のチラシとしても多く用います。
Posted by コバ at 2006年03月20日 08:58
コバさん、おひさしぶりです。
なるほど!気づきませんでした。
生まれが竹富。それで「竹富」=「武富節」
これも本歌が八重山。
古典の本を調べて、それにも本歌は詳しいのですが、まったく「真栄節」のことが書いてありませんでした。
私も歌の背景の落差については深く感じます。
貫花を作る余裕のある暮らしは、その時代でどのようなものだったか。
勉強が足りませんね。
なるほど!気づきませんでした。
生まれが竹富。それで「竹富」=「武富節」
これも本歌が八重山。
古典の本を調べて、それにも本歌は詳しいのですが、まったく「真栄節」のことが書いてありませんでした。
私も歌の背景の落差については深く感じます。
貫花を作る余裕のある暮らしは、その時代でどのようなものだったか。
勉強が足りませんね。
Posted by せきひろし(たるー) at 2006年03月21日 00:40
コバさんのご指摘を参考に加筆しました。
「移住」とコバさんが控えめに言われている政策は首里王朝が人頭税の効率を上げるために村を別け強制的に新しい村を作ったものです。
マラリア(熱病)のために村ごと全滅したり、家族や恋人の別離の悲しみは歌となって多くの八重山民謡に残されています。
「移住」とコバさんが控えめに言われている政策は首里王朝が人頭税の効率を上げるために村を別け強制的に新しい村を作ったものです。
マラリア(熱病)のために村ごと全滅したり、家族や恋人の別離の悲しみは歌となって多くの八重山民謡に残されています。
Posted by せきひろし(たるー) at 2006年03月26日 14:04
たるーさん、貴重なHPをありがとうございます。いつも唄の意味がわかるのでとてもうれしいです。
赤糸と白糸の考察ですが、赤糸は恋の糸、白糸は叶わない恋の糸と仮定すると、武富節では、「赤い糸で貫花をつくるんだよ、白糸はだめだよ、わらびー」と諭すように歌っているのかなと感じています。
すみません、根拠はありませんが、、笑
花笠節=白糸節となるのは、歌詞の
「白糸かきやい 貫花造とて里前御衣
里と我が仲語らんむんぬん 我がうてちちゅみ」
が、叶わぬ恋をする女性の気持ちを唄った歌詞なので、
白糸節となったのかなーと思いました。
勝手な憶測での予測は危険であるとたるーさんが言われるよう、承知いたしておりますのでご容赦くださいませ。
赤糸と白糸の考察ですが、赤糸は恋の糸、白糸は叶わない恋の糸と仮定すると、武富節では、「赤い糸で貫花をつくるんだよ、白糸はだめだよ、わらびー」と諭すように歌っているのかなと感じています。
すみません、根拠はありませんが、、笑
花笠節=白糸節となるのは、歌詞の
「白糸かきやい 貫花造とて里前御衣
里と我が仲語らんむんぬん 我がうてちちゅみ」
が、叶わぬ恋をする女性の気持ちを唄った歌詞なので、
白糸節となったのかなーと思いました。
勝手な憶測での予測は危険であるとたるーさんが言われるよう、承知いたしておりますのでご容赦くださいませ。
Posted by いぇらぶ at 2018年09月21日 21:14
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。