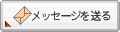2009年04月09日
久場山越地
久場山越地
くばやまくいち
kubayamakuichi
語句・くばやまくいち 八重山民謡「久場山越路節」(大浜英普[1775-1843]作)の曲をもとにしたのでこの名前がある。「久場山越路の峠は、昔の桃里村と野底村の間にあって、曲がりくねって登るので、八重山の峠の中で最も険しい山道といわれている」(「島うた紀行」仲宗根幸市編著より)。いうまでもないが桃里村、野底村は石垣島の村。
作詞 小浜守栄
一、(女)布ぬ袖取やい 我がゆ知りなぎな 如何ならわんとぅ思てぃ捨てぃてぃいめんな よう里前
んすぬすでぃとぅやい わがゆしりなぎな ちゃならわんとぅむてぃしてぃてぃ'いめんな よーさとぅめ
Nsu nu sudi tuyai waga yu shirinagina cha narawaN tumuti shititi 'imeNna yoo satume
○お着物の袖を取ったりする私を知りながら どうにもならないと思って捨ててお行きにならないで ねえ貴方
語句・んす着物。「①着物(ciN)の敬語。お召し物。みそ(御衣)。②ciirukabi(正月などに祭壇と火の神の前に供える黄色の紙)のことをいうときがある」(沖)。「布」という当て字があるが「お着物」ぐらいが適当。 「・なぎな<なぎーな ・・ながら。・いめんな <いめーん 「居る・行く・来るの敬語」(琉)。 否定の命令形。「お行きにならないで」
二、(男)うぬ肝やあらん むしか他所知りてぃ 世間口しばに かからちゃすが よう無蔵よ
'うぬちむや'あらん むしかゆすしりてぃ しきんくちしばにかからちゃすが よーんぞよ
'unu chimu ya 'araN mushika yusu shiriti shikiN kuchishiba ni kakara chasuga yoo Nzo yo
○そんなつもりではない もしも他人が知って世間の噂にでもなればどうする? なあお前
語句・うぬちむやあらん そんなつもりではない。・むしか もしか。もしも。 ・くちしば 噂。「[口唇]噂。~-shiba ni kakajun 世間の噂にのぼる。」(琉)。
三、(女)女身ぬなれぬ義理恥ん捨てぃてぃ焦がりゆる肝や里や知らに よう里前
うぃきがみぬなれぬじりはじんしてぃてぃ くがりゆるちむやさとぅやしらに よーさとぅめ
wikiga mi nu nare nu jirihajiN shititi kugariyuru chimu ya satu ya shirani yoo satume
○女身の習わしである義理や恥も捨てて焦がれる心を貴方は知らないの? ねえ貴方
。なれ <なれー。 習わし。習慣。
四(男)嵐声ぬあてぃん 靡くなよ胸内ぬ契り 他所に知らすなよ よう無蔵よ
'あらしぐぃぬ'あてぃんなびくなよ んにうちぬちじり ゆすにしらすなよ よーんぞよ
'arashigwi nu 'atiN nabikuna yo Nni 'uchi nu chijiri yusuni shirasuna yo yoo Nzo yoo
○悪い知らせがあっても(心)なびくなよ 胸内の契りを他人に知らせるなよ なあお前
語句・あらしぐぃ<あらしぐぃー 'arashigwii 「不幸な知らせ。死んだという知らせなど」しかし、ここでは「不幸な」ではピンとこない。「あらし」には「嵐。おとなの使う語」(沖)ともある。周囲からのいろいろな「声」を「嵐」にたとえているとも考えられる。
五、(男女)二人が真心ん あだになちなゆみ 変わるなよ互に幾世迄ん よう無蔵よ よう 里前
たいがまぐくるん 'あだになちなゆみ かわるなよ たげに'いくゆまでぃん よーんぞよ よーさとぅめ
tai ga magukuruN 'adani nachi nayumi kawaruna yo tage ni 'ikuyu madiN yoo Nzo yoo yoo satume
○二人の真心も無駄にしてはなるまい 変わるなよ互いに幾世までも なあお前 ねえあなた
語句・なちなゆみ <なしゅん ・・にする。・・してしまう。+ なゆん ・・なる。→なゆみ 疑問。なるか?そして「反語」を含んでいるので「なるか?」「ならない」→「なるまい」と訳す。
くばやまくいち
kubayamakuichi
語句・くばやまくいち 八重山民謡「久場山越路節」(大浜英普[1775-1843]作)の曲をもとにしたのでこの名前がある。「久場山越路の峠は、昔の桃里村と野底村の間にあって、曲がりくねって登るので、八重山の峠の中で最も険しい山道といわれている」(「島うた紀行」仲宗根幸市編著より)。いうまでもないが桃里村、野底村は石垣島の村。
作詞 小浜守栄
一、(女)布ぬ袖取やい 我がゆ知りなぎな 如何ならわんとぅ思てぃ捨てぃてぃいめんな よう里前
んすぬすでぃとぅやい わがゆしりなぎな ちゃならわんとぅむてぃしてぃてぃ'いめんな よーさとぅめ
Nsu nu sudi tuyai waga yu shirinagina cha narawaN tumuti shititi 'imeNna yoo satume
○お着物の袖を取ったりする私を知りながら どうにもならないと思って捨ててお行きにならないで ねえ貴方
語句・んす着物。「①着物(ciN)の敬語。お召し物。みそ(御衣)。②ciirukabi(正月などに祭壇と火の神の前に供える黄色の紙)のことをいうときがある」(沖)。「布」という当て字があるが「お着物」ぐらいが適当。 「・なぎな<なぎーな ・・ながら。・いめんな <いめーん 「居る・行く・来るの敬語」(琉)。 否定の命令形。「お行きにならないで」
二、(男)うぬ肝やあらん むしか他所知りてぃ 世間口しばに かからちゃすが よう無蔵よ
'うぬちむや'あらん むしかゆすしりてぃ しきんくちしばにかからちゃすが よーんぞよ
'unu chimu ya 'araN mushika yusu shiriti shikiN kuchishiba ni kakara chasuga yoo Nzo yo
○そんなつもりではない もしも他人が知って世間の噂にでもなればどうする? なあお前
語句・うぬちむやあらん そんなつもりではない。・むしか もしか。もしも。 ・くちしば 噂。「[口唇]噂。~-shiba ni kakajun 世間の噂にのぼる。」(琉)。
三、(女)女身ぬなれぬ義理恥ん捨てぃてぃ焦がりゆる肝や里や知らに よう里前
うぃきがみぬなれぬじりはじんしてぃてぃ くがりゆるちむやさとぅやしらに よーさとぅめ
wikiga mi nu nare nu jirihajiN shititi kugariyuru chimu ya satu ya shirani yoo satume
○女身の習わしである義理や恥も捨てて焦がれる心を貴方は知らないの? ねえ貴方
。なれ <なれー。 習わし。習慣。
四(男)嵐声ぬあてぃん 靡くなよ胸内ぬ契り 他所に知らすなよ よう無蔵よ
'あらしぐぃぬ'あてぃんなびくなよ んにうちぬちじり ゆすにしらすなよ よーんぞよ
'arashigwi nu 'atiN nabikuna yo Nni 'uchi nu chijiri yusuni shirasuna yo yoo Nzo yoo
○悪い知らせがあっても(心)なびくなよ 胸内の契りを他人に知らせるなよ なあお前
語句・あらしぐぃ<あらしぐぃー 'arashigwii 「不幸な知らせ。死んだという知らせなど」しかし、ここでは「不幸な」ではピンとこない。「あらし」には「嵐。おとなの使う語」(沖)ともある。周囲からのいろいろな「声」を「嵐」にたとえているとも考えられる。
五、(男女)二人が真心ん あだになちなゆみ 変わるなよ互に幾世迄ん よう無蔵よ よう 里前
たいがまぐくるん 'あだになちなゆみ かわるなよ たげに'いくゆまでぃん よーんぞよ よーさとぅめ
tai ga magukuruN 'adani nachi nayumi kawaruna yo tage ni 'ikuyu madiN yoo Nzo yoo yoo satume
○二人の真心も無駄にしてはなるまい 変わるなよ互いに幾世までも なあお前 ねえあなた
語句・なちなゆみ <なしゅん ・・にする。・・してしまう。+ なゆん ・・なる。→なゆみ 疑問。なるか?そして「反語」を含んでいるので「なるか?」「ならない」→「なるまい」と訳す。
先日の「桃売い姉小」の流れで、「久場山越地」をとりあげた。
戦後の本島の民謡界のリーダー小浜守栄(こはましゅえい)が作詞。
小浜守英は1919年現在の沖縄市(越来村)生まれ。
嘉手苅林昌とのコンビで各地を回った。
この曲のように、古い民謡に新しい歌詞をのせて作品をよみがえらせる仕事をした。
この歌は「比嘉盛保,城間ひろみ」の音源がてもとにある。
三番の「なびくな」が「かわるな」になっているのと
五番がない。
さて、この歌の元歌は八重山民謡「久場山越路節」。
その曲そのままではないが、本調子を三下げに変え、
多少変化をくわえると、この曲のように
どこか悲しい、暗さもあり、そして情感もたっぷりの曲になる。
元歌は、題名の語句にとりあげているように、険しい久場山越路という峠を歌ったもの。(次回取り上げる)。
それが「つんだら節」のチラシとなって、歌詞には、ひきさかれていく男女の様子がえがかれる。
わたしには「恨み歌」とも聞えるその曲調が、この本島の「久場山越地節」にはいかされている
ように感じる。
小浜守栄は、その情感たっぷりの曲に男女の契りをかわしつつ
世間の「嵐声」にゆられながら互いの愛を守ろうとする二人の対話を歌にした。
これも名曲である。
戦後の本島の民謡界のリーダー小浜守栄(こはましゅえい)が作詞。
小浜守英は1919年現在の沖縄市(越来村)生まれ。
嘉手苅林昌とのコンビで各地を回った。
この曲のように、古い民謡に新しい歌詞をのせて作品をよみがえらせる仕事をした。
この歌は「比嘉盛保,城間ひろみ」の音源がてもとにある。
三番の「なびくな」が「かわるな」になっているのと
五番がない。
さて、この歌の元歌は八重山民謡「久場山越路節」。
その曲そのままではないが、本調子を三下げに変え、
多少変化をくわえると、この曲のように
どこか悲しい、暗さもあり、そして情感もたっぷりの曲になる。
元歌は、題名の語句にとりあげているように、険しい久場山越路という峠を歌ったもの。(次回取り上げる)。
それが「つんだら節」のチラシとなって、歌詞には、ひきさかれていく男女の様子がえがかれる。
わたしには「恨み歌」とも聞えるその曲調が、この本島の「久場山越地節」にはいかされている
ように感じる。
小浜守栄は、その情感たっぷりの曲に男女の契りをかわしつつ
世間の「嵐声」にゆられながら互いの愛を守ろうとする二人の対話を歌にした。
これも名曲である。
Posted by たる一 at 09:38│Comments(3)
│か行
この記事へのコメント
いつも見させてもらっています。とても勉強になります!もしよければ、『ぬんぬくそいそい』もお願いできますか??
Posted by うるま at 2009年04月10日 00:49
偶然というものは
けっこうあるものですね。
ぬんぬくそいそい。
前からやるつもりでしたが
最近よく聞いていた曲です。
近々に取り組むつもりです。
期待なされないでお待ちください。
けっこうあるものですね。
ぬんぬくそいそい。
前からやるつもりでしたが
最近よく聞いていた曲です。
近々に取り組むつもりです。
期待なされないでお待ちください。
Posted by たるー at 2009年04月14日 23:13
すごいです
とても嬉しく思います。ありがとうございます。
首を長く待ってますね
とても嬉しく思います。ありがとうございます。
首を長く待ってますね
Posted by うるま at 2009年04月16日 18:09
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。