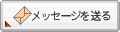2016年08月25日
今帰仁ミャークニー (5/5)
今帰仁ミャークニー
なちじん みゃーくにー
nachijiN myaakunii
◯今帰仁のミャークニー(宮古の音)
語句・なちじん 現在の沖縄県国頭郡今帰仁村を指す。琉球王朝時代の17世紀の頃、今帰仁間切はほぼ本部半島全域だったが18世紀の初めに本部間切と今帰仁間切に分離された。
歌詞参考;「今帰仁ミャークニー歌詞選集」(作成・記録 平成二十五年五月 平良哲男氏)より。
干瀬に居る鳥や 満ち潮恨みゆい 我身や暁ぬ鶏る恨む
ふぃしうるとぅいや みちす(しゅ)うらみゆい わみやあかちちぬとぅいるうらむ
hwishi ni wuru tui ya michis(j)u 'uramiyui wami ya 'akachichi nu tui ru 'uramu
◯沖の岩場に居る鳥は 満潮を恨んで 私は(恋人と別れる時を知らせる)夜明けに鳴く鶏を恨む
語句・ふぃし 「満潮の時は隠れ、干潮になると現れる岩や洲」【沖縄語辞典(国立国語研究所編)】。以下【沖辞】とする。語句・みちす 満潮。「みちしゅ」とも言う。・うらみゆい 恨んでいて。動詞の後に「い」がつく場合は「継続的」(〜していて)の意味。・る 強調の助詞「どぅ」と同じ。
遊びかさにたる 志情きぬ夜や 忘るなよ互に 幾世までん
あしびかさにたる しなさきぬゆるや わしるなよ たげに いくゆまでぃん
'ashibi kasanitaru sinasaki nu yuru ya washiruna yoo tagee ni 'ikuyuu madiN
◯遊びを重ねた 心通わせた夜は 忘れるなよ お互いに 幾世までも
語句・あしび この時代(琉球王朝末期から明治にかけて)の男女の交遊は「もーあしび」(毛遊び)と呼ばれる野外での草むらで酒や肴を飲み食べしつつ歌ったり踊ったりする「遊び」だった。
真夜中どやしが 夢に起こされて 醒めて恋しさや 無ぞが姿
まゆなかどぅやしが いみにうくさりてぃ さみてぃくいしさや んぞがしがた
mayunaka du yashiga 'imi ni 'ukusariti samiti kuishisa ya Nzo ga shigata
◯真夜中であるが 夢で目が覚めて 覚めても恋しいのは 彼女の姿
むとや片袖に ぬちゃる二人やしが 今やちりじりに なたる苦しゃ
むとぅやかたすでぃに ぬちゃるたいやしが なまやちりじりに なたるくりしゃ
mutu ya katasudi ni nucharu tai yashiga nama ya chirijirini nataru kurisya
◯以前は片袖に同じ腕を通すほど仲の良い二人だったが 今はちりじりになって そのことが苦しいことよ
語句・ぬちゃる 穴に通す。<ぬちゅん。
八十なてうてん 唄ぬ忘らりみ 愛し思里(無ぞ)に 唄てぃ聞かさ
はちじゅうなてぃうてぃん うたぬわしらりみ かなしうみんぞに うたてぃちかさ
hachijuu nati utiN 'uta nu wasirarimi kanashi 'umiNzo ni 'utati chikasa
◯八十歳になっても ウタをわすれられまい? 愛しい彼女に歌って聞かせたい。
今帰仁ぬ今泊 フシバルぬ美らさ 今からん後ぅん 代々にぬくさ
なちじんぬいぇーどぅめー ふしばるぬちゅらさ なまからんあとぅん ゆゆにぬくさ
nachijiN nu yeedumee hushibaru nu churasa namakaraN 'atuN yuyu ni nukusa
◯今帰仁の今泊にあるコバテイシは美しい!今から後世に代々残していきたいものだ
語句・ふしばる クファディーサー。コバテイシ。シクンシ科に属する熱帯性の高木。
平良哲男さんの「今帰仁ミャークニー歌詞選集」からの歌詞を検討してきたが、今回で最後となる。
しかし実際には今帰仁ミャークニーで歌われる歌詞は無数にあるといっても過言ではない。
それは人々が暮らす情景や、人の情けを思ったままに歌詞にするという民謡の自然な姿を今帰仁ミャークニーが残しているが所以である。
この歌詞の中には戦後の民謡歌手がナークニーとして歌い継いでいると思われる歌詞も幾つか見える。それだけ強い影響を与えているのだろう。
【フシバルの木】

2016年7月22日に平良哲男さんのご案内で今泊のフシバルを訪れた。
天然記念物、今帰仁、今泊(いぇーどぅめー)のフシバル。樹高18メートル、胸高周囲4.5メートルで推定樹齢は300〜400年と言われる。
「墓の庭に植える。人の泣き声を聞いて成長するといわれている」【沖辞】。
今泊を「いぇーどぅめー」と読むのは、昔は今帰仁と親泊(いぇーどぅめー)が合併して今泊と書くようになったため。

沖縄県と今帰仁村による解説がある。
《字民とフパルシ
戦前は現存するフパルシの根元に接して、もう一本のフパルシがあった。その痕跡は今でも少し残っているが、大きな幹が西側に長く延びていたので、途中に「つっかい」を入れて保護していた。
シマの人たちは、これを「ウー(雄)フパルシ」といい、現存するものを「ミー(雌)フパルシ」と愛称していた。
フパルシとその周辺は、シマ中の子供たちの格好の遊び場であった。彼等は「ミーフパルシ」の大きな幹に挑んで、よじ登りごっこをしたり、横に延びた「ウーフパルシ」の上を伝わり歩いてスリルを味わっていた。
夏から秋にかけて、フパルシにはたくさんの実がなった。その実は甘酸っぱい味がするし、中の種子は落花生のような香りがあるようで、子供たちは競ってその実を求めた。
暴風の時には、沢山の実が落ちるので、近隣の子供たちは、早起きして拾いに行ったものだ。
この老大木は、わが字のど真ん中に根を張り、枝を伸ばし、幾世代ものシマの子供たちのよい遊び相手を勤めてきたばかりでなく、字の重要行事の舞台背景をなして、その存在を誇ってきたのである。》
なちじん みゃーくにー
nachijiN myaakunii
◯今帰仁のミャークニー(宮古の音)
語句・なちじん 現在の沖縄県国頭郡今帰仁村を指す。琉球王朝時代の17世紀の頃、今帰仁間切はほぼ本部半島全域だったが18世紀の初めに本部間切と今帰仁間切に分離された。
歌詞参考;「今帰仁ミャークニー歌詞選集」(作成・記録 平成二十五年五月 平良哲男氏)より。
干瀬に居る鳥や 満ち潮恨みゆい 我身や暁ぬ鶏る恨む
ふぃしうるとぅいや みちす(しゅ)うらみゆい わみやあかちちぬとぅいるうらむ
hwishi ni wuru tui ya michis(j)u 'uramiyui wami ya 'akachichi nu tui ru 'uramu
◯沖の岩場に居る鳥は 満潮を恨んで 私は(恋人と別れる時を知らせる)夜明けに鳴く鶏を恨む
語句・ふぃし 「満潮の時は隠れ、干潮になると現れる岩や洲」【沖縄語辞典(国立国語研究所編)】。以下【沖辞】とする。語句・みちす 満潮。「みちしゅ」とも言う。・うらみゆい 恨んでいて。動詞の後に「い」がつく場合は「継続的」(〜していて)の意味。・る 強調の助詞「どぅ」と同じ。
遊びかさにたる 志情きぬ夜や 忘るなよ互に 幾世までん
あしびかさにたる しなさきぬゆるや わしるなよ たげに いくゆまでぃん
'ashibi kasanitaru sinasaki nu yuru ya washiruna yoo tagee ni 'ikuyuu madiN
◯遊びを重ねた 心通わせた夜は 忘れるなよ お互いに 幾世までも
語句・あしび この時代(琉球王朝末期から明治にかけて)の男女の交遊は「もーあしび」(毛遊び)と呼ばれる野外での草むらで酒や肴を飲み食べしつつ歌ったり踊ったりする「遊び」だった。
真夜中どやしが 夢に起こされて 醒めて恋しさや 無ぞが姿
まゆなかどぅやしが いみにうくさりてぃ さみてぃくいしさや んぞがしがた
mayunaka du yashiga 'imi ni 'ukusariti samiti kuishisa ya Nzo ga shigata
◯真夜中であるが 夢で目が覚めて 覚めても恋しいのは 彼女の姿
むとや片袖に ぬちゃる二人やしが 今やちりじりに なたる苦しゃ
むとぅやかたすでぃに ぬちゃるたいやしが なまやちりじりに なたるくりしゃ
mutu ya katasudi ni nucharu tai yashiga nama ya chirijirini nataru kurisya
◯以前は片袖に同じ腕を通すほど仲の良い二人だったが 今はちりじりになって そのことが苦しいことよ
語句・ぬちゃる 穴に通す。<ぬちゅん。
八十なてうてん 唄ぬ忘らりみ 愛し思里(無ぞ)に 唄てぃ聞かさ
はちじゅうなてぃうてぃん うたぬわしらりみ かなしうみんぞに うたてぃちかさ
hachijuu nati utiN 'uta nu wasirarimi kanashi 'umiNzo ni 'utati chikasa
◯八十歳になっても ウタをわすれられまい? 愛しい彼女に歌って聞かせたい。
今帰仁ぬ今泊 フシバルぬ美らさ 今からん後ぅん 代々にぬくさ
なちじんぬいぇーどぅめー ふしばるぬちゅらさ なまからんあとぅん ゆゆにぬくさ
nachijiN nu yeedumee hushibaru nu churasa namakaraN 'atuN yuyu ni nukusa
◯今帰仁の今泊にあるコバテイシは美しい!今から後世に代々残していきたいものだ
語句・ふしばる クファディーサー。コバテイシ。シクンシ科に属する熱帯性の高木。
平良哲男さんの「今帰仁ミャークニー歌詞選集」からの歌詞を検討してきたが、今回で最後となる。
しかし実際には今帰仁ミャークニーで歌われる歌詞は無数にあるといっても過言ではない。
それは人々が暮らす情景や、人の情けを思ったままに歌詞にするという民謡の自然な姿を今帰仁ミャークニーが残しているが所以である。
この歌詞の中には戦後の民謡歌手がナークニーとして歌い継いでいると思われる歌詞も幾つか見える。それだけ強い影響を与えているのだろう。
【フシバルの木】

2016年7月22日に平良哲男さんのご案内で今泊のフシバルを訪れた。
天然記念物、今帰仁、今泊(いぇーどぅめー)のフシバル。樹高18メートル、胸高周囲4.5メートルで推定樹齢は300〜400年と言われる。
「墓の庭に植える。人の泣き声を聞いて成長するといわれている」【沖辞】。
今泊を「いぇーどぅめー」と読むのは、昔は今帰仁と親泊(いぇーどぅめー)が合併して今泊と書くようになったため。

沖縄県と今帰仁村による解説がある。
《字民とフパルシ
戦前は現存するフパルシの根元に接して、もう一本のフパルシがあった。その痕跡は今でも少し残っているが、大きな幹が西側に長く延びていたので、途中に「つっかい」を入れて保護していた。
シマの人たちは、これを「ウー(雄)フパルシ」といい、現存するものを「ミー(雌)フパルシ」と愛称していた。
フパルシとその周辺は、シマ中の子供たちの格好の遊び場であった。彼等は「ミーフパルシ」の大きな幹に挑んで、よじ登りごっこをしたり、横に延びた「ウーフパルシ」の上を伝わり歩いてスリルを味わっていた。
夏から秋にかけて、フパルシにはたくさんの実がなった。その実は甘酸っぱい味がするし、中の種子は落花生のような香りがあるようで、子供たちは競ってその実を求めた。
暴風の時には、沢山の実が落ちるので、近隣の子供たちは、早起きして拾いに行ったものだ。
この老大木は、わが字のど真ん中に根を張り、枝を伸ばし、幾世代ものシマの子供たちのよい遊び相手を勤めてきたばかりでなく、字の重要行事の舞台背景をなして、その存在を誇ってきたのである。》
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。