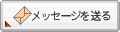2014年03月07日
かたみ節 (八重山民謡)
かたみ節
かたみぶし
katami bushi
◯男女の契りの唄
語句・かたみ 「男女の契り。また、契りとして取りかわすもの」(【沖縄語辞典(国立国語研究所編)】以下【沖辞】と略す。)
歌詞は「八重山古典民謡工工四上巻」(大濱安伴編著)を参考。
一、さてぃむ目出度や此ぬ御代に(さー)祝いぬ限りねらん
さてぃむ めでたや(みでぃた)や くぬ みゆに (さー)ゆわいぬ かぎりねらん
satimu medeta(midita) ya kunu miyu ni (saa) yuwai nu kaziri neeraN
◯さても めでたいこの御世に祝いの限りはないほどめでたい
語句・さてぃむ <さってぃむ。「さても。おやまあ。いやはや。珍しい場合・あきれた場合・深く感じた場合などにいう。」【沖辞】。さてぃ(さて)+む(強調)。・めでたや めでたいことよ! 「めでたい」は当然、沖縄語辞典にはない。「めでたい」と本島では歌うが、この読みは本土方言の影響。八重山の歌い方せは「みでぃたや」。・ゆわい これも本土方言の影響。沖縄語では、「お祝い」は「いうぇー」、「ゆーうぇー」、「ういうぇー」、「うゆうぇー」【沖辞】。・かぎり 限り。本島の「かたみ節」は「かじり」。・ねらん<neeraN ない。歌の中では短く「ねらん」という発音になる。
(囃子)あすびたぬしむに すり わんやかたみくいら ちとぅしまでぃん
あすびたぬしむに すり わんや かたみくぃら ちとぅしまでぃん
'ashubi tanushimu ni suri waN ya katami kuira chitushi madiN
◯遊ぶ楽しみに 私は形見をあげよう 千年までも(以下 囃子は略)
語句・かたみ ①男女の契り契りとして交わす物②死者、長い別れの人の形見。【沖辞】。ここではめでたい歌なので①。・くいら あげよう。【石垣方言辞典(宮城信勇)】を見ても、八重山では「くぃゆん」はなく、「ひーるん」「ひーん」があるだけである。この歌詞が本島方言で作られた可能性が大きい。「くぃゆん」の意味については「かたみ節(本島)」を参照。
ニ、一番願わば福禄寿 すぬふか無蔵とぅ連りてぃ
いちばん にがわば ふくるくじゅ すぬふか んぞとぅ ちりてぃ
'ichibaN nigawaba hukurukuju sunuhuka Nzo tu chiriti
◯一番願うならば 福禄寿 その他には貴女を連れ添って
語句・ふくるくじゅ 「福禄寿」の「福」は「幸福」、「禄」は「財産」、「寿」は「長寿」を意味する。Wikipediaには「福禄寿(ふくろくじゅ)は、七福神の一つ。道教で強く希求される3種の願い、すなわち幸福(現代日本語でいう漠然とした幸福全般のことではなく血のつながった実の子に恵まれること)、封禄(財産のこと)、長寿(単なる長生きではなく健康を伴う長寿)の三徳を具現化したものである。宋の道士・天南星の化身や、南極星の化身(南極老人)とされ、七福神の寿老人と同体、異名の神とされることもある。 福禄人(ふくろくじん)とも言われる」
三、無蔵とぅ我んとぅやむとぅゆりぬ 契りぬ深さあたん
んぞとぅ わんとぅや むとぅゆりぬ ちぎりぬふかさあたん
Nzo tu waN tu ya mutu yuri nu chigiri nu hukasa 'ataN
◯貴女と私は昔からの契りの深いものがあったのだ
語句・むとぅ 「元。元来」「muutuと同じ」【沖辞】。「muutu」とは「元。本。みなもと。また、先祖」【沖辞】とあるように、ここでは「先祖」つまり「前世からの縁があった」と解釈するほうが自然だろう。・ちぎり 契り。本島かたみ節は「ちじり」。・あたん あった。'ataN('aNの過去形)。
四、百歳なるまでぃ肝一つ 変わるな 元ぬ心
ひゃくせ なるまでぃちむふぃとぅち かわるなむとぅぬくくる
hyakusee narumadi chimu hwituchi kawaruna mutu nu kukuru
◯百歳になるまで二人の心は一つだ 変わるな昔からの心
語句・せー 歳。大和口のsaiは変化してseeとなる。「さー」「さい」と歌っているものも多い。
八重山民謡にある「かたみ節」をとりあげた。
結婚式などのお祝いの席や、座開きで歌われることが多い祝儀歌。
2005年にこのブログとりあげた本島で歌われる「かたみ節」(「本島かたみ節」とここでは呼ぶ)の元歌である。
【実在したとされる「かたみ節」のモデル】
喜舍場永珣の「八重山島民謡誌」によると、
「当時琉球の馬艦船(マーランブニ)が風波の都合でこの久志間港に停泊した。この際何時しか久志間村の女と船乗りの男とは水も漏らさない慕しき仲となり、二世三世迄もと二人は深く契った。」
この様子を首里から派遣されていた役人の黒島英任が「かたみ節」にしたとある。
黒島英任が、1732年に平久保村に赴任してきたそうだから、だいたい280年前後ほど昔の歌ということになる。
これが本当なら、かたみ節には実在のモデルがいたことになる。
ちなみに、マーランブニとは山原船ともいい、当時の航海によく使われていた帆が二つある帆船である。
【八重山かたみ節と本島のそれとの違い】
いくつか語句の読みかたに若干の相違がある。
(八重山) (本島)
あすび ー あしび
くいら ー くぃら
ちぎり ー ちじり
一番の「めでた」を「みでぃた」とうたう八重山の流派もある。「安室流」。
三線の壺(つぼ、ちぶ)で「尺」の位置がちがう。
【かたみ節の生まれた土地】
石垣島の北部の平久保村と伊原間村との間には、昔「久志間」(くしま)という村が昔はあった。現在は廃村となっている。
現在はそのあたりを久宇良浜という。

▲狭い道をぬけると



280年ほど前にも、この浜にかたみ節のモデルとなった夫婦がきているかもしれない。
いや、いまでもひょっこりでてくるのでは?
とロマンチックな気持ちにさせる美しい浜辺だった。
(2014年2月に筆者撮影)
本島で歌われる「かたみ節」はこちら。
かたみぶし
katami bushi
◯男女の契りの唄
語句・かたみ 「男女の契り。また、契りとして取りかわすもの」(【沖縄語辞典(国立国語研究所編)】以下【沖辞】と略す。)
歌詞は「八重山古典民謡工工四上巻」(大濱安伴編著)を参考。
一、さてぃむ目出度や此ぬ御代に(さー)祝いぬ限りねらん
さてぃむ めでたや(みでぃた)や くぬ みゆに (さー)ゆわいぬ かぎりねらん
satimu medeta(midita) ya kunu miyu ni (saa) yuwai nu kaziri neeraN
◯さても めでたいこの御世に祝いの限りはないほどめでたい
語句・さてぃむ <さってぃむ。「さても。おやまあ。いやはや。珍しい場合・あきれた場合・深く感じた場合などにいう。」【沖辞】。さてぃ(さて)+む(強調)。・めでたや めでたいことよ! 「めでたい」は当然、沖縄語辞典にはない。「めでたい」と本島では歌うが、この読みは本土方言の影響。八重山の歌い方せは「みでぃたや」。・ゆわい これも本土方言の影響。沖縄語では、「お祝い」は「いうぇー」、「ゆーうぇー」、「ういうぇー」、「うゆうぇー」【沖辞】。・かぎり 限り。本島の「かたみ節」は「かじり」。・ねらん<neeraN ない。歌の中では短く「ねらん」という発音になる。
(囃子)あすびたぬしむに すり わんやかたみくいら ちとぅしまでぃん
あすびたぬしむに すり わんや かたみくぃら ちとぅしまでぃん
'ashubi tanushimu ni suri waN ya katami kuira chitushi madiN
◯遊ぶ楽しみに 私は形見をあげよう 千年までも(以下 囃子は略)
語句・かたみ ①男女の契り契りとして交わす物②死者、長い別れの人の形見。【沖辞】。ここではめでたい歌なので①。・くいら あげよう。【石垣方言辞典(宮城信勇)】を見ても、八重山では「くぃゆん」はなく、「ひーるん」「ひーん」があるだけである。この歌詞が本島方言で作られた可能性が大きい。「くぃゆん」の意味については「かたみ節(本島)」を参照。
ニ、一番願わば福禄寿 すぬふか無蔵とぅ連りてぃ
いちばん にがわば ふくるくじゅ すぬふか んぞとぅ ちりてぃ
'ichibaN nigawaba hukurukuju sunuhuka Nzo tu chiriti
◯一番願うならば 福禄寿 その他には貴女を連れ添って
語句・ふくるくじゅ 「福禄寿」の「福」は「幸福」、「禄」は「財産」、「寿」は「長寿」を意味する。Wikipediaには「福禄寿(ふくろくじゅ)は、七福神の一つ。道教で強く希求される3種の願い、すなわち幸福(現代日本語でいう漠然とした幸福全般のことではなく血のつながった実の子に恵まれること)、封禄(財産のこと)、長寿(単なる長生きではなく健康を伴う長寿)の三徳を具現化したものである。宋の道士・天南星の化身や、南極星の化身(南極老人)とされ、七福神の寿老人と同体、異名の神とされることもある。 福禄人(ふくろくじん)とも言われる」
三、無蔵とぅ我んとぅやむとぅゆりぬ 契りぬ深さあたん
んぞとぅ わんとぅや むとぅゆりぬ ちぎりぬふかさあたん
Nzo tu waN tu ya mutu yuri nu chigiri nu hukasa 'ataN
◯貴女と私は昔からの契りの深いものがあったのだ
語句・むとぅ 「元。元来」「muutuと同じ」【沖辞】。「muutu」とは「元。本。みなもと。また、先祖」【沖辞】とあるように、ここでは「先祖」つまり「前世からの縁があった」と解釈するほうが自然だろう。・ちぎり 契り。本島かたみ節は「ちじり」。・あたん あった。'ataN('aNの過去形)。
四、百歳なるまでぃ肝一つ 変わるな 元ぬ心
ひゃくせ なるまでぃちむふぃとぅち かわるなむとぅぬくくる
hyakusee narumadi chimu hwituchi kawaruna mutu nu kukuru
◯百歳になるまで二人の心は一つだ 変わるな昔からの心
語句・せー 歳。大和口のsaiは変化してseeとなる。「さー」「さい」と歌っているものも多い。
八重山民謡にある「かたみ節」をとりあげた。
結婚式などのお祝いの席や、座開きで歌われることが多い祝儀歌。
2005年にこのブログとりあげた本島で歌われる「かたみ節」(「本島かたみ節」とここでは呼ぶ)の元歌である。
【実在したとされる「かたみ節」のモデル】
喜舍場永珣の「八重山島民謡誌」によると、
「当時琉球の馬艦船(マーランブニ)が風波の都合でこの久志間港に停泊した。この際何時しか久志間村の女と船乗りの男とは水も漏らさない慕しき仲となり、二世三世迄もと二人は深く契った。」
この様子を首里から派遣されていた役人の黒島英任が「かたみ節」にしたとある。
黒島英任が、1732年に平久保村に赴任してきたそうだから、だいたい280年前後ほど昔の歌ということになる。
これが本当なら、かたみ節には実在のモデルがいたことになる。
ちなみに、マーランブニとは山原船ともいい、当時の航海によく使われていた帆が二つある帆船である。
【八重山かたみ節と本島のそれとの違い】
いくつか語句の読みかたに若干の相違がある。
(八重山) (本島)
あすび ー あしび
くいら ー くぃら
ちぎり ー ちじり
一番の「めでた」を「みでぃた」とうたう八重山の流派もある。「安室流」。
三線の壺(つぼ、ちぶ)で「尺」の位置がちがう。
【かたみ節の生まれた土地】
石垣島の北部の平久保村と伊原間村との間には、昔「久志間」(くしま)という村が昔はあった。現在は廃村となっている。
現在はそのあたりを久宇良浜という。

▲狭い道をぬけると



280年ほど前にも、この浜にかたみ節のモデルとなった夫婦がきているかもしれない。
いや、いまでもひょっこりでてくるのでは?
とロマンチックな気持ちにさせる美しい浜辺だった。
(2014年2月に筆者撮影)
本島で歌われる「かたみ節」はこちら。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。