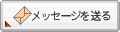2006年07月06日
踊いクワディサー節
踊いクワディサー節
'うどぅいくふぁでぃさーぶし
'udui kuhwadisaa bushi
(古典女踊り)
うちならし ならし 四ツ竹わならち 今日や御座出じて あしぶうりしや
'うちならしならし ゆちだきわならち きゆや'うざ'んじてぃ'あしぶ'うりしゃ
'uchinarashi narashi yuchidaki wa narachi kiyu ya 'uza 'Njiti 'ashibu 'urisha
○うち鳴らせ 鳴らせ 四ツ竹は鳴らして 今日は御座敷に出て遊んで嬉しいことよ
(古典)
こはでさのお月まどまどど照ゆる よそ目まどはかて 忍でいまうれ
くふぁでぃさぬ'うつぃち まどぅまどぅどぅてぃゆる ゆすみまどぅはかてぃ しぬでぃ'いもり
kuhwadisa nu 'utsuchi madumadu du tiyuru yusumi maduhakati shinudi 'imoori
○クワディサの(葉の間から)お月は隙間隙間に照る 他人の目の隙間を見はかって忍んでいらしてください
'うどぅいくふぁでぃさーぶし
'udui kuhwadisaa bushi
(古典女踊り)
うちならし ならし 四ツ竹わならち 今日や御座出じて あしぶうりしや
'うちならしならし ゆちだきわならち きゆや'うざ'んじてぃ'あしぶ'うりしゃ
'uchinarashi narashi yuchidaki wa narachi kiyu ya 'uza 'Njiti 'ashibu 'urisha
○うち鳴らせ 鳴らせ 四ツ竹は鳴らして 今日は御座敷に出て遊んで嬉しいことよ
(古典)
こはでさのお月まどまどど照ゆる よそ目まどはかて 忍でいまうれ
くふぁでぃさぬ'うつぃち まどぅまどぅどぅてぃゆる ゆすみまどぅはかてぃ しぬでぃ'いもり
kuhwadisa nu 'utsuchi madumadu du tiyuru yusumi maduhakati shinudi 'imoori
○クワディサの(葉の間から)お月は隙間隙間に照る 他人の目の隙間を見はかって忍んでいらしてください
解説
(語句)
・クファディサー 広葉落葉樹。葉がおおきく美ら海水族館にも庭に植えてあったが、辞書によると墓の庭に植える、人の鳴き声を聴いて成長するんだとか。

先日久高島で見たクファディサー
・うちならし 鳴らせ 命令形
「ならして」という訳がよくあるが、連用形(。。して)なら「ならち」である。「鳴らせ」の「se」が三母音化で「si」となったもの。
・わ は
普通は「や」である。ヤマトグチとの関わりを感じさせる。
・うざ お座敷
「'uza」には①内閣、政府②お座敷 部屋の敬語 普通もっともよい客間をさす
・つぃち 月
月の発音は、首里語では「つぃち」、平民は「ちち」。
微妙に違う。古典では正確な発音が求められる。
・まどぅまどぅ 隙間すきま
暇暇に、暇を見て、という意味もある。
・ゆすみ 他所の目 他人の目
(かなさんど)
・はかてぃ (み)はからって
<はかゆん 計る
(コメント)
古典女踊りで有名な「四つ竹」、その曲は「踊りクワディサー節」。
ゆったりとした曲調、沖縄音階もたっぷり。
しかし、歌詞を見ても「どうしてクワディサーなのか?」わからない。
それは古典の中に「こはでさ」=クワディサをモチーフにした琉歌があるからなのだ。
通い婚を誘う歌に、クワディサーの葉の様子がひっかけられている。
月の光が葉の隙間から漏れて見えるように、人の目を盗んでいらっしゃい。
その曲に、「踊りクファディサー節」の歌詞があとからつけられたのだろう。
(語句)
・クファディサー 広葉落葉樹。葉がおおきく美ら海水族館にも庭に植えてあったが、辞書によると墓の庭に植える、人の鳴き声を聴いて成長するんだとか。
先日久高島で見たクファディサー
・うちならし 鳴らせ 命令形
「ならして」という訳がよくあるが、連用形(。。して)なら「ならち」である。「鳴らせ」の「se」が三母音化で「si」となったもの。
・わ は
普通は「や」である。ヤマトグチとの関わりを感じさせる。
・うざ お座敷
「'uza」には①内閣、政府②お座敷 部屋の敬語 普通もっともよい客間をさす
・つぃち 月
月の発音は、首里語では「つぃち」、平民は「ちち」。
微妙に違う。古典では正確な発音が求められる。
・まどぅまどぅ 隙間すきま
暇暇に、暇を見て、という意味もある。
・ゆすみ 他所の目 他人の目
(かなさんど)
・はかてぃ (み)はからって
<はかゆん 計る
(コメント)
古典女踊りで有名な「四つ竹」、その曲は「踊りクワディサー節」。
ゆったりとした曲調、沖縄音階もたっぷり。
しかし、歌詞を見ても「どうしてクワディサーなのか?」わからない。
それは古典の中に「こはでさ」=クワディサをモチーフにした琉歌があるからなのだ。
通い婚を誘う歌に、クワディサーの葉の様子がひっかけられている。
月の光が葉の隙間から漏れて見えるように、人の目を盗んでいらっしゃい。
その曲に、「踊りクファディサー節」の歌詞があとからつけられたのだろう。
Posted by たる一 at 23:31│Comments(2)
│あ行
この記事へのコメント
ぼくもじつは不思議に思っていたんですよ。
踊りの地方をしたときは「四ツ竹」としてやりました。これは分かる。
あとで分かったんですけど、「踊こはでさ節」の本歌にクワディーサーがかかわっていたんですね。分かりにくいなあ。
踊りの地方をしたときは「四ツ竹」としてやりました。これは分かる。
あとで分かったんですけど、「踊こはでさ節」の本歌にクワディーサーがかかわっていたんですね。分かりにくいなあ。
Posted by コロリ at 2007年03月17日 20:32
コロリさん
おひさしぶりです。
八重山民謡の道がんばっておられますか。
クファディサの木は見るからに物悲しい。
エイサーではおなじみの屋慶名にあるクファディサも立派です。
おひさしぶりです。
八重山民謡の道がんばっておられますか。
クファディサの木は見るからに物悲しい。
エイサーではおなじみの屋慶名にあるクファディサも立派です。
Posted by せき ひろし(たるー) at 2007年03月18日 16:48
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。