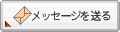2018年02月11日
谷茶前
谷茶前
taNcha mee
たんちゃめー
◯谷茶の前
語句・たんちゃめー 谷茶前の浜、が正式な呼び名である。「の浜」が省略されている。
一、谷茶前の浜に(よー)スルル小が寄ててんどー(ヘイ)(ナンチャマシマシ ディアンガ ソイソイ)
たんちゃめーぬはまに(よー)するるぐぁーがゆてぃてぃんどー(へい)(なんちゃましまし でぃー あんぐぁー そいそい)
taNchamee nu hama ni yoo sururugwaa ga yutitiN doo (hei naNca mashimashi dii aNgwaa soi soi)
◯谷茶(の)前の浜に きびなごが集まっているぞー
語句・するるぐぁ 「小魚の名。きびなご。体長10センチたらずで、かつおの釣り餌に用いられる」【沖縄語辞典(国立国語研究所編)】(以下【沖辞】と略す)。・なんちゃましまし でぃあんぐぁーそいそい 囃し言葉。囃し言葉は拍子を揃えたりするものも多い。また昔の囃し言葉が伝搬する間に別の語句と入れ替わったりもする。この場合「なんちゃ」は「たんちゃ」と歌われる曲もある。「ましまし」は「むさむさ」とも。「でぃーあんぐぁー」は意味がはっきりしているので変化がほとんど見られない。「でぃー」は「さあ」であり、「あんぐぁー」は平民の「お姉さん」だ。「そいそい」は「やくしく」(約束)となったりもする。
二、スルル小やあらん大和ミズンど やんてんどー
するるぐぁーやあらん やまとぅみじゅんどぅ やんてぃんどー
sururugwaa ya 'araN yamatu mijuN du yaNtiN doo
◯きびなごではない ヤマトミズン(ニシンの一種)だぞ
語句・やまとぅみじゅん 正式には「ニシン科ニシン亜科ヤマトミズン属」と言う分類になる。いわゆるニシン科の魚だが、辞書でも「鰯の一種」【琉球語辞典(半田一郎)】と書かれることが多い。しかし同じニシン科の中ではあるが、ヤマトゥミジュンはヤマトゥミジュン属、イワシの代表マイワシはマイワシ属となって属が違っている。(余談ながらカタクチイワシはニシン目カタクチイワシ科となって少し別の科)
三、兄達や うり取いが あん小や かみてうり売いが
あふぃーたーや 'うりとぅいが あんぐぁーや かみてぃ'うり'ういが
'ahwiitaaya 'uri tuiga 'angwaaya kamiti 'uri 'uiga
◯兄さんたちはそれを採るために 姉さんたちは頭に乗せて売るために
語句・あふぃーたー 兄さん達。「あふぃー」は「平民の兄さん」。「あっぴー」とも言う。ちなみに士族は「やっちー」。・とぅいが 取りに。「が」は「〜しに」の意味。したがって、この後に「いちゅん」(行く)が省略されている。・かみてぃ頭に載せて。<かみゆん。 「頭上に載せる」【琉辞】。
四、うり売て戻いぬアン小が 匂いぬしゅらさ
'うり'うてぃもぅどぅいぬ 'あんぐぁーが にうぃぬしゅらさ
'uri 'uti mudui nu 'angwaa ga niwi nu shurasa
◯それを売って戻った姉さんの 匂いのかわいらしいことよ
語句・しゅらさ かわいらしいことよ!<しゅーらーさん。「かわいい」【琉辞】。形容詞の体言止め(〜さ)は「とても〜なことよ!」という感嘆の意味がある。
五、うり取ゆる島や 謝名と宇地泊
'うりとぅゆるしまや じゃな とぅ 'うちどぅまい
'urituyuru shima ya jana tu 'uchidumai
◯それを採る村は 謝名と宇地泊
語句・しま 「島」つまりアイランドではなく村などの地名を指す。・じゃなとぅうちどぅまい 謝名は今帰仁村にある。宇地泊は宜野湾市にある。単にミジュンが良く採れる地域をさしているのか、どうなのか。不明。
(コメント)
沖縄は北部、西海岸の恩納村谷茶(たんちゃ)。そこに伝わる漁村ののどかな男女の風景を歌にしたもの。
明治初期に舞踊の名人といわれた玉城盛重が谷茶に伝わる古謡を元に振り付けをして人気を博した。
最初は女の手踊りだけだったが、やがて女がバーキ(竹籠)を、男がウェーク(櫂)を持って踊る雑踊り(ぞう うどい zoo udui)と言われる現在の型が生み出されて行く。
舞踊曲としては「出羽」(んじふぁ;舞台に出てくる場面)に「伊計はなり節」が使われることが多い。また谷茶前が先でチラシ(続けて弾く曲)に「伊計はなり節」がくることもある。
三線では三下げ(さんさぎ saNsagi)で、沖縄音階ほぼ100%の曲。
早弾きで、タッタタ、タッタタのリズムで弾くことで躍動感に満ちている。
(注意点)
・谷茶前 地名は「谷茶」のみで「前」は、「前の浜」(meenuhama)という慣用の語句。
・「谷茶」と言う地名は恩納村と本部町にある。谷茶前は恩納村が発祥とされているが本部町だとする説もある。
・ヤマトミジュン、ニシンの一種である。

明治初期は歌詞のこの部分は「スク」であったようだ(仲宗根幸市氏)→「マジク」と言う魚の名前が出てくるのだが、これについてはまた後日検討する。
・三番、「うりとぅいが」「うりういが」のそれぞれの後に「いちゅん 'icuN」が省略されている。「・・を採り・・を売り」とリズム良く歌えるようにしてある。
・四番「しゅらさ」は舞踊曲の場合で、民謡では「ひるぐささ」(臭さ)であるという(仲宗根幸市氏 島うた紀行 第1集)これも後日検討しよう。
魚を一日中頭に乗せて売っていたら魚臭くなるでしょうね。
いろいろな歌詞もあるし、時代によりそれも変わる。
民謡の運命(さだめ)である。
人々の口を介して、いいものが残り、変えられてよいものになる。
時代の好みに合わせて変わり、人々は、よくないものは捨てていく。
捨てられたものは戻ってこない。
新しい歌詞が加えられて、元の姿は、見えなくなる。
谷茶前もそういう運命をたどり、今日私たちに、進化した姿を見せてくれるのである。
(歌碑)
昔の谷茶前の歌碑は、少しわかりにくい行きずらい場所にあった。

現在は浜の近くに駐車場と共に新設された。

次回はこの歌碑の歌詞を取り上げたい。
(2018年2月11日 加筆修正)
【このブログが本になりました!】
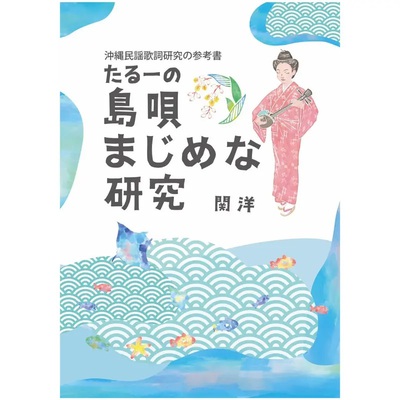
書籍【たるーの島唄まじめな研究】のご購入はこちら
taNcha mee
たんちゃめー
◯谷茶の前
語句・たんちゃめー 谷茶前の浜、が正式な呼び名である。「の浜」が省略されている。
一、谷茶前の浜に(よー)スルル小が寄ててんどー(ヘイ)(ナンチャマシマシ ディアンガ ソイソイ)
たんちゃめーぬはまに(よー)するるぐぁーがゆてぃてぃんどー(へい)(なんちゃましまし でぃー あんぐぁー そいそい)
taNchamee nu hama ni yoo sururugwaa ga yutitiN doo (hei naNca mashimashi dii aNgwaa soi soi)
◯谷茶(の)前の浜に きびなごが集まっているぞー
語句・するるぐぁ 「小魚の名。きびなご。体長10センチたらずで、かつおの釣り餌に用いられる」【沖縄語辞典(国立国語研究所編)】(以下【沖辞】と略す)。・なんちゃましまし でぃあんぐぁーそいそい 囃し言葉。囃し言葉は拍子を揃えたりするものも多い。また昔の囃し言葉が伝搬する間に別の語句と入れ替わったりもする。この場合「なんちゃ」は「たんちゃ」と歌われる曲もある。「ましまし」は「むさむさ」とも。「でぃーあんぐぁー」は意味がはっきりしているので変化がほとんど見られない。「でぃー」は「さあ」であり、「あんぐぁー」は平民の「お姉さん」だ。「そいそい」は「やくしく」(約束)となったりもする。
二、スルル小やあらん大和ミズンど やんてんどー
するるぐぁーやあらん やまとぅみじゅんどぅ やんてぃんどー
sururugwaa ya 'araN yamatu mijuN du yaNtiN doo
◯きびなごではない ヤマトミズン(ニシンの一種)だぞ
語句・やまとぅみじゅん 正式には「ニシン科ニシン亜科ヤマトミズン属」と言う分類になる。いわゆるニシン科の魚だが、辞書でも「鰯の一種」【琉球語辞典(半田一郎)】と書かれることが多い。しかし同じニシン科の中ではあるが、ヤマトゥミジュンはヤマトゥミジュン属、イワシの代表マイワシはマイワシ属となって属が違っている。(余談ながらカタクチイワシはニシン目カタクチイワシ科となって少し別の科)
三、兄達や うり取いが あん小や かみてうり売いが
あふぃーたーや 'うりとぅいが あんぐぁーや かみてぃ'うり'ういが
'ahwiitaaya 'uri tuiga 'angwaaya kamiti 'uri 'uiga
◯兄さんたちはそれを採るために 姉さんたちは頭に乗せて売るために
語句・あふぃーたー 兄さん達。「あふぃー」は「平民の兄さん」。「あっぴー」とも言う。ちなみに士族は「やっちー」。・とぅいが 取りに。「が」は「〜しに」の意味。したがって、この後に「いちゅん」(行く)が省略されている。・かみてぃ頭に載せて。<かみゆん。 「頭上に載せる」【琉辞】。
四、うり売て戻いぬアン小が 匂いぬしゅらさ
'うり'うてぃもぅどぅいぬ 'あんぐぁーが にうぃぬしゅらさ
'uri 'uti mudui nu 'angwaa ga niwi nu shurasa
◯それを売って戻った姉さんの 匂いのかわいらしいことよ
語句・しゅらさ かわいらしいことよ!<しゅーらーさん。「かわいい」【琉辞】。形容詞の体言止め(〜さ)は「とても〜なことよ!」という感嘆の意味がある。
五、うり取ゆる島や 謝名と宇地泊
'うりとぅゆるしまや じゃな とぅ 'うちどぅまい
'urituyuru shima ya jana tu 'uchidumai
◯それを採る村は 謝名と宇地泊
語句・しま 「島」つまりアイランドではなく村などの地名を指す。・じゃなとぅうちどぅまい 謝名は今帰仁村にある。宇地泊は宜野湾市にある。単にミジュンが良く採れる地域をさしているのか、どうなのか。不明。
(コメント)
沖縄は北部、西海岸の恩納村谷茶(たんちゃ)。そこに伝わる漁村ののどかな男女の風景を歌にしたもの。
明治初期に舞踊の名人といわれた玉城盛重が谷茶に伝わる古謡を元に振り付けをして人気を博した。
最初は女の手踊りだけだったが、やがて女がバーキ(竹籠)を、男がウェーク(櫂)を持って踊る雑踊り(ぞう うどい zoo udui)と言われる現在の型が生み出されて行く。
舞踊曲としては「出羽」(んじふぁ;舞台に出てくる場面)に「伊計はなり節」が使われることが多い。また谷茶前が先でチラシ(続けて弾く曲)に「伊計はなり節」がくることもある。
三線では三下げ(さんさぎ saNsagi)で、沖縄音階ほぼ100%の曲。
早弾きで、タッタタ、タッタタのリズムで弾くことで躍動感に満ちている。
(注意点)
・谷茶前 地名は「谷茶」のみで「前」は、「前の浜」(meenuhama)という慣用の語句。
・「谷茶」と言う地名は恩納村と本部町にある。谷茶前は恩納村が発祥とされているが本部町だとする説もある。
・ヤマトミジュン、ニシンの一種である。

明治初期は歌詞のこの部分は「スク」であったようだ(仲宗根幸市氏)→「マジク」と言う魚の名前が出てくるのだが、これについてはまた後日検討する。
・三番、「うりとぅいが」「うりういが」のそれぞれの後に「いちゅん 'icuN」が省略されている。「・・を採り・・を売り」とリズム良く歌えるようにしてある。
・四番「しゅらさ」は舞踊曲の場合で、民謡では「ひるぐささ」(臭さ)であるという(仲宗根幸市氏 島うた紀行 第1集)これも後日検討しよう。
魚を一日中頭に乗せて売っていたら魚臭くなるでしょうね。
いろいろな歌詞もあるし、時代によりそれも変わる。
民謡の運命(さだめ)である。
人々の口を介して、いいものが残り、変えられてよいものになる。
時代の好みに合わせて変わり、人々は、よくないものは捨てていく。
捨てられたものは戻ってこない。
新しい歌詞が加えられて、元の姿は、見えなくなる。
谷茶前もそういう運命をたどり、今日私たちに、進化した姿を見せてくれるのである。
(歌碑)
昔の谷茶前の歌碑は、少しわかりにくい行きずらい場所にあった。

現在は浜の近くに駐車場と共に新設された。

次回はこの歌碑の歌詞を取り上げたい。
(2018年2月11日 加筆修正)
【このブログが本になりました!】
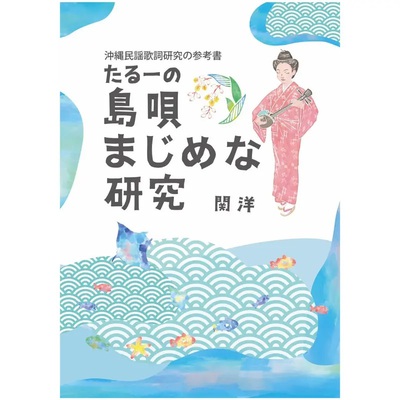
書籍【たるーの島唄まじめな研究】のご購入はこちら
2018年2月11日に加筆修正したものを再度掲載しています。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。