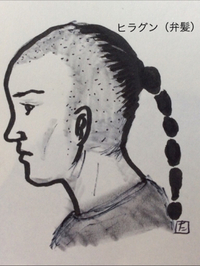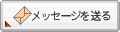2005年11月02日
浜千鳥
浜千鳥
chijyuyaa
◯浜千鳥
語句・ちじゅやー 「千鳥。浜に群れて鳴き飛ぶ小鳥。cizujaaともいう。文語はhama-ciduri」【沖縄語辞典(国立国語研究所編)】(以下【沖辞】と略す)文語では「はまちどぅり」。小鳥は「ちじゅい」という。
一、旅や浜宿い 草ぬ(ヤリ)葉ぬ枕 寝てぃん忘ららん 我親ぬ御側
tabiya hamayadui kusanu (yari)hwaa nu makura nitiN washiraraN wa’uyanu ‘usuba
たびや はまやどぅい くさぬ (やり)ふぁーぬまくら にてぃんわしららん わやぬ ‘うすば
◯旅は浜に宿をし、草の葉の(ヤレは囃子言葉)枕 寝ても忘れられない 私の親のお側
語句・やどぅい 「やどぅゆん」(泊まる)という動詞の活用形ともとれるが、「屋取」(やーどぅい)という「都落ちした士族の部落。都に定職なく都落ちした士族は、平民の村落と離れた所に居を定め、農業を営むようになった。その部落をいう」【沖辞】。すなわち琉球王朝末期に士族が増えすぎたために首里から各地方に士族を移住させ、平民の村落とは区別して農業を営ませた。後の記事に見るようにこの歌詞が実在の屋取部落の士族によって歌われたウタである可能性も高い。・やり 囃子言葉。「やれ」と歌う事もある。・わや 我親(わーうや)の短縮。
※千鳥や 浜居てぃ チュイチュイナ
chizuyaa ya hama wuti chui chui naa
ちじゅやーや はま うぅてぃ ちゅいちゅいなー
◯千鳥は浜に居て チュイチュイ(と鳴いている)
(以下囃子は全て同じため省略する。)
語句・うぅてぃ 居て。存在動詞「うぅん」の活用形。
二、旅宿ぬ寝覚め 枕すばだてぃてぃ 覚出すさ昔 夜半ぬ辛さ
tabiyadu nu nizami makura subadatiti ‘ubizasusa ‘Nkasi yuhwa nu chirasa
たびやどぅぬにざみ まくらすばだてぃてぃ うびじゃすさんかし ゆふぁぬちらさ
◯旅宿で目覚め 枕をかたむけて 思い出すよ昔を こんな夜半の辛いことよ
語句・すばだてぃてぃ 枕を立てて。源氏物語に「枕をそばたてて、四方(よも)の嵐を聞き給ふに」というのがある。「1.高く聳(そび)え立たせる。高く差し上げる。立てるようにする。」というのが国語辞典にある。・うびじゃす 思い出す。「うびんじゃしゅん」(思い出す)の短縮。・ゆふぁ 夜中。「ゆわ」「ゆふぁん」とも言う。
三、渡海や 隔じゃみてぃん 照る月やふぃとぅち あまん眺みゆら 今日ぬ空や
tukeya hwijamitiN tiru chichi ya hwituchi ‘amaN nagamiyura kiyu nu sura ya
とぅけやふぃじゃみてぃん てぃるちちやふぃとぅち あまんながみゆらきゆぬすらや
◯海を隔てていても 照る月はひとつ あの方も眺めているだろう 今日の空を
語句・とぅけ<とぅけー。「海洋」【沖辞】。いわゆる海。・ふぃじゃみてぃん 隔てていても。<ふぃじゃみゆん。ふぃじゃみいん。隔てる。・ふぃとぅち 文語の「ひとつ」。口語は「てぃーち」・あまん あの方も。「あま」には「あそこ」「あちら」という意味もあるが、ここでは「あのかた」【沖辞】。ちなみにウタでは男から女をさして「あり」、女から男をさして「あま」と使い分けることもある。【沖辞】。
四、柴木植いてぃうかば しばしばとぅいもり 真竹植いてぃうかば いもり忍ば
shibaki 'witi 'ukaba shibashibatu 'imoori mataki 'wiiti 'ukaba 'imoori shinuba
しばき’うぃてぃうかば しばしばいもり またきうぃてぃうかば いもりしぬば
◯柴木を植えておくので たびたびおいでください 真竹を植えておくので いらしてお逢いしましょう
語句・しばき 柴木。「やぶにっけい。種子から油をしぼり、食用・燈用にする。」【沖辞】。ここでは「しばしばとぅいもり」に掛けている。・またき ダイサンチクという熱帯原産の竹。高さは20メートルにもなる。建築資材や物干し竿、また筍は食用になる。首里では「まーたく」と呼ぶ。「またくー」とは「また来い」という意味であり、「またんしぬば」に掛けている。
(コメント)
【ウタの由来】
この歌碑がうるま市の赤野の浜にある。

なぜそこにあるのか。うるま市の伊波家に代々この浜千鳥の一番の歌詞が口承でつたえられてきたからで、その調査を基に元具志川市(現うるま市)が1997年に建立した。

この記事(琉球新報)には、沖縄戦で資料は消失してしまったが「チジュヤーは、アカザンガー下(具志川小学校近く)の田んぼの水管理をしていたころ、赤野浜で鳴く千鳥の声に郷愁感に誘われて歌に詠んだ」と伝えられているという。19世紀半ばの頃だという。
歌碑に刻まれた歌詞は
表には
旅や浜宿り 草の葉と枕寝ても忘ららぬ 我親のおそば
裏には
たびやはまやどぅい くさぬふぁどぅまくら にてぃんわすぃららん わやぬ うすば
とある。
【「ヤドゥイ」とは】
伊波家に代々伝わる事が事実なのかどうか、それはわからない。
ただし、18世紀の初頭、琉球王府内で増える士族を首里から地方に移住させる政策がとられた。平民の部落とは区別された「屋取」(やーどぅい)という部落を形成し農業などを営むようになる。屋取は具志川、北谷、越来という地域に多く作られた。
このウタの「ハマ・ヤドゥイ」がその「屋取」(ヤードゥイ)に当たると受け取るならば伊波家説は信ぴょう性も出てくる。
【多様な歌詞】
野村流と安冨祖流の工工四では歌詞とその表記に若干違いがある。さらに舞踊の地謡で歌われるとまた少し歌詞や囃子が変わったりもする。
野村流 野村流地謡 安冨祖流地謡
◯浜宿い ハマヤドゥリ ハマヤドゥイ ハマヤドゥイ
◯草ぬ葉ぬ クサヌファドゥ クサヌファヌ クサヌファヌ
◯忘ららん ワスィララン ワスィララン ワシララン
◯覚出す ウビジャシュ ウビジャシュ ウビジャス
◯辛さ ツィラサ ツィラサ チラサ
◯隔じゃみてぃ フィザミティ フィザミティ ヒザミティ
◯月 ツィチ ツィチ チチ
◯一ち フィトゥツィ フィトゥツィ ヒトゥチ
歌碑に「草の葉と」と「くさぬふぁどぅ」が併記されていたように、流派によっても歌詞に若干の違いが見られる。「草ぬ葉どぅ枕」(草の葉だけの枕)と、「草ぬ葉ぬ枕」(草の葉の枕)、さらに「草の葉と枕」(草の葉と枕)では意味に少し違いもでてこようが、あまり細かい事は関係ないのかもしれない。
また「月」の士族のよる発音は「ツィチ」であった。「チチ」となるとより平民の発音に近い。士族が平民化していく時代の流れの中で、そういう変化も歌詞の違いに反映しているかもしれない。
【いろいろなチジュヤー】
南洋浜千鳥は、本調子で、中位の手つきで三線を弾く。つまり、ひとさし指が中六を担当し、中指が尺七。小指は八。つまり、沖縄音階たっぷりの曲調になる。まさか、あのブームの島唄は、これを下敷きに?などと疑うくらい似ている。まあ、音楽の世界、似ている曲は百万とあるし、あってもよいと私は思う。著作権のうるさい今日でも、だ。
浜千鳥系と呼ばれる唄はいくつかある。
南洋浜千鳥は本調子。島尻浜千鳥は三下げ。舞踊で有名なのは二揚げと、三線の調子によって曲調を変えるが、歌詞はほとんど同じである。この曲が原型であろう。人気の高いウタにはよくあることだ。
下千鳥(サギチジュヤー)という浮世の不条理を歌うウタもある。これは歌詞は自由型。
【その他の気づき】
1、歌詞の省略がある。八八八六の琉歌の形式にあわせるために、たとえば1番の 「我
親」は「わーうや」だが、「わや」と読ませる。
2番の「夜半ぬ」は同様に「ゆーふぁんぬ」→「ゆふぁぬ」
つまり、おそらく、曲が別にあって、そこにあとから歌詞を流し込んだ形跡ではない
かと推測する。
2、3番では、曲により「照る月」が「てぃるち」「ち」と分断される。
4番でも「しばしばとぅ」が「しばし」「ばとぅ・・」に。
しかし、そのあたりも、歌っていて面白いと感じる。
3、囃子の「やり」は「やれ」とも歌う。
【このブログが本になりました!】
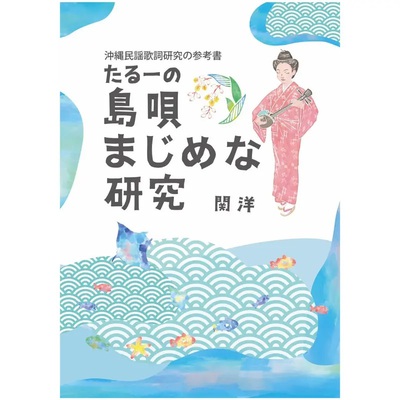
書籍【たるーの島唄まじめな研究】のご購入はこちら
chijyuyaa
◯浜千鳥
語句・ちじゅやー 「千鳥。浜に群れて鳴き飛ぶ小鳥。cizujaaともいう。文語はhama-ciduri」【沖縄語辞典(国立国語研究所編)】(以下【沖辞】と略す)文語では「はまちどぅり」。小鳥は「ちじゅい」という。
一、旅や浜宿い 草ぬ(ヤリ)葉ぬ枕 寝てぃん忘ららん 我親ぬ御側
tabiya hamayadui kusanu (yari)hwaa nu makura nitiN washiraraN wa’uyanu ‘usuba
たびや はまやどぅい くさぬ (やり)ふぁーぬまくら にてぃんわしららん わやぬ ‘うすば
◯旅は浜に宿をし、草の葉の(ヤレは囃子言葉)枕 寝ても忘れられない 私の親のお側
語句・やどぅい 「やどぅゆん」(泊まる)という動詞の活用形ともとれるが、「屋取」(やーどぅい)という「都落ちした士族の部落。都に定職なく都落ちした士族は、平民の村落と離れた所に居を定め、農業を営むようになった。その部落をいう」【沖辞】。すなわち琉球王朝末期に士族が増えすぎたために首里から各地方に士族を移住させ、平民の村落とは区別して農業を営ませた。後の記事に見るようにこの歌詞が実在の屋取部落の士族によって歌われたウタである可能性も高い。・やり 囃子言葉。「やれ」と歌う事もある。・わや 我親(わーうや)の短縮。
※千鳥や 浜居てぃ チュイチュイナ
chizuyaa ya hama wuti chui chui naa
ちじゅやーや はま うぅてぃ ちゅいちゅいなー
◯千鳥は浜に居て チュイチュイ(と鳴いている)
(以下囃子は全て同じため省略する。)
語句・うぅてぃ 居て。存在動詞「うぅん」の活用形。
二、旅宿ぬ寝覚め 枕すばだてぃてぃ 覚出すさ昔 夜半ぬ辛さ
tabiyadu nu nizami makura subadatiti ‘ubizasusa ‘Nkasi yuhwa nu chirasa
たびやどぅぬにざみ まくらすばだてぃてぃ うびじゃすさんかし ゆふぁぬちらさ
◯旅宿で目覚め 枕をかたむけて 思い出すよ昔を こんな夜半の辛いことよ
語句・すばだてぃてぃ 枕を立てて。源氏物語に「枕をそばたてて、四方(よも)の嵐を聞き給ふに」というのがある。「1.高く聳(そび)え立たせる。高く差し上げる。立てるようにする。」というのが国語辞典にある。・うびじゃす 思い出す。「うびんじゃしゅん」(思い出す)の短縮。・ゆふぁ 夜中。「ゆわ」「ゆふぁん」とも言う。
三、渡海や 隔じゃみてぃん 照る月やふぃとぅち あまん眺みゆら 今日ぬ空や
tukeya hwijamitiN tiru chichi ya hwituchi ‘amaN nagamiyura kiyu nu sura ya
とぅけやふぃじゃみてぃん てぃるちちやふぃとぅち あまんながみゆらきゆぬすらや
◯海を隔てていても 照る月はひとつ あの方も眺めているだろう 今日の空を
語句・とぅけ<とぅけー。「海洋」【沖辞】。いわゆる海。・ふぃじゃみてぃん 隔てていても。<ふぃじゃみゆん。ふぃじゃみいん。隔てる。・ふぃとぅち 文語の「ひとつ」。口語は「てぃーち」・あまん あの方も。「あま」には「あそこ」「あちら」という意味もあるが、ここでは「あのかた」【沖辞】。ちなみにウタでは男から女をさして「あり」、女から男をさして「あま」と使い分けることもある。【沖辞】。
四、柴木植いてぃうかば しばしばとぅいもり 真竹植いてぃうかば いもり忍ば
shibaki 'witi 'ukaba shibashibatu 'imoori mataki 'wiiti 'ukaba 'imoori shinuba
しばき’うぃてぃうかば しばしばいもり またきうぃてぃうかば いもりしぬば
◯柴木を植えておくので たびたびおいでください 真竹を植えておくので いらしてお逢いしましょう
語句・しばき 柴木。「やぶにっけい。種子から油をしぼり、食用・燈用にする。」【沖辞】。ここでは「しばしばとぅいもり」に掛けている。・またき ダイサンチクという熱帯原産の竹。高さは20メートルにもなる。建築資材や物干し竿、また筍は食用になる。首里では「まーたく」と呼ぶ。「またくー」とは「また来い」という意味であり、「またんしぬば」に掛けている。
(コメント)
【ウタの由来】
この歌碑がうるま市の赤野の浜にある。

なぜそこにあるのか。うるま市の伊波家に代々この浜千鳥の一番の歌詞が口承でつたえられてきたからで、その調査を基に元具志川市(現うるま市)が1997年に建立した。

この記事(琉球新報)には、沖縄戦で資料は消失してしまったが「チジュヤーは、アカザンガー下(具志川小学校近く)の田んぼの水管理をしていたころ、赤野浜で鳴く千鳥の声に郷愁感に誘われて歌に詠んだ」と伝えられているという。19世紀半ばの頃だという。
歌碑に刻まれた歌詞は
表には
旅や浜宿り 草の葉と枕寝ても忘ららぬ 我親のおそば
裏には
たびやはまやどぅい くさぬふぁどぅまくら にてぃんわすぃららん わやぬ うすば
とある。
【「ヤドゥイ」とは】
伊波家に代々伝わる事が事実なのかどうか、それはわからない。
ただし、18世紀の初頭、琉球王府内で増える士族を首里から地方に移住させる政策がとられた。平民の部落とは区別された「屋取」(やーどぅい)という部落を形成し農業などを営むようになる。屋取は具志川、北谷、越来という地域に多く作られた。
このウタの「ハマ・ヤドゥイ」がその「屋取」(ヤードゥイ)に当たると受け取るならば伊波家説は信ぴょう性も出てくる。
【多様な歌詞】
野村流と安冨祖流の工工四では歌詞とその表記に若干違いがある。さらに舞踊の地謡で歌われるとまた少し歌詞や囃子が変わったりもする。
野村流 野村流地謡 安冨祖流地謡
◯浜宿い ハマヤドゥリ ハマヤドゥイ ハマヤドゥイ
◯草ぬ葉ぬ クサヌファドゥ クサヌファヌ クサヌファヌ
◯忘ららん ワスィララン ワスィララン ワシララン
◯覚出す ウビジャシュ ウビジャシュ ウビジャス
◯辛さ ツィラサ ツィラサ チラサ
◯隔じゃみてぃ フィザミティ フィザミティ ヒザミティ
◯月 ツィチ ツィチ チチ
◯一ち フィトゥツィ フィトゥツィ ヒトゥチ
歌碑に「草の葉と」と「くさぬふぁどぅ」が併記されていたように、流派によっても歌詞に若干の違いが見られる。「草ぬ葉どぅ枕」(草の葉だけの枕)と、「草ぬ葉ぬ枕」(草の葉の枕)、さらに「草の葉と枕」(草の葉と枕)では意味に少し違いもでてこようが、あまり細かい事は関係ないのかもしれない。
また「月」の士族のよる発音は「ツィチ」であった。「チチ」となるとより平民の発音に近い。士族が平民化していく時代の流れの中で、そういう変化も歌詞の違いに反映しているかもしれない。
【いろいろなチジュヤー】
南洋浜千鳥は、本調子で、中位の手つきで三線を弾く。つまり、ひとさし指が中六を担当し、中指が尺七。小指は八。つまり、沖縄音階たっぷりの曲調になる。まさか、あのブームの島唄は、これを下敷きに?などと疑うくらい似ている。まあ、音楽の世界、似ている曲は百万とあるし、あってもよいと私は思う。著作権のうるさい今日でも、だ。
浜千鳥系と呼ばれる唄はいくつかある。
南洋浜千鳥は本調子。島尻浜千鳥は三下げ。舞踊で有名なのは二揚げと、三線の調子によって曲調を変えるが、歌詞はほとんど同じである。この曲が原型であろう。人気の高いウタにはよくあることだ。
下千鳥(サギチジュヤー)という浮世の不条理を歌うウタもある。これは歌詞は自由型。
【その他の気づき】
1、歌詞の省略がある。八八八六の琉歌の形式にあわせるために、たとえば1番の 「我
親」は「わーうや」だが、「わや」と読ませる。
2番の「夜半ぬ」は同様に「ゆーふぁんぬ」→「ゆふぁぬ」
つまり、おそらく、曲が別にあって、そこにあとから歌詞を流し込んだ形跡ではない
かと推測する。
2、3番では、曲により「照る月」が「てぃるち」「ち」と分断される。
4番でも「しばしばとぅ」が「しばし」「ばとぅ・・」に。
しかし、そのあたりも、歌っていて面白いと感じる。
3、囃子の「やり」は「やれ」とも歌う。
【このブログが本になりました!】
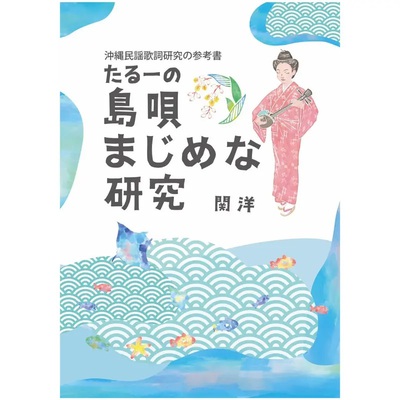
書籍【たるーの島唄まじめな研究】のご購入はこちら
この記事へのコメント
たるーさん 「島唄まじめな研究」のブログ開設おめでとう
水くさいな~~~一番にコメントしたかったのにさ~~
浜千鳥は、子供の頃から聞いている好きな曲のひとつです。
これが、じっくりと歌えるようになるのはいつなのかなあ~
水くさいな~~~一番にコメントしたかったのにさ~~
浜千鳥は、子供の頃から聞いている好きな曲のひとつです。
これが、じっくりと歌えるようになるのはいつなのかなあ~
Posted by MAGI at 2005年11月03日 14:21
引越しをそっとしてたので、知らせるのが遅くなってしまった。すまんですのー。
今日はタネモリおじーとデートであった。
よー二人で、話題もつきないというくらい2時間以上しゃべった。
おやじとおじいがイタリアレストランでケーキ食いながらしゃべっておる光景も異様だわな。
今日はタネモリおじーとデートであった。
よー二人で、話題もつきないというくらい2時間以上しゃべった。
おやじとおじいがイタリアレストランでケーキ食いながらしゃべっておる光景も異様だわな。
Posted by たるー at 2005年11月04日 23:22
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。