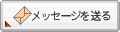2006年11月19日
イラヨイ月夜浜
イラヨイ月夜浜
'いらよい [つきよ]はま
'irayoi [つきよ] hama
語句・いらよい 囃子言葉。
作詞 大島保克 作曲 比嘉栄昇
([]は大和口。なので発音は省略。唄は比嘉栄昇のものを採譜。)
一、唄者達の夜がふけ 踊者達の夜がふけ 太陽のあがるまで舞い遊ば イラヨイマーヌ舞い遊ば'うたしゃたーぬゆるが[ふけ] ぶどぅしゃたーぬゆるが[ふけ] てぃだぬ'あがるまでぃまい'あしば 'いらよいまーぬ まい'あしば
'utashataa nu yuru ga [ふけ] budushataa nu yuru ga [ふけ] tiida nu 'agarumadi mai 'ashiba 'irayoimaanu mai 'ashiba
〇唄者達の夜が更け、踊る者達の夜が更け、太陽があがるまで舞い遊びたい イラヨイマーヌ(囃子言葉 以下略) 舞い遊びたい
語句・ふけ 大和口。 沖縄口では ふき<ふきゆん(更ける)と発音する。・ぶどぅしゃ 八重山口で「踊るもの」。ウチナーグチでは「うどぅいしゃー」
二、月夜浜には花が咲く ゆりのような花が咲く 青く白くもえてよ イラヨイマーヌ花が咲く
[つきよはまにははながさく ゆりのようなはながさく あおくしろくもえてよ]いらよいまーぬ[はながさく]
〇月夜(の)浜には花が咲く ゆりのような花が咲く 青く白くもえてよ イラヨイマーヌ花が咲く
イラヨイマーヌ桃の花 イラヨイマーヌキビの花 イラヨイマーヌ木綿花 イラヨイマーヌ花が咲く
いらよいまーぬ とぅーぬはな いらよいまーぬきびぬはな いらよいまーぬむみんぱな いらよいまーぬ[はながさく]
'irayoimaanu tu nu hana 'irayoimaanu kibinuhana 'irayoimaanu mumiNpana 'irayoimaanu [はながさく]
〇桃の花 キビの花 木綿花 花が咲く
語句・とぅーぬはな 桃の花。比嘉栄昇はCDで、こう発音して歌っている。沖縄口では「むむぬはな」 沖縄口で桃は「とー」と発音する場合がある(「桃原」=とーばる)が、これは「とー」には「平ら」という意味があるからである。「車とーばる」(砂糖車が走る平坦な地面の比喩)「多幸山」) 八重山口ではどうか、私には不明。桃林地という仏教の寺が石垣島にあるが「とーりんじ」と発音するようである。・きび 沖縄口では「うーじ」。八重山では「きび」というのだろうか。「はな」は八重山口では「ぱな」。・むみんぱな 木綿花。沖縄口 「むみんばな」。八重山口では「はな hana」が「ぱな pana」である。
三、月ん灯ん波に受け戻し戻されくぬ浮き世 ヤマト世まで照らし給りイラヨイマーヌ照らし給り
[つき]ん'あかりんなみに[うけ] むどぅしむどぅさり くぬ'うちゆ やまとぅゆまでぃてぃらしたぼり いらよいまーぬてぃらしたぼり
[つき]N 'akariN nami ni [うけ] mudushi mudusari kunu 'uchiyuu yamatu yuu madi tirashi tabori 'irayoimaanu tirashitabori
〇月も灯りも波に受け 戻し戻されてこの浮世 ヤマト(の支配する)時代まで照らしてください。
語句・つきん 月も。「月」は八重山口では「つぃく」(「月のかいしゃ」)。沖縄口では「ちち」。比嘉栄昇は「つき」と発音。次の「ん」は「ぬ」がなまったものか?「月も灯りも」では意味が不明。「月の灯りも」ならば「ちちぬあかりん」。・やまとぅゆー 通常は「薩摩・幕府・日本政府」など本土の権力が沖縄を支配していた時代のことをいう。「あめりかーゆー」というのは戦後のアメリカ政府の支配していた時代。しかし、ここでは「時代」ではなく「世界」という意味が感じられる。
イラヨイマーヌ波にぬれ イラヨイマーヌ流されて イラヨイマーヌ照らされて イラヨイマーヌ流されて
[なみにぬれ][ながされて][てらされて][ながされて]
〇波に濡れ、流されて、照らされて、流されて
イラヨイマーヌ大和ぬ世、イラヨイマーヌ沖縄ぬ世 イラヨイマーヌ宮古ぬ世 イラヨイマーヌ八重山ぬ世 イラヨイマーヌ花が咲く
やまとぅぬゆー うきなーゆー みやくぬゆー やいまぬゆー [はながさく]
yamatu nu yuu ukinaa nu yuu yaima nu yuu miyaku nu yuu
〇ヤマトの世界 沖縄の世界 宮古の世界 八重山の世界に花が咲く
共に八重山は石垣島出身の大島保克(作詞)、比嘉栄昇(BEGIN)(作曲)の作品。
メロディー、歌詞ともにヤマトンチュも魅了する見事な曲。
私個人も好きになり、よく唄わせていただいている。
歌詞は、沖縄口、八重山口に大和口も混ざる混合。
新良幸人のつくるファムレウタなどもそうだが、最近の新唄は、古い唄からの引用に大和口や自分の島(故郷)の言葉を織り交ぜたものが多い。
やはり、ヒットすることを意識し、ヤマトの世界にも受け入れられやすい言葉を使い、メロディーを混ぜて曲が作られているように思える。それも時代の流れだろう。
かつて沖縄民謡の隆盛も、八重山、宮古の民謡のメロディーを沖縄本島に持ってきて、自分たちの歌詞を乗せて盛り上がっている。
古典も、メロディーは八重山、宮古、奄美民謡生まれのものが多い。
そういう「混合」から新しいものが生まれてきたのが沖縄の芸能の強さの秘訣だと思う。
しかし、「島言葉」(しまくとぅば)が混乱していることも事実、それを嘆く人もすくなくない。そういうことも知っておいて、こういう歌も楽しむことは私達、大和人に必要な姿勢ではないだろうか。
【このブログが本になりました!】
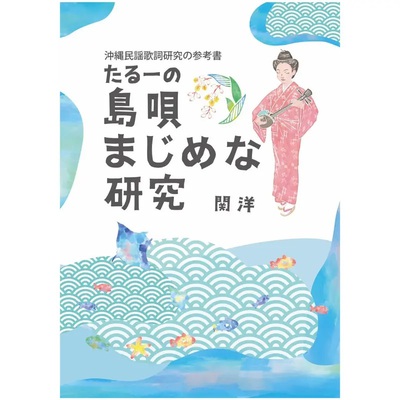
書籍【たるーの島唄まじめな研究】のご購入はこちら
'いらよい [つきよ]はま
'irayoi [つきよ] hama
語句・いらよい 囃子言葉。
作詞 大島保克 作曲 比嘉栄昇
([]は大和口。なので発音は省略。唄は比嘉栄昇のものを採譜。)
一、唄者達の夜がふけ 踊者達の夜がふけ 太陽のあがるまで舞い遊ば イラヨイマーヌ舞い遊ば'うたしゃたーぬゆるが[ふけ] ぶどぅしゃたーぬゆるが[ふけ] てぃだぬ'あがるまでぃまい'あしば 'いらよいまーぬ まい'あしば
'utashataa nu yuru ga [ふけ] budushataa nu yuru ga [ふけ] tiida nu 'agarumadi mai 'ashiba 'irayoimaanu mai 'ashiba
〇唄者達の夜が更け、踊る者達の夜が更け、太陽があがるまで舞い遊びたい イラヨイマーヌ(囃子言葉 以下略) 舞い遊びたい
語句・ふけ 大和口。 沖縄口では ふき<ふきゆん(更ける)と発音する。・ぶどぅしゃ 八重山口で「踊るもの」。ウチナーグチでは「うどぅいしゃー」
二、月夜浜には花が咲く ゆりのような花が咲く 青く白くもえてよ イラヨイマーヌ花が咲く
[つきよはまにははながさく ゆりのようなはながさく あおくしろくもえてよ]いらよいまーぬ[はながさく]
〇月夜(の)浜には花が咲く ゆりのような花が咲く 青く白くもえてよ イラヨイマーヌ花が咲く
イラヨイマーヌ桃の花 イラヨイマーヌキビの花 イラヨイマーヌ木綿花 イラヨイマーヌ花が咲く
いらよいまーぬ とぅーぬはな いらよいまーぬきびぬはな いらよいまーぬむみんぱな いらよいまーぬ[はながさく]
'irayoimaanu tu nu hana 'irayoimaanu kibinuhana 'irayoimaanu mumiNpana 'irayoimaanu [はながさく]
〇桃の花 キビの花 木綿花 花が咲く
語句・とぅーぬはな 桃の花。比嘉栄昇はCDで、こう発音して歌っている。沖縄口では「むむぬはな」 沖縄口で桃は「とー」と発音する場合がある(「桃原」=とーばる)が、これは「とー」には「平ら」という意味があるからである。「車とーばる」(砂糖車が走る平坦な地面の比喩)「多幸山」) 八重山口ではどうか、私には不明。桃林地という仏教の寺が石垣島にあるが「とーりんじ」と発音するようである。・きび 沖縄口では「うーじ」。八重山では「きび」というのだろうか。「はな」は八重山口では「ぱな」。・むみんぱな 木綿花。沖縄口 「むみんばな」。八重山口では「はな hana」が「ぱな pana」である。
三、月ん灯ん波に受け戻し戻されくぬ浮き世 ヤマト世まで照らし給りイラヨイマーヌ照らし給り
[つき]ん'あかりんなみに[うけ] むどぅしむどぅさり くぬ'うちゆ やまとぅゆまでぃてぃらしたぼり いらよいまーぬてぃらしたぼり
[つき]N 'akariN nami ni [うけ] mudushi mudusari kunu 'uchiyuu yamatu yuu madi tirashi tabori 'irayoimaanu tirashitabori
〇月も灯りも波に受け 戻し戻されてこの浮世 ヤマト(の支配する)時代まで照らしてください。
語句・つきん 月も。「月」は八重山口では「つぃく」(「月のかいしゃ」)。沖縄口では「ちち」。比嘉栄昇は「つき」と発音。次の「ん」は「ぬ」がなまったものか?「月も灯りも」では意味が不明。「月の灯りも」ならば「ちちぬあかりん」。・やまとぅゆー 通常は「薩摩・幕府・日本政府」など本土の権力が沖縄を支配していた時代のことをいう。「あめりかーゆー」というのは戦後のアメリカ政府の支配していた時代。しかし、ここでは「時代」ではなく「世界」という意味が感じられる。
イラヨイマーヌ波にぬれ イラヨイマーヌ流されて イラヨイマーヌ照らされて イラヨイマーヌ流されて
[なみにぬれ][ながされて][てらされて][ながされて]
〇波に濡れ、流されて、照らされて、流されて
イラヨイマーヌ大和ぬ世、イラヨイマーヌ沖縄ぬ世 イラヨイマーヌ宮古ぬ世 イラヨイマーヌ八重山ぬ世 イラヨイマーヌ花が咲く
やまとぅぬゆー うきなーゆー みやくぬゆー やいまぬゆー [はながさく]
yamatu nu yuu ukinaa nu yuu yaima nu yuu miyaku nu yuu
〇ヤマトの世界 沖縄の世界 宮古の世界 八重山の世界に花が咲く
共に八重山は石垣島出身の大島保克(作詞)、比嘉栄昇(BEGIN)(作曲)の作品。
メロディー、歌詞ともにヤマトンチュも魅了する見事な曲。
私個人も好きになり、よく唄わせていただいている。
歌詞は、沖縄口、八重山口に大和口も混ざる混合。
新良幸人のつくるファムレウタなどもそうだが、最近の新唄は、古い唄からの引用に大和口や自分の島(故郷)の言葉を織り交ぜたものが多い。
やはり、ヒットすることを意識し、ヤマトの世界にも受け入れられやすい言葉を使い、メロディーを混ぜて曲が作られているように思える。それも時代の流れだろう。
かつて沖縄民謡の隆盛も、八重山、宮古の民謡のメロディーを沖縄本島に持ってきて、自分たちの歌詞を乗せて盛り上がっている。
古典も、メロディーは八重山、宮古、奄美民謡生まれのものが多い。
そういう「混合」から新しいものが生まれてきたのが沖縄の芸能の強さの秘訣だと思う。
しかし、「島言葉」(しまくとぅば)が混乱していることも事実、それを嘆く人もすくなくない。そういうことも知っておいて、こういう歌も楽しむことは私達、大和人に必要な姿勢ではないだろうか。
【このブログが本になりました!】
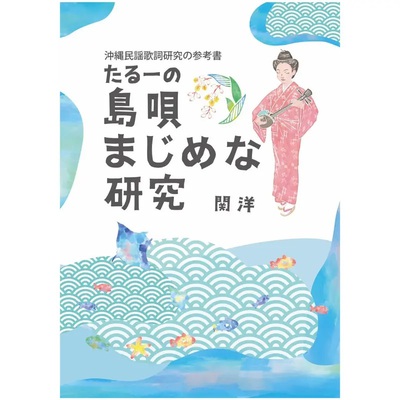
書籍【たるーの島唄まじめな研究】のご購入はこちら
Posted by たる一 at 10:04│Comments(10)
│あ行
この記事へのコメント
この唄、BEGINの中でもかなり上位に来ます。
それくらい僕は好きです。
サビの盛り上がりが最高ですよね。
せきさんはこの唄をよく唄われるんですね。
BEGINの曲で他に唄われるものってありますか?
それくらい僕は好きです。
サビの盛り上がりが最高ですよね。
せきさんはこの唄をよく唄われるんですね。
BEGINの曲で他に唄われるものってありますか?
Posted by kta at 2006年11月20日 12:58
ktaさん
コメントありがとう。
サビ、よくできています。
古い唄と新しい感性の昇華という感じですね。
BEGINの唄では、涙そうそう、おじい自慢、島人の宝などメジャーな唄もその場に応じて歌いますよ。
しかし、このイラヨイ月夜浜はダントツです。
コメントありがとう。
サビ、よくできています。
古い唄と新しい感性の昇華という感じですね。
BEGINの唄では、涙そうそう、おじい自慢、島人の宝などメジャーな唄もその場に応じて歌いますよ。
しかし、このイラヨイ月夜浜はダントツです。
Posted by せきひろし(たるー) at 2006年11月20日 22:03
お久しぶりで~す おはようございます b(^o^)d W(^O^)W
「イラヨイ月夜浜」は大島保克さんの代名詞的作品ですね。
8年前訪沖した時、「仲田幸子芸能館」の仲田正江さんが「この歌、ダイスキ!」と歌ってくれました♪
「イラヨイ月夜浜」は大島保克さんの代名詞的作品ですね。
8年前訪沖した時、「仲田幸子芸能館」の仲田正江さんが「この歌、ダイスキ!」と歌ってくれました♪
Posted by 金魚小 at 2006年11月23日 09:52
金魚小さん おはようございます。
それくらい、とても魅力のある歌だと思いますね。
すぐに消えていく新唄も多いなか、もしかしたら
長く残る唄かもしれませんね。
それくらい、とても魅力のある歌だと思いますね。
すぐに消えていく新唄も多いなか、もしかしたら
長く残る唄かもしれませんね。
Posted by せきひろし(たるー) at 2006年11月24日 05:51
はじめまして。
「きびの花」ですが、サトウキビではなく、「黍」ではないでしょうか?
「あわ」や「ひえ」と並ぶイネ科の植物です。
西表を旅したとき、きびの畑を見たことを思い出しました。
「きびの花」ですが、サトウキビではなく、「黍」ではないでしょうか?
「あわ」や「ひえ」と並ぶイネ科の植物です。
西表を旅したとき、きびの畑を見たことを思い出しました。
Posted by よう at 2007年07月25日 21:04
ようさん
はじめまして
黍、なのかさとうきびなのか私には知るよしもありませんが
たしかにそういう可能性もありますね。
気が付きませんでした。
石垣島では特産で「もちきび」というものがあるのを
八重山の新聞ではじめて知りました。
でも「さとうきび」も「キビ」と書いた記事も多かったです。
黍の花は見たことがありません。
どんな花なのでしょうか。
さとうきびの花は、風情があり、歌われることもあります。
さてどちらなのでしょうか。
いいご指摘ありがとうございます。
はじめまして
黍、なのかさとうきびなのか私には知るよしもありませんが
たしかにそういう可能性もありますね。
気が付きませんでした。
石垣島では特産で「もちきび」というものがあるのを
八重山の新聞ではじめて知りました。
でも「さとうきび」も「キビ」と書いた記事も多かったです。
黍の花は見たことがありません。
どんな花なのでしょうか。
さとうきびの花は、風情があり、歌われることもあります。
さてどちらなのでしょうか。
いいご指摘ありがとうございます。
Posted by 関洋(せきひろし) at 2007年07月27日 06:04
at 2007年07月27日 06:04
 at 2007年07月27日 06:04
at 2007年07月27日 06:04もちきびの花はかなり地味でした(笑
月夜に照らされ光る穂が風に揺れる姿を想像すると、確かにサトウキビの花の方が、風情があって歌には合いそうですね。
三線を始めたばかりなのですが、とても好きな歌です。
新たなイメージが膨らんで、さらに好きになりそうです。
ありがとうございました。
月夜に照らされ光る穂が風に揺れる姿を想像すると、確かにサトウキビの花の方が、風情があって歌には合いそうですね。
三線を始めたばかりなのですが、とても好きな歌です。
新たなイメージが膨らんで、さらに好きになりそうです。
ありがとうございました。
Posted by よう at 2007年07月29日 23:26
ただ、想像で歌の意味を決めるのは避けたい
私です。
作詞の大島さんの気持ちまではわかりません。
しかし、矛盾するようですが、
想像は自由です。
それゆえに歌は生きていきます。
いいご指摘ありがとう。
私です。
作詞の大島さんの気持ちまではわかりません。
しかし、矛盾するようですが、
想像は自由です。
それゆえに歌は生きていきます。
いいご指摘ありがとう。
Posted by 関洋 at 2007年07月31日 22:52
お久しぶりです。三線を弾きつつ最近、息子に付き合ってエイサーを始めました。体はかなりきついんですが、なかなか面白いです。三線とエイサー、同時進行で続けていければと思ってます。沖縄から離れて沖縄にハマっている自分がなんか滑稽に感じます。不思議なもんです。すごい勉強になるのでまたお邪魔するかと思います。
Posted by kikibrutus at 2010年11月27日 21:24
kikibrutusさん いらっしゃいませ。
三線とエイサーにとりくんでらっしゃるんですね。
しかも息子さんと一緒に。すばらしいことですね!
このブログがお役にたてれば。よろしくお願いします。
記事、すこし加筆、修正しました。
こちらもよろしく。
三線とエイサーにとりくんでらっしゃるんですね。
しかも息子さんと一緒に。すばらしいことですね!
このブログがお役にたてれば。よろしくお願いします。
記事、すこし加筆、修正しました。
こちらもよろしく。
Posted by たる一 at 2010年11月28日 07:55
at 2010年11月28日 07:55
 at 2010年11月28日 07:55
at 2010年11月28日 07:55※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。