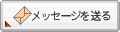2014年12月12日
あやぐ節 (本島民謡)
あやぐ節
あやぐぶし
'ayagu bushi
語句・あやぐぶし または「宮古ぬあやぐ」(みゃーくぬあやぐ)とも呼ばれる。「あやぐ」は「美しい言葉」つまり「うた」。「[綾言〔あやごと〕美しく妙なる詞]あやぐ〔宮古島の伝統歌謡〕aaguとも;Toogani 'ayaguなど」【琉球語辞典】(半田一郎著)。だから「あやぐの歌」と訳すと「歌の歌」となりおかしい事になる。
歌 知名定男 (「島唄百景 Disk 1 祝儀曲・舞踊曲」 より筆者聴き取り)
一、道ぬ美らさや 仮屋ぬ前 あやぐぬ美らさや 宮古ぬあやぐ イーラヨー マーヌヨー 宮古ぬあやぐ エンヤラースーリ
みちぬちゅらさや かいやぬめー あやぐぬちゅらさや みゃーくぬあやぐ (いらよーまーぬよー)みゃーくぬあやぐ(えんやらーすーり)
michi nu churasa ya kaiya nu mee 'ayagu nu churasa ya myaaku nu 'ayagu ('ira yoo maa nu yoo )myaaku nu 'ayagu (eNyara suuri)
《()は囃子言葉。以下省略する》
◯道が美しいのは仮屋の前 歌が美しいのは宮古の歌
語句・ちゅらさ 「美しい。きれいである。また、清潔である。」【沖縄語辞典(国立国語研究所編)】(以下【沖辞】と略す)。「清らさ」(きよらさ)が変化して出来た言葉である。・かいや 「在番奉行の役所」【沖辞】。下に場所と詳しい解説がある。
二、手拭ぬ長さや まち長さ 庭に植てるガジマル木ぬ 下葉ぬ長さ
てぃーさじぬながさや まちなげさ にわにうぃーてるがじまるぎぬ しちゃふぁぬながさ
tiisaji nu nagasa ya machi nageesa niwa ni 'wiiteeru gajimaru gii nu shichahwaa nu nagasa
◯手ぬぐいの長さは待ち長さ(と同じ)。庭に生えているガジュマル木の下葉(気根)の長さのようだ
語句・てぃーさじ 手ぬぐい。昔は女性が織って好きな男性に渡した「恋の証」。・まち 待つ。「なぎ」(長さ)と歌ったものもよくある。・うぃーてーる 生えている。<うぃーゆん。①植える。②「成長する。発育する。大きくなる」【沖辞】。ここでは②であろう。・しちゃふぁー 下の葉、つまりガジュマルの枝や幹から下にのびる気根(ヒゲのような根)だろう。「しちゃばー」という歌詞もある。
三、うばが家とぅ ばんたが家とぅ隣やりば 今日ん見り 明日ん見り かなし里よ
うばがやーとぅ ばんたがやーとぅ とぅないやりば ちゅーんみり あちゃーんみり かなしさとぅよ
'uba ga yaa tu baNta ga yaa tu tunai yariba chuuN miri 'achaaN miri kanashi satu yoo
◯あなたの家と私の家が隣どうしならば 今日も見えて(会って)明日も見えるのに 愛しい貴方よ
語句・うば お前、あなた。<「っゔぁ」。宮古語、ミャークフツのウチナーグチ表現。発音記号で「vva」と表される。「図説 琉球語辞典」(中本正智著)によると、宮古語で「 あなた」ないし「君」に当たる語句は「ゥ゛ゥ゛アー」vvaaとも記されている。・ばんた 私達。宮古語、ミャークフツで「私達」。・が の。・かなし 愛しい。
四、宮古から 船出じゃち 渡地ぬ前ぬ浜に しぐはいくまち
みゃーくからふにんじゃち わたんじぬ めーぬはまに しぐはいくまち
myaaku kara huni 'Njachi wataNji nu mee nu hama ni shigu hai kumachi
◯宮古島から船を出し 渡船場の前の浜にすぐ走りそこに居続けて
語句・んじゃち 出して。<んじゆん。出る。・わたんじ 「①渡し場。渡船場。②[渡地]那覇にあった遊郭の名」 【沖辞】。ここでは那覇三大遊郭の一つの「渡地」というより、一般的な渡船場のことだろう。・しぐ すぐ。・はい すぐに。はゆん(走る)の意味か、はい(早い)の意味か曖昧だが、「すぐに」と訳した。・くまち 籠って。居続けて。<くまゆん。籠る。居続ける。
五、沖縄いもらば 沖縄ぬ主 うてぃんだぬ水に あみさますなよ ばんたがかじゃぬ 美童匂いぬ うてぃがすゆら エンヤラースリ
うちなーいもらば うちなーぬしゅ ウ亭だぬみじに あみさますなよー ばんたがかじゃぬ みやらびにういぬ うてぃがすゆら
'uchinaa 'imooraba 'uchinaa nu shu 'utiNda nu miji ni 'amisamasuna yoo
◯沖縄に行かれましたら沖縄の主 落平の水で行水をしてさまないでね。私たちの匂いが、娘の匂いが落ちるかもしれないから。
語句・ ・あみさますな 浴びてさますな。あみゆん。「水浴する。水浴びをする。行水する。」【沖辞】。+ さますな。<さましゅん。覚ます。冷ます。酔いをさます。の否定命令。・かじゃ 「におい。niwiともいう。」・みやらび 「娘。おとめ。『めわらべ』に対応する。農村の未婚の娘をいう。」【沖辞】。「美童」は当て字。「み」は「女」の意味。・うてぃがすゆら 落ちるのではないか。「が」は「疑わしさを表す文に用いて、文の疑わしい部分につく。あとを推量の形(aで終わる)で結ぶ。」【沖辞】。
六、なかんガラシぬ 声聞きば 生りらん先からぬ 縁がやたら
なかんがらしぬ くいちきば んまりらんさちからぬ いんがやたら
nakaN garashi nu kui chikiba 'NmariraN sachi kara nu yiN ga yatara
◯鳴かないカラスの声を聞いたので あなたとは生まれる前からの縁があったのでしょうか
語句・がらし 「からす。凶鳥とされ、夕方家の上を鳴いて飛ぶのを見ると、iikutu katari(よいことを語れ)と呪文をとなえる」【沖辞】。・いんがやたら 縁であったのか。「縁」(いん、ゐん、yiN, 声門破裂音無し)は発音に注意し「犬」(いん、'iN、声門破裂音有り。)と区別する。
「宮古のあやぐ」とも呼ばれる。
ここではCDのタイトルに従い「あやぐ節」とした。
宮古島の民謡ではなく、本島民謡として歌われている。
エイサーの地謡曲としても歌われることが多い。
宮古民謡の工工四にもすこし違う歌詞で載っているものもあるので
そちらはまた別に取り上げたい。
【歌の背景】
「沖縄ぬ主」つまり沖縄から来た役人または船員の男性と、宮古島の「みやらび」(娘)たちとの熱い恋の思いを歌ったものである。
「島うた紀行」(第三集 仲宗根幸市編著)によると
「仲毛芝居の頃名優玉城盛重が『あやぐ』という男女の群舞を創作した。」
とある。
この玉城盛重は、いわゆる琉球舞踊の最大流派「玉城流」の祖で、
玉城盛重(たまぐすくせいじゅう)
《明治元年(1868~1945) 首里赤平生まれ。17歳で芝居に入り、後に名優となる。最後の御冠船踊りをつとめた師匠たちから組踊や舞踊を習い、古典の正統的な継承者であると同時に、雑踊りの創作に多くの功績を残した。作品には、「花風」「むんじゅる」「加那ヨー」「あやぐ」「松竹梅」などがある。》
Weblio辞書
さて、この「あやぐ節」は「トーガニアヤグ」をヒントにしてつくられたと「島うた紀行」にも書かれている。
それを証明するのは困難である、曲がどれだけ似た音階でできているかを見ることにしよう。
沖縄民謡、宮古民謡、八重山民謡には
【沖縄音階】;ドミファソシ(レとラが無い)の音で構成されたもの。
【律音階】;ドレファソラ(ミとシがない)。
そしてそれが混合されたもの、
また大和の民謡音階のものもある。
例えば、沖縄音階100パーセントの曲(遊びションガネ、だんじゅかりゆし、など)もあれば、
ほぼ沖縄音階でできているが、時々「レ」などの音が入り個性的な曲(アッチャメー小など)になっているものもある。
「宮古民謡工工四」(與儀栄巧編)で「トーガニアヤグ」の三線のツボ(ツィブドゥクル)を調べると
四を(ド)として、中(ミ)、工(ファ)、五(ソ)、七(シ)、八(ド)
一個だけ例外として、上(レ)が入っている。
工工四に表示されたツボ数66個に対し1個が例外。1.5%。
音階から見ると「トーガニアヤグ」は宮古民謡で数少ないほぼ沖縄音階の曲である。
では「あやぐ節」はどうか。
同様にツボを見ると、上が5個入っている。
ツボ数100に対し例外が5個。5%。
音階を見るとトーガニアヤグもあやぐ節もほぼ沖縄音階でできた曲だといえる。
さらに、歌持ち(前奏)だけを見てみよう。
一見違う曲のように聞こえるが
(トーガニアヤグ 中 工七`五 七 四 五七`四
(あやぐ節) 四 上 工 中 工 五`七 四 五七`四
後半の《五 七 四 五七`四》が同じである。
音階、歌持ちにおいて二つの曲はよく似た曲であるということは言える。
ちなみに、沖縄本島の「ナークニー」が「トーガニアヤグ」からきているという説も、音階からみると説得力が出てくる。
ナークニーを代表する曲の一つ、「本部ナークニー」を見ると、
曲調として「二つの山」があって
《七、八》という部分が二箇所あり、歌もここが一番高くなる。
「トーガニアヤグ」では《八◯八》が二箇所、
同様に歌も一番高い部分である。
「あやぐ節」では《七四八四八》、《七四八四七》という部分が出てくる。
曲の構成を見ても、よく似た作りをしている。
(もっとも、一節が上句、下句でできているから二つの山があるという曲は少なくない)
そして「あやぐ節」が本島の伝統芸能エイサーの曲として人気が高い要因のひとつに
沖縄音階の濃さもあるのかもしれない。
【仮屋ぬ前】
一番で「道ぬ美らさや 仮屋ぬ前 」と歌われている「仮屋」とは、ここだといわれている。

(Google MAPより)
那覇港のすぐ近くにある。
薩摩藩在番奉行所跡 《那覇市西1ー2ー16》
そこには説明板がある。


(2014年10月筆者撮影)
そこにはこう書かれている。
《在藩仮屋、大仮屋ともいう。1609年の島津侵入の後薩摩藩が出先機関として1628年に設置した。以来1872年までの250年間、琉球支配の拠点となっていた。在番奉行や附役など約20人が常勤し、薩琉間の公務の処理や貿易の管理に当たった。1872年の琉球藩設置後、外務省ついで内務省出張所となり、1879年沖縄県設置(廃藩置県)で仮県庁、1881年から県庁となって1920年に泉崎(現在地)へ移転するまで県政の中心となっていた。
奉行所の前は(道の美らさや仮屋ぬ前」と唄われ、那覇四町の大綱引きもこの通りで行われた。掲げた「那覇綱引き図」の中央が奉行所で見物する役人が書かれている。》
【落平の水】
五番で、
《沖縄いもらば 沖縄ぬ主 うてぃんだぬ水に あみさますなよ ばんたがかじゃぬ 美童匂いぬ うてぃがすゆら 》
と歌われている「落平ぬ水」は、現在も那覇市、奥武山公園の西側の山下町大通りに面した斜面の下にある樋川跡である。



そこにある説明板にはこう書かれている。
《 那覇港湾内の奥武山(おうのやま)に向かい合う小禄(おろく)の垣花(かきのはな)にあった樋川(ヒージャー)跡。樋川とは、丘陵の岩間から流れ落ちる湧水を、樋を設けて取水する井泉のこと。
落平は崖の中腹から流れ出て、小滝のように崖下の漫湖(まんこ)の水面に注いでいた。また、落平とその背後の丘陵の松林は、漢詩や琉歌で詠まれるなど那覇の名勝で、楊文鳳(ようぶんほう)(嘉味田親雲上光祥(かみたペーチンこうしょう))は、「落平瀑布(ばくふ)」と題する漢詩を詠んでいる。
那覇港に出入りする船は、朝から夕方まで落平に参まり、取水のため、先を争って口論が絶えなかったという。中国からの冊封使(さっぽうし)一行の来琉を控え、落平を調べると、樋が壊れ、水量が減っていたため、泉崎村(いずみざきむら)の長廻筑登之親(ながさくチクドゥンペーチン)雲上等36人の寄付によって、1807年に落平の樋を修理し、さらに60間(約108m)程東に、新しい樋を設け、新旧2本の樋で給水に供したという(「落平樋碑記(ひひき)」)。
浮島(うきしま)と呼ばれた那覇は、周りを海に囲まれているため、井戸水は塩分が多く、飲料には適さなかったという。
1879年(明治12)の沖縄県設置(琉球処分)後、県庁所在地として人口が増加した那覇では、水問題が一層深刻となっていた。そのため、大きな水桶2 ~ 3個に注いだ落平の水を伝馬船(てんません)で那覇に運び、それを女性がてんびん棒にかついで売り歩く水商売が繁盛したという。明治期以来、水道敷設計画は何度も持ち上がっていたが、1933年(昭和8)に至って念願の水道が敷かれ、水道普及により、水商売も姿を消していった。
終戦後、米軍の軍港整備にともない、那覇港南岸の垣花が敷き直されたが、そこから出た土砂や、那覇港浚渫(しゅんせつ)の土砂を用いて、1957年(昭和32)頃、落平と奥武山の間約4,000坪が埋め立てられ、陸続きとなった。水が湧き出る落平の岩肌は残されたものの、一帯は宅地化が進んだため、落平の水量も減少した。現在では、岩肌からしみ出る程度となっており、1807年に新たに造られた樋川は、拝所となっている。》
落平の水が現在ではわずかな水量らしいが、昔はかなりの水量があったようである。
「琉球交易港図屏風」(浦添市美術館所蔵)には、このウティンダが二基あって、そこから水を汲む様子が描かれている。

▲図屏風の全体。

▲ウティンダ。
作者も不明だが、描かれた年代は1830年頃から40年代と推測されている。
あやぐぶし
'ayagu bushi
語句・あやぐぶし または「宮古ぬあやぐ」(みゃーくぬあやぐ)とも呼ばれる。「あやぐ」は「美しい言葉」つまり「うた」。「[綾言〔あやごと〕美しく妙なる詞]あやぐ〔宮古島の伝統歌謡〕aaguとも;Toogani 'ayaguなど」【琉球語辞典】(半田一郎著)。だから「あやぐの歌」と訳すと「歌の歌」となりおかしい事になる。
歌 知名定男 (「島唄百景 Disk 1 祝儀曲・舞踊曲」 より筆者聴き取り)
一、道ぬ美らさや 仮屋ぬ前 あやぐぬ美らさや 宮古ぬあやぐ イーラヨー マーヌヨー 宮古ぬあやぐ エンヤラースーリ
みちぬちゅらさや かいやぬめー あやぐぬちゅらさや みゃーくぬあやぐ (いらよーまーぬよー)みゃーくぬあやぐ(えんやらーすーり)
michi nu churasa ya kaiya nu mee 'ayagu nu churasa ya myaaku nu 'ayagu ('ira yoo maa nu yoo )myaaku nu 'ayagu (eNyara suuri)
《()は囃子言葉。以下省略する》
◯道が美しいのは仮屋の前 歌が美しいのは宮古の歌
語句・ちゅらさ 「美しい。きれいである。また、清潔である。」【沖縄語辞典(国立国語研究所編)】(以下【沖辞】と略す)。「清らさ」(きよらさ)が変化して出来た言葉である。・かいや 「在番奉行の役所」【沖辞】。下に場所と詳しい解説がある。
二、手拭ぬ長さや まち長さ 庭に植てるガジマル木ぬ 下葉ぬ長さ
てぃーさじぬながさや まちなげさ にわにうぃーてるがじまるぎぬ しちゃふぁぬながさ
tiisaji nu nagasa ya machi nageesa niwa ni 'wiiteeru gajimaru gii nu shichahwaa nu nagasa
◯手ぬぐいの長さは待ち長さ(と同じ)。庭に生えているガジュマル木の下葉(気根)の長さのようだ
語句・てぃーさじ 手ぬぐい。昔は女性が織って好きな男性に渡した「恋の証」。・まち 待つ。「なぎ」(長さ)と歌ったものもよくある。・うぃーてーる 生えている。<うぃーゆん。①植える。②「成長する。発育する。大きくなる」【沖辞】。ここでは②であろう。・しちゃふぁー 下の葉、つまりガジュマルの枝や幹から下にのびる気根(ヒゲのような根)だろう。「しちゃばー」という歌詞もある。
三、うばが家とぅ ばんたが家とぅ隣やりば 今日ん見り 明日ん見り かなし里よ
うばがやーとぅ ばんたがやーとぅ とぅないやりば ちゅーんみり あちゃーんみり かなしさとぅよ
'uba ga yaa tu baNta ga yaa tu tunai yariba chuuN miri 'achaaN miri kanashi satu yoo
◯あなたの家と私の家が隣どうしならば 今日も見えて(会って)明日も見えるのに 愛しい貴方よ
語句・うば お前、あなた。<「っゔぁ」。宮古語、ミャークフツのウチナーグチ表現。発音記号で「vva」と表される。「図説 琉球語辞典」(中本正智著)によると、宮古語で「 あなた」ないし「君」に当たる語句は「ゥ゛ゥ゛アー」vvaaとも記されている。・ばんた 私達。宮古語、ミャークフツで「私達」。・が の。・かなし 愛しい。
四、宮古から 船出じゃち 渡地ぬ前ぬ浜に しぐはいくまち
みゃーくからふにんじゃち わたんじぬ めーぬはまに しぐはいくまち
myaaku kara huni 'Njachi wataNji nu mee nu hama ni shigu hai kumachi
◯宮古島から船を出し 渡船場の前の浜にすぐ走りそこに居続けて
語句・んじゃち 出して。<んじゆん。出る。・わたんじ 「①渡し場。渡船場。②[渡地]那覇にあった遊郭の名」 【沖辞】。ここでは那覇三大遊郭の一つの「渡地」というより、一般的な渡船場のことだろう。・しぐ すぐ。・はい すぐに。はゆん(走る)の意味か、はい(早い)の意味か曖昧だが、「すぐに」と訳した。・くまち 籠って。居続けて。<くまゆん。籠る。居続ける。
五、沖縄いもらば 沖縄ぬ主 うてぃんだぬ水に あみさますなよ ばんたがかじゃぬ 美童匂いぬ うてぃがすゆら エンヤラースリ
うちなーいもらば うちなーぬしゅ ウ亭だぬみじに あみさますなよー ばんたがかじゃぬ みやらびにういぬ うてぃがすゆら
'uchinaa 'imooraba 'uchinaa nu shu 'utiNda nu miji ni 'amisamasuna yoo
◯沖縄に行かれましたら沖縄の主 落平の水で行水をしてさまないでね。私たちの匂いが、娘の匂いが落ちるかもしれないから。
語句・ ・あみさますな 浴びてさますな。あみゆん。「水浴する。水浴びをする。行水する。」【沖辞】。+ さますな。<さましゅん。覚ます。冷ます。酔いをさます。の否定命令。・かじゃ 「におい。niwiともいう。」・みやらび 「娘。おとめ。『めわらべ』に対応する。農村の未婚の娘をいう。」【沖辞】。「美童」は当て字。「み」は「女」の意味。・うてぃがすゆら 落ちるのではないか。「が」は「疑わしさを表す文に用いて、文の疑わしい部分につく。あとを推量の形(aで終わる)で結ぶ。」【沖辞】。
六、なかんガラシぬ 声聞きば 生りらん先からぬ 縁がやたら
なかんがらしぬ くいちきば んまりらんさちからぬ いんがやたら
nakaN garashi nu kui chikiba 'NmariraN sachi kara nu yiN ga yatara
◯鳴かないカラスの声を聞いたので あなたとは生まれる前からの縁があったのでしょうか
語句・がらし 「からす。凶鳥とされ、夕方家の上を鳴いて飛ぶのを見ると、iikutu katari(よいことを語れ)と呪文をとなえる」【沖辞】。・いんがやたら 縁であったのか。「縁」(いん、ゐん、yiN, 声門破裂音無し)は発音に注意し「犬」(いん、'iN、声門破裂音有り。)と区別する。
「宮古のあやぐ」とも呼ばれる。
ここではCDのタイトルに従い「あやぐ節」とした。
宮古島の民謡ではなく、本島民謡として歌われている。
エイサーの地謡曲としても歌われることが多い。
宮古民謡の工工四にもすこし違う歌詞で載っているものもあるので
そちらはまた別に取り上げたい。
【歌の背景】
「沖縄ぬ主」つまり沖縄から来た役人または船員の男性と、宮古島の「みやらび」(娘)たちとの熱い恋の思いを歌ったものである。
「島うた紀行」(第三集 仲宗根幸市編著)によると
「仲毛芝居の頃名優玉城盛重が『あやぐ』という男女の群舞を創作した。」
とある。
この玉城盛重は、いわゆる琉球舞踊の最大流派「玉城流」の祖で、
玉城盛重(たまぐすくせいじゅう)
《明治元年(1868~1945) 首里赤平生まれ。17歳で芝居に入り、後に名優となる。最後の御冠船踊りをつとめた師匠たちから組踊や舞踊を習い、古典の正統的な継承者であると同時に、雑踊りの創作に多くの功績を残した。作品には、「花風」「むんじゅる」「加那ヨー」「あやぐ」「松竹梅」などがある。》
Weblio辞書
さて、この「あやぐ節」は「トーガニアヤグ」をヒントにしてつくられたと「島うた紀行」にも書かれている。
それを証明するのは困難である、曲がどれだけ似た音階でできているかを見ることにしよう。
沖縄民謡、宮古民謡、八重山民謡には
【沖縄音階】;ドミファソシ(レとラが無い)の音で構成されたもの。
【律音階】;ドレファソラ(ミとシがない)。
そしてそれが混合されたもの、
また大和の民謡音階のものもある。
例えば、沖縄音階100パーセントの曲(遊びションガネ、だんじゅかりゆし、など)もあれば、
ほぼ沖縄音階でできているが、時々「レ」などの音が入り個性的な曲(アッチャメー小など)になっているものもある。
「宮古民謡工工四」(與儀栄巧編)で「トーガニアヤグ」の三線のツボ(ツィブドゥクル)を調べると
四を(ド)として、中(ミ)、工(ファ)、五(ソ)、七(シ)、八(ド)
一個だけ例外として、上(レ)が入っている。
工工四に表示されたツボ数66個に対し1個が例外。1.5%。
音階から見ると「トーガニアヤグ」は宮古民謡で数少ないほぼ沖縄音階の曲である。
では「あやぐ節」はどうか。
同様にツボを見ると、上が5個入っている。
ツボ数100に対し例外が5個。5%。
音階を見るとトーガニアヤグもあやぐ節もほぼ沖縄音階でできた曲だといえる。
さらに、歌持ち(前奏)だけを見てみよう。
一見違う曲のように聞こえるが
(トーガニアヤグ 中 工七`五 七 四 五七`四
(あやぐ節) 四 上 工 中 工 五`七 四 五七`四
後半の《五 七 四 五七`四》が同じである。
音階、歌持ちにおいて二つの曲はよく似た曲であるということは言える。
ちなみに、沖縄本島の「ナークニー」が「トーガニアヤグ」からきているという説も、音階からみると説得力が出てくる。
ナークニーを代表する曲の一つ、「本部ナークニー」を見ると、
曲調として「二つの山」があって
《七、八》という部分が二箇所あり、歌もここが一番高くなる。
「トーガニアヤグ」では《八◯八》が二箇所、
同様に歌も一番高い部分である。
「あやぐ節」では《七四八四八》、《七四八四七》という部分が出てくる。
曲の構成を見ても、よく似た作りをしている。
(もっとも、一節が上句、下句でできているから二つの山があるという曲は少なくない)
そして「あやぐ節」が本島の伝統芸能エイサーの曲として人気が高い要因のひとつに
沖縄音階の濃さもあるのかもしれない。
【仮屋ぬ前】
一番で「道ぬ美らさや 仮屋ぬ前 」と歌われている「仮屋」とは、ここだといわれている。

(Google MAPより)
那覇港のすぐ近くにある。
薩摩藩在番奉行所跡 《那覇市西1ー2ー16》
そこには説明板がある。


(2014年10月筆者撮影)
そこにはこう書かれている。
《在藩仮屋、大仮屋ともいう。1609年の島津侵入の後薩摩藩が出先機関として1628年に設置した。以来1872年までの250年間、琉球支配の拠点となっていた。在番奉行や附役など約20人が常勤し、薩琉間の公務の処理や貿易の管理に当たった。1872年の琉球藩設置後、外務省ついで内務省出張所となり、1879年沖縄県設置(廃藩置県)で仮県庁、1881年から県庁となって1920年に泉崎(現在地)へ移転するまで県政の中心となっていた。
奉行所の前は(道の美らさや仮屋ぬ前」と唄われ、那覇四町の大綱引きもこの通りで行われた。掲げた「那覇綱引き図」の中央が奉行所で見物する役人が書かれている。》
【落平の水】
五番で、
《沖縄いもらば 沖縄ぬ主 うてぃんだぬ水に あみさますなよ ばんたがかじゃぬ 美童匂いぬ うてぃがすゆら 》
と歌われている「落平ぬ水」は、現在も那覇市、奥武山公園の西側の山下町大通りに面した斜面の下にある樋川跡である。



そこにある説明板にはこう書かれている。
《 那覇港湾内の奥武山(おうのやま)に向かい合う小禄(おろく)の垣花(かきのはな)にあった樋川(ヒージャー)跡。樋川とは、丘陵の岩間から流れ落ちる湧水を、樋を設けて取水する井泉のこと。
落平は崖の中腹から流れ出て、小滝のように崖下の漫湖(まんこ)の水面に注いでいた。また、落平とその背後の丘陵の松林は、漢詩や琉歌で詠まれるなど那覇の名勝で、楊文鳳(ようぶんほう)(嘉味田親雲上光祥(かみたペーチンこうしょう))は、「落平瀑布(ばくふ)」と題する漢詩を詠んでいる。
那覇港に出入りする船は、朝から夕方まで落平に参まり、取水のため、先を争って口論が絶えなかったという。中国からの冊封使(さっぽうし)一行の来琉を控え、落平を調べると、樋が壊れ、水量が減っていたため、泉崎村(いずみざきむら)の長廻筑登之親(ながさくチクドゥンペーチン)雲上等36人の寄付によって、1807年に落平の樋を修理し、さらに60間(約108m)程東に、新しい樋を設け、新旧2本の樋で給水に供したという(「落平樋碑記(ひひき)」)。
浮島(うきしま)と呼ばれた那覇は、周りを海に囲まれているため、井戸水は塩分が多く、飲料には適さなかったという。
1879年(明治12)の沖縄県設置(琉球処分)後、県庁所在地として人口が増加した那覇では、水問題が一層深刻となっていた。そのため、大きな水桶2 ~ 3個に注いだ落平の水を伝馬船(てんません)で那覇に運び、それを女性がてんびん棒にかついで売り歩く水商売が繁盛したという。明治期以来、水道敷設計画は何度も持ち上がっていたが、1933年(昭和8)に至って念願の水道が敷かれ、水道普及により、水商売も姿を消していった。
終戦後、米軍の軍港整備にともない、那覇港南岸の垣花が敷き直されたが、そこから出た土砂や、那覇港浚渫(しゅんせつ)の土砂を用いて、1957年(昭和32)頃、落平と奥武山の間約4,000坪が埋め立てられ、陸続きとなった。水が湧き出る落平の岩肌は残されたものの、一帯は宅地化が進んだため、落平の水量も減少した。現在では、岩肌からしみ出る程度となっており、1807年に新たに造られた樋川は、拝所となっている。》
落平の水が現在ではわずかな水量らしいが、昔はかなりの水量があったようである。
「琉球交易港図屏風」(浦添市美術館所蔵)には、このウティンダが二基あって、そこから水を汲む様子が描かれている。

▲図屏風の全体。

▲ウティンダ。
作者も不明だが、描かれた年代は1830年頃から40年代と推測されている。
Posted by たる一 at 11:36│Comments(2)
この記事へのコメント
わたしが仮屋ぬ前を見つけたフェイスブックの記事にたるーさんが反応してから、こんなにいろいろお調べになったんですねー!読んで楽しい!!いつも勉強させていただいてます。ありがとうございます(*゚▽゚*) 落平にもしまだ行ってないようでしたら行かれるときわたしも同行させてください♪♪
Posted by KIKO at 2015年03月04日 00:13
あっと言う間でしたね。
KIKOさんが、紹介して下さって、前から気になっていた問題がだんだん繋がってくるようになりました。
あやぐ節、宮古島の歌謡の数々と、本島、八重山の歌謡との関係、本島のナークニーへの影響など、いっぱい考えるきっかけになりました。
ありがとうございます!
落平、次回訪沖時には行きたいと思いますので、その時はよろしくお願いしますね。
KIKOさんが、紹介して下さって、前から気になっていた問題がだんだん繋がってくるようになりました。
あやぐ節、宮古島の歌謡の数々と、本島、八重山の歌謡との関係、本島のナークニーへの影響など、いっぱい考えるきっかけになりました。
ありがとうございます!
落平、次回訪沖時には行きたいと思いますので、その時はよろしくお願いしますね。
Posted by たる一 at 2015年03月04日 08:11
at 2015年03月04日 08:11
 at 2015年03月04日 08:11
at 2015年03月04日 08:11※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。