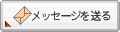2005年11月05日
安波節
安波節
あは ぶし
aha bushi
語句・あは 国頭間切安波村。現在は沖縄県国頭郡国頭村にある村。東海岸に面し、安波川と普久川が太平洋に流れ込むあたりに位置する。かつては「あふぁ」と発音していた【沖縄語辞典】ので、「あふぁぶし」と読んだり、歌っても問題はない。
一、安波のまはんたや(ハリ)肝すがり所
あはのまはんたや(はり)ちむすがり どぅくる
'aha nu mahaNta ya (hari) chimusugari dukuru
○安波の真の崖(絶壁)は心に風にあたって涼むところである
語句・あは 安波村。「あふぁ」とも発音する。・まはんた 真の崖。<ま。真の。+ はんた。崖。切り立った崖。絶壁。安波村の清水山(そーじゃやま)の東側が絶壁になっている。その上にかつては毛遊びが盛んに行われた広場がある。「はんた」は「崖」であり「端」という意味があり、崖そのものよりもその上にある場所を示すことが多い。(例)「はんたばる」(「険しい高地の畑」【琉球語辞典】。)・ちむ 心。・すがりどぅくる 風に当たって涼むところ。<すがり<すがりゆん。「風に当たる[風に当たって涼む]」【琉辞】。+どぅくる<とぅくる。所。
二、宇久の松下や 寝なし所
うくぬ まちしちゃや になしどぅくる
'uku nu machishicha ya ninashi dukuru
○宇久の松下は寝てしまう所
語句・うく 奥。「宇久」と当て字がしてあるが、この広場の「奥」に大きな松があったという。その辺りのこと。になしどぅくる 寝てしまう所。<に<にんじゅん。寝る。+なし<なしゅん。〜してしまう。接尾語として。単純に「寝る所」ではない。
三、安波の祝女殿内 黄金灯篭下げて
あはぬ ぬんどぅんち くがにどぅるさぎてぃ
'aha nu nuunduNci kuganiduru sagiti
○安波の祝女(ノロ)のお屋敷に黄金の灯篭下げて
語句・ぬんどぅんち 祝女(ノロ)のお屋敷。<ぬん<ぬーる。ノロ。+ぬ。の。が詰まった言い方。nuuru nu→nuN。琉球王朝時代から地域の神事を司る人(女性)を「ぬーる」と呼んだ。「ノル[宣る]」「イノル[祈る]」などと同源【琉辞】。そのお屋敷といっても住んでいるわけではなく神事を行う家の事。・くがに 黄金色の。または火が灯った状態。さらに「大切な」の意味がある。・どぅる 灯篭。<どぅーる<「とぅーる」(灯篭)の連濁。
四、うりが明かがれば 弥勒世果報
うりがあかがりば みるくゆがふ
'uri ga 'akagariba mirukuyuugahu
○それが 明るくなれば 豊年だ
語句・うり それ。・あかがりば 明るくなれば。<あかがゆん。明るくなる。・みるくゆがふ 「幸せで豊かな理想の世界」【琉辞】。みるく<みろく「弥勒[釈迦入寂の56億7千万年後にこの世に下生〈来臨〉が待望される菩薩〈サンスクリット語でMaitreya(<maitri〈慈愛〉<mitra〈友〉)〉]沖縄では豊穣をもたらす来訪神とされ、その化身としての布袋〈ほてい〉の姿で豊年祭に‘登場’する」【琉辞】。いわゆる沖縄での「みるく信仰」で信じられている豊年の世の中。

(安波村のマハンタ公園)
子どもからお年寄りまで、三線を始める人はこの歌のお世話になることが多い。
民謡のコンクールでは新人賞の課題曲になる場合が多い。
音階は沖縄音階ではなく律音階。
しかし意味深なところもあるのだ。
実際に安波村にいってみるとわかるが、太平洋を目前にして、川が流れ込み、その海の風があたるところに清水山(そーじゃやま)の断崖がある。
その周りに村落がある。清水山の断崖にあがっていく道は急で、お年寄りはどうやってあがるのかと思うくらい。
風の当たるところにマハンタ公園があり、松の木が生えている。
公園の裏手に、今やコンクリート造りの祝女殿内がある。
「になしどぅくる」というのは、ただ「昼寝」という意味ではなく、
恋人たちの寝る場所という意味がある。
たしかに、その公園は昔から「毛遊び」(月夜に村の若い男女が三線で歌い踊り酒を酌み交わす異性交遊。本土でも昔は行われていた。)の場所。
そこで知り合った男女が、人目を忍ぶには「裏の松の下」はちょうどよさそうだ。
とはいえ、「子どもから」唄うこの歌を「恋の歌」「遊び歌」と言い切るのも少しはばかられる。
歌には奥にこめられた人々の「想い」がある。
これを唄う方は是非一度この安波村と歌碑を訪れて欲しい。

(公園の中にある安波節の歌碑)
【このブログが本になりました!】
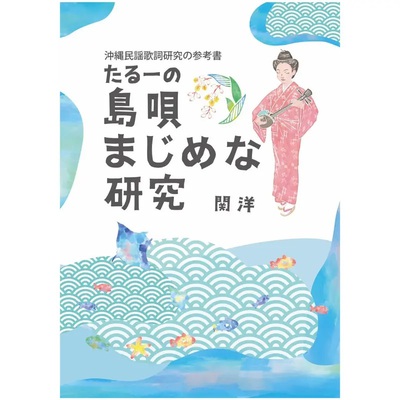
書籍【たるーの島唄まじめな研究】のご購入はこちら
あは ぶし
aha bushi
語句・あは 国頭間切安波村。現在は沖縄県国頭郡国頭村にある村。東海岸に面し、安波川と普久川が太平洋に流れ込むあたりに位置する。かつては「あふぁ」と発音していた【沖縄語辞典】ので、「あふぁぶし」と読んだり、歌っても問題はない。
一、安波のまはんたや(ハリ)肝すがり所
あはのまはんたや(はり)ちむすがり どぅくる
'aha nu mahaNta ya (hari) chimusugari dukuru
○安波の真の崖(絶壁)は心に風にあたって涼むところである
語句・あは 安波村。「あふぁ」とも発音する。・まはんた 真の崖。<ま。真の。+ はんた。崖。切り立った崖。絶壁。安波村の清水山(そーじゃやま)の東側が絶壁になっている。その上にかつては毛遊びが盛んに行われた広場がある。「はんた」は「崖」であり「端」という意味があり、崖そのものよりもその上にある場所を示すことが多い。(例)「はんたばる」(「険しい高地の畑」【琉球語辞典】。)・ちむ 心。・すがりどぅくる 風に当たって涼むところ。<すがり<すがりゆん。「風に当たる[風に当たって涼む]」【琉辞】。+どぅくる<とぅくる。所。
二、宇久の松下や 寝なし所
うくぬ まちしちゃや になしどぅくる
'uku nu machishicha ya ninashi dukuru
○宇久の松下は寝てしまう所
語句・うく 奥。「宇久」と当て字がしてあるが、この広場の「奥」に大きな松があったという。その辺りのこと。になしどぅくる 寝てしまう所。<に<にんじゅん。寝る。+なし<なしゅん。〜してしまう。接尾語として。単純に「寝る所」ではない。
三、安波の祝女殿内 黄金灯篭下げて
あはぬ ぬんどぅんち くがにどぅるさぎてぃ
'aha nu nuunduNci kuganiduru sagiti
○安波の祝女(ノロ)のお屋敷に黄金の灯篭下げて
語句・ぬんどぅんち 祝女(ノロ)のお屋敷。<ぬん<ぬーる。ノロ。+ぬ。の。が詰まった言い方。nuuru nu→nuN。琉球王朝時代から地域の神事を司る人(女性)を「ぬーる」と呼んだ。「ノル[宣る]」「イノル[祈る]」などと同源【琉辞】。そのお屋敷といっても住んでいるわけではなく神事を行う家の事。・くがに 黄金色の。または火が灯った状態。さらに「大切な」の意味がある。・どぅる 灯篭。<どぅーる<「とぅーる」(灯篭)の連濁。
四、うりが明かがれば 弥勒世果報
うりがあかがりば みるくゆがふ
'uri ga 'akagariba mirukuyuugahu
○それが 明るくなれば 豊年だ
語句・うり それ。・あかがりば 明るくなれば。<あかがゆん。明るくなる。・みるくゆがふ 「幸せで豊かな理想の世界」【琉辞】。みるく<みろく「弥勒[釈迦入寂の56億7千万年後にこの世に下生〈来臨〉が待望される菩薩〈サンスクリット語でMaitreya(<maitri〈慈愛〉<mitra〈友〉)〉]沖縄では豊穣をもたらす来訪神とされ、その化身としての布袋〈ほてい〉の姿で豊年祭に‘登場’する」【琉辞】。いわゆる沖縄での「みるく信仰」で信じられている豊年の世の中。
(安波村のマハンタ公園)
子どもからお年寄りまで、三線を始める人はこの歌のお世話になることが多い。
民謡のコンクールでは新人賞の課題曲になる場合が多い。
音階は沖縄音階ではなく律音階。
しかし意味深なところもあるのだ。
実際に安波村にいってみるとわかるが、太平洋を目前にして、川が流れ込み、その海の風があたるところに清水山(そーじゃやま)の断崖がある。
その周りに村落がある。清水山の断崖にあがっていく道は急で、お年寄りはどうやってあがるのかと思うくらい。
風の当たるところにマハンタ公園があり、松の木が生えている。
公園の裏手に、今やコンクリート造りの祝女殿内がある。
「になしどぅくる」というのは、ただ「昼寝」という意味ではなく、
恋人たちの寝る場所という意味がある。
たしかに、その公園は昔から「毛遊び」(月夜に村の若い男女が三線で歌い踊り酒を酌み交わす異性交遊。本土でも昔は行われていた。)の場所。
そこで知り合った男女が、人目を忍ぶには「裏の松の下」はちょうどよさそうだ。
とはいえ、「子どもから」唄うこの歌を「恋の歌」「遊び歌」と言い切るのも少しはばかられる。
歌には奥にこめられた人々の「想い」がある。
これを唄う方は是非一度この安波村と歌碑を訪れて欲しい。
(公園の中にある安波節の歌碑)
【このブログが本になりました!】
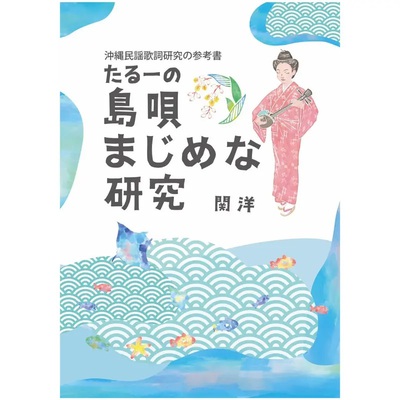
書籍【たるーの島唄まじめな研究】のご購入はこちら
この記事へのトラックバック
私が通っている三線倶楽部の課題曲には、いままで「安波節」が入っていなかったのだけど、秋に千葉県の流山の方でやるイベントに友好サークルと合同で参加するため、双方の持ち歌をす...
安波節【海翁の独り言「夏炉当然!」】at 2007年04月10日 19:53
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。