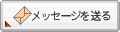2008年04月11日
月のまぴろーま節(八重山民謡)
月のまぴろーま節
つぃくぃぬまぷぃろーま ぶすぃ
tsiki nu mapiroma bushi
○月が(出て明るい)真昼間(のような夜中)
語句・まぴぅろーま 真昼間。「真昼、正午から三時ごろまで。」(石)。ここでは真夜中に月が照らし、まるで真昼間のように明るい様。
(つぃ、tsi、kiなどは中舌母音を表す。)
月ぬ真昼間や やんさ潮ぬ真干り 夜ぬ真夜中や(ハイヘー)女童ぬ潮時(ハイヘー)
つぃくぃぬまぷぃろーまややんさすーぬまふぇり ゆるぬまゆなかや(はいへー)みやらびぬすどぅぐぃ(はいへー)
(囃子は以下省略。)
tsiki nu mapiroma ya yaNsasuu nu mahweri yuru nu mayunaka ya miyarabi nu sudugi
○月が(出て明るい)真昼間(のような夜中)はヤンサ潮が1番干がり 夜の真夜中は娘の潮時
語句・やんさすー ヤンサ潮<ヤンザ潮yaNza suu 「二月夜間の干潮の甚だしい時の潮。陰暦二、三月ごろの夜間の干潮とも、陰暦十一月ごろの干潮ともいう」(石) ・まふぇり 1番干上がり。「干上がる」は辞書に「ぷぃすん」。その活用形か。
月に願立てぃてい 星に夜半参り 思いすとぅ我んとぅ 行逢しゆ給り
つぃくぃにぐゎんたてぃてぃ ふすぃにやはんまいり 'うむいすとぅばんとぅ 'いかしゆたぼり
tsiki ni gwaN tatiti husu ni yahaNmairi 'umuisu tu baN tu 'ikashiyutabori
○月に願立てて星に夜半参り 思う人と私と出会わせてください
語句・ふすぃ (石)には星は「ぷす」または「…ぶすぃ」しかない。・やはんまいり 「島うた紀行」(仲宗根幸市編著)によると「女性が男装し、男性が女装して意中の人に会わせてくれることを願い、神仏に祈願をして、その人の通る道端の暗いところに人目を忍び立つこと」・うむいす 思う人。<うむい+す。「す」は「事、物、人。連体形に続く形式名詞」(石)。・いかし 出会わせて。<いかーすぃん 'ikaashiN 会うようにさせる。出会わせる。沖縄口の「いちゃーしゅん」
思いすとぅ我んとぅ 行逢さんどぅあらば あたら我が命ゆ とぅらばちゃすが
'うむいすとぅばんとぅ'いかさんどぅ'あらば 'あたらわがぬつぃゆ とぅらばちゃすが
'umuisu tu baN tu 'ikasaN du 'araba 'atara waga nuchi yu turaba chasuga
○思う人と私と出会わせないのであれば 大事な私の命を断ちます さあいかがなさるか
語句・あたら 大事な。<あたらさーん「可惜(あたら)し。可愛らしい。」(石)。あたらむん 大事なもの。沖縄口の「あたらしゃん」(大事である)。・ちゃすが いかがするか→いかがなさるか?
東から上りおる大月加那志 沖縄から八重山まで照らしょうり
'あーるぃから'あーるぃおーる'うふつぃくぃがなし 'うくぃなからやいままでぃてぃらしたぼり
'aari kara 'aariooru 'uhutsikiganashi 'ukina kara yaima madi tirashitabori
○東からあがられる満月様 沖縄から八重山まで御照らしください
潮の満干や月からど定まみようる 島の有卦無卦やはらの主から
すぬ'んちぷぃすぃや つぃくぃからどぅさだみようる すぃまぬ'うきむきや はらぬしゅから
su nu 'Nchipishi ya tsiki kara du sadamiyouru shima nu 'ukimuki ya hara nu shu kara
○潮の満ち干きは月によって定まっておられる 島[村]の幸不幸は村の主によって決まる
語句・んちぷぃすぃ 満ち干き。<んつぃすー 上げ潮。ぷぃすぃすー 引き潮。「引く」は「ぷぃすん」。
・から「原因・理由をあらわす。」(石)。…によって。・うきむき 有卦無卦。幸不幸。はら村。「古謡に出てくる。村。」(石)。
つぃくぃぬまぷぃろーま ぶすぃ
tsiki nu mapiroma bushi
○月が(出て明るい)真昼間(のような夜中)
語句・まぴぅろーま 真昼間。「真昼、正午から三時ごろまで。」(石)。ここでは真夜中に月が照らし、まるで真昼間のように明るい様。
(つぃ、tsi、kiなどは中舌母音を表す。)
月ぬ真昼間や やんさ潮ぬ真干り 夜ぬ真夜中や(ハイヘー)女童ぬ潮時(ハイヘー)
つぃくぃぬまぷぃろーまややんさすーぬまふぇり ゆるぬまゆなかや(はいへー)みやらびぬすどぅぐぃ(はいへー)
(囃子は以下省略。)
tsiki nu mapiroma ya yaNsasuu nu mahweri yuru nu mayunaka ya miyarabi nu sudugi
○月が(出て明るい)真昼間(のような夜中)はヤンサ潮が1番干がり 夜の真夜中は娘の潮時
語句・やんさすー ヤンサ潮<ヤンザ潮yaNza suu 「二月夜間の干潮の甚だしい時の潮。陰暦二、三月ごろの夜間の干潮とも、陰暦十一月ごろの干潮ともいう」(石) ・まふぇり 1番干上がり。「干上がる」は辞書に「ぷぃすん」。その活用形か。
月に願立てぃてい 星に夜半参り 思いすとぅ我んとぅ 行逢しゆ給り
つぃくぃにぐゎんたてぃてぃ ふすぃにやはんまいり 'うむいすとぅばんとぅ 'いかしゆたぼり
tsiki ni gwaN tatiti husu ni yahaNmairi 'umuisu tu baN tu 'ikashiyutabori
○月に願立てて星に夜半参り 思う人と私と出会わせてください
語句・ふすぃ (石)には星は「ぷす」または「…ぶすぃ」しかない。・やはんまいり 「島うた紀行」(仲宗根幸市編著)によると「女性が男装し、男性が女装して意中の人に会わせてくれることを願い、神仏に祈願をして、その人の通る道端の暗いところに人目を忍び立つこと」・うむいす 思う人。<うむい+す。「す」は「事、物、人。連体形に続く形式名詞」(石)。・いかし 出会わせて。<いかーすぃん 'ikaashiN 会うようにさせる。出会わせる。沖縄口の「いちゃーしゅん」
思いすとぅ我んとぅ 行逢さんどぅあらば あたら我が命ゆ とぅらばちゃすが
'うむいすとぅばんとぅ'いかさんどぅ'あらば 'あたらわがぬつぃゆ とぅらばちゃすが
'umuisu tu baN tu 'ikasaN du 'araba 'atara waga nuchi yu turaba chasuga
○思う人と私と出会わせないのであれば 大事な私の命を断ちます さあいかがなさるか
語句・あたら 大事な。<あたらさーん「可惜(あたら)し。可愛らしい。」(石)。あたらむん 大事なもの。沖縄口の「あたらしゃん」(大事である)。・ちゃすが いかがするか→いかがなさるか?
東から上りおる大月加那志 沖縄から八重山まで照らしょうり
'あーるぃから'あーるぃおーる'うふつぃくぃがなし 'うくぃなからやいままでぃてぃらしたぼり
'aari kara 'aariooru 'uhutsikiganashi 'ukina kara yaima madi tirashitabori
○東からあがられる満月様 沖縄から八重山まで御照らしください
潮の満干や月からど定まみようる 島の有卦無卦やはらの主から
すぬ'んちぷぃすぃや つぃくぃからどぅさだみようる すぃまぬ'うきむきや はらぬしゅから
su nu 'Nchipishi ya tsiki kara du sadamiyouru shima nu 'ukimuki ya hara nu shu kara
○潮の満ち干きは月によって定まっておられる 島[村]の幸不幸は村の主によって決まる
語句・んちぷぃすぃ 満ち干き。<んつぃすー 上げ潮。ぷぃすぃすー 引き潮。「引く」は「ぷぃすん」。
・から「原因・理由をあらわす。」(石)。…によって。・うきむき 有卦無卦。幸不幸。はら村。「古謡に出てくる。村。」(石)。
八重山民謡の「月のマピローマ」。
月が真昼のように照らす真夜中、娘は会いたい彼氏と会えるよう願をかける。夜間の干潮で月の明かりに照らされて、いままで見えなかった干瀬が海から浮かび上がる。まるで娘のひそやかな願いのように。
ロマンチックな情景も、神仏に「会わせないなら命もかける」女心の高ぶりに変わる。
四番、五番はまた話の向きが変わっている。あとから加えられた歌詞なのかもしれない。
月や潮の情景をからませながら歌詞が情緒的であり、娘のストレートな思いが表現されていて、多くの節歌などとやや一線を画しているように私には思える。
月が真昼のように照らす真夜中、娘は会いたい彼氏と会えるよう願をかける。夜間の干潮で月の明かりに照らされて、いままで見えなかった干瀬が海から浮かび上がる。まるで娘のひそやかな願いのように。
ロマンチックな情景も、神仏に「会わせないなら命もかける」女心の高ぶりに変わる。
四番、五番はまた話の向きが変わっている。あとから加えられた歌詞なのかもしれない。
月や潮の情景をからませながら歌詞が情緒的であり、娘のストレートな思いが表現されていて、多くの節歌などとやや一線を画しているように私には思える。
Posted by たる一 at 17:21│Comments(3)
この記事へのコメント
安室流の工工四(大川月ぬまぴろま節)では2番までしかありません。
たしかに4・5番は感じが違うので、あとから加えられたかもしれませんね。
「安里屋節」もそうですが結末が変わっているのもあるでしょうね。
たしかに4・5番は感じが違うので、あとから加えられたかもしれませんね。
「安里屋節」もそうですが結末が変わっているのもあるでしょうね。
Posted by コロリ at 2008年04月23日 20:48
返事遅くなりました。
コメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。
Posted by たるー(せきひろし) at 2008年04月28日 16:16
at 2008年04月28日 16:16
 at 2008年04月28日 16:16
at 2008年04月28日 16:16舞踊曲の月ぬ真昼間節は極端な上げ出しですね。
また、石垣と大川では曲の尺の長さや節入り自体が途中から変わりますね。
また、石垣と大川では曲の尺の長さや節入り自体が途中から変わりますね。
Posted by くがなー at 2011年03月07日 04:43
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。